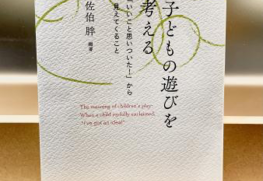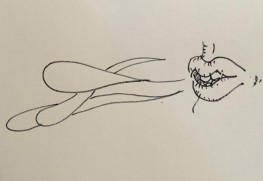画像キャプション:写真はイメージです
蕎麦の話をここに書くのはこれで3回目である。ひとつは蕎麦というよりうどんの話で、小粋なセンスが讃えられる蕎麦に対して、ずんぐりぶっとい「うどん屋の看板」について書いた。黒々と書かれた「うどん」という太い文字を見ると、日本の美意識を「あはれ」とか「幽玄」とか、はたまた秋草の美学とか言うのが馬鹿馬鹿しくなるほど、頼もしくも好ましい。もうひとつ書いたのは、関東の方は当然のこととして疑いをいれないであろう、立ち食い蕎麦の存在についてである。東京近郊を除くと、立ち食い蕎麦が当たり前のようにあるわけではない。関西、特に京都ではめったに見かけないのが立ち食い蕎麦である。京阪電車のホームにあった「比叡そば」が消えてからは、ますます寂しい情況となっている。どうしてそうした東西格差が生じたのかを考えてみた。
この文章も蕎麦がらみの話である。しかし、ちょっとしみったれた、貧乏くさい昔ばなしである。
私は九州の山奥で昭和30年代に生まれた。今から考えると本当に慎ましい暮らしで、衣食住何から何まで貧乏で節約していたような記憶がある。家には浴室もなかった。風呂はあったのだが、いわゆる五右衛門風呂で、庭に置かれたドラム缶のような風呂釜の下から火を焚いて、木の板の蓋を足踏みに使って湯に浸かった記憶がある。雨だと足元がべちゃべちゃに汚れて、ちょっと嫌だった。しかし、街中には数軒の銭湯があるので、そんなに困っていたということもない。食事も質素なものである。肉など普通に食べられるわけではなく、動物性たんぱく質といえば真っ白に塩を吹いた塩鮭が代表格で、お刺し身などはよほどのことがない限りは食べられない。醤油や塩も、それは大事に大事に使っていて、取皿に残った醤油のあまりも使いまわしていた気がする。甘みはもっと貴重だった。普通に家にお菓子が常時置いてあるようなこともなく、甘いものが欲しくなると、家族に許可をもらって砂糖水を作って飲んでいた。母親の世代は砂糖すら貴重で、「サッカリンのおっさん」と親しまれていた人物がサッカリン(砂糖の代替甘味料)で作った氷菓を売りに来るのを楽しみにしていたそうだ。
おそらく、同じ1960年代でも、東京や京都で育った方はそんなことはなかったのだと思う。しかし、いまから半世紀以上前の地域間格差は相当なものがあった。
そんな田舎でのごちそうの一つが蕎麦切りだった。「だった」と書いたものの、これは私が直接立ち会ったわけではなく、母親や祖母から聞いた話でしかないが、冠婚葬祭、あるいはそれに限らずお客をもてなすときには大概、蕎麦を打って振る舞っていたそうである。とはいえ、お米がなかったわけではない。田舎だけあって、お米はもちろんまあまああって、第二次大戦直後の食糧難のころもお米は食べられたそうだ。しかし、それでも私が幼い頃に親戚の家に行くと、来客として白米を出してくれるものの、親類たちは自分の食事としては黍を食べていた。幼少期の私は黄色い黍のご飯が美味しそうで、なんであの黄色いご飯を食べさせてくれないのかと愚図ったが、今思えば親戚の心遣いから貴重な米飯を出してくれていたのだった。白米も大事なご馳走だったが、お米と並んで特別感があったのが蕎麦切りのようだ。「蕎麦」ではなく「蕎麦切り」である。蕎麦という食材はそれはそれで結構日常的な食べ物で、蕎麦であれば特別な料理というわけではないからである。蕎麦を打って麺に切り、それをつゆとともに食べる、というのはちょっと手間も工夫も出汁も必要な面倒な料理である。だからこそ、饗応の食膳に供されたのだろう。しかしそれよりももっとお手軽な蕎麦の食べ方があった。それが蕎麦掻きである。
私自身、祖母から蕎麦切りの仕方を教えてもらっただけでなく、もっと普通に食べていた方法として蕎麦掻きも教わった。私が生まれたときにはもう亡くなっていた祖父が夜食によく食べていたらしい。熱湯をかけて蕎麦粉を練るだけなので、本当に簡単である。蕎麦粉を湯呑に入れて沸かしたての湯を少しずつ入れる。そして冷める前に急いでかき混ぜる。そこにちょっとだけ醤油を垂らして箸で食べる。それだけである。またそれだけの味だった。子供の舌にはとてもおいしいとは思わなかったが、これまた田舎では夜中にお腹が空いたからといって簡単に食べられるスナック類があるわけでもなく、またなんとなく見たことのない祖父の夜食を偲ぶような気持ちもあって、時々蕎麦掻きを作っては食べていた。
それから半世紀ほど経った。今は京都に住んでいて、徒歩圏内にスーパーマーケットもコンビニエンスストアもあるし、いろんなおいしいものには事欠かない。しかし、先日たまたま蕎麦粉を入手することがあって、本当に久しぶりに蕎麦掻きを作って食べた。蕎麦掻きは蕎麦屋さんでもメニューのなかに見かけることがないわけではない。ただ、小さい頃の、さしておいしくもない蕎麦掻きの記憶があったうえに、蕎麦屋の蕎麦掻きはやたらと値段が高い。何でこんな田舎の貧しい食べ物に何百円も(ときには1000円超も)払わないといけないのか、と半ば義憤すら感じていた。そんなこんなで、数十年間、蕎麦掻きにはご無沙汰していたのだが、蕎麦粉もあることだし、久しぶりに自分で蕎麦掻きを作ろうと思い立った。
すると、何と意外なことに、大変おいしい。蕎麦粉の香りもよく分かるし、下手な蕎麦切りよりもずっと蕎麦の味が楽しめる。ああ、おいしい! なんでこんなおいしいものを長年放置していたのだろう。
その時は昔のように醤油を垂らして、というのではなく、蕎麦つゆをかけたのが美味の理由かもしれない。またひょっとしたら、かつて作っていた蕎麦掻きの蕎麦粉は挽いてから時間が経って劣化していたのかもしれない。しかし、そもそもの蕎麦の味がおいしいものであることに、歳を取ってようやく気がついたのだろう。食べ物の味わいの記憶は、ほとんどおいしかったはずのものが実はそれほどでもなかった、と裏切られることが多いだけに、蕎麦掻きの発見(再発見)は新鮮な驚きであった。
貧乏な生活の慎ましい食べ物とばかり思っていた蕎麦掻きだが、蕎麦掻きの味わいを再認識するとともに、入るのに苦労した五右衛門風呂も、その熱い風呂釜とひんやりした外気の風がなつかしくなる。蒸し暑い夏の夜に吊った蚊帳も、布地を透かして入ってくる月の光のさやけさが思い出される。わびしい田舎暮らしどころか、実は何もかもがとんでもなくありがたい生活を享受していたのではなかったか、という気になってきた。連日35度超の酷暑のなか、冷房なしでは生きていけないという実感がある反面、貧乏で不自由で手間のかかる生活の良いとこ取りをしたい欲望が抑えられない。
しかし、これはきっと、昭和の暮らしを懐かしむほどまで快適な生活に溺れてしまったのではないか。他にも同じような、ほどほどに不自由な生活なら、また味わってみようかという大人は増えているのではなかろうか。だからこそ、グランピングとか移住とかが流行るのだろう。なんだか、日頃から胡散臭く感じていたエコでロハスな生活がありがたく思えてきた。ああ、困った。すっかりどっぷり回顧モードになってしまった。もはやおしゃれな蕎麦掻きは当分おあずけにして、緑のたぬきでも食べて寝ることにしようか。