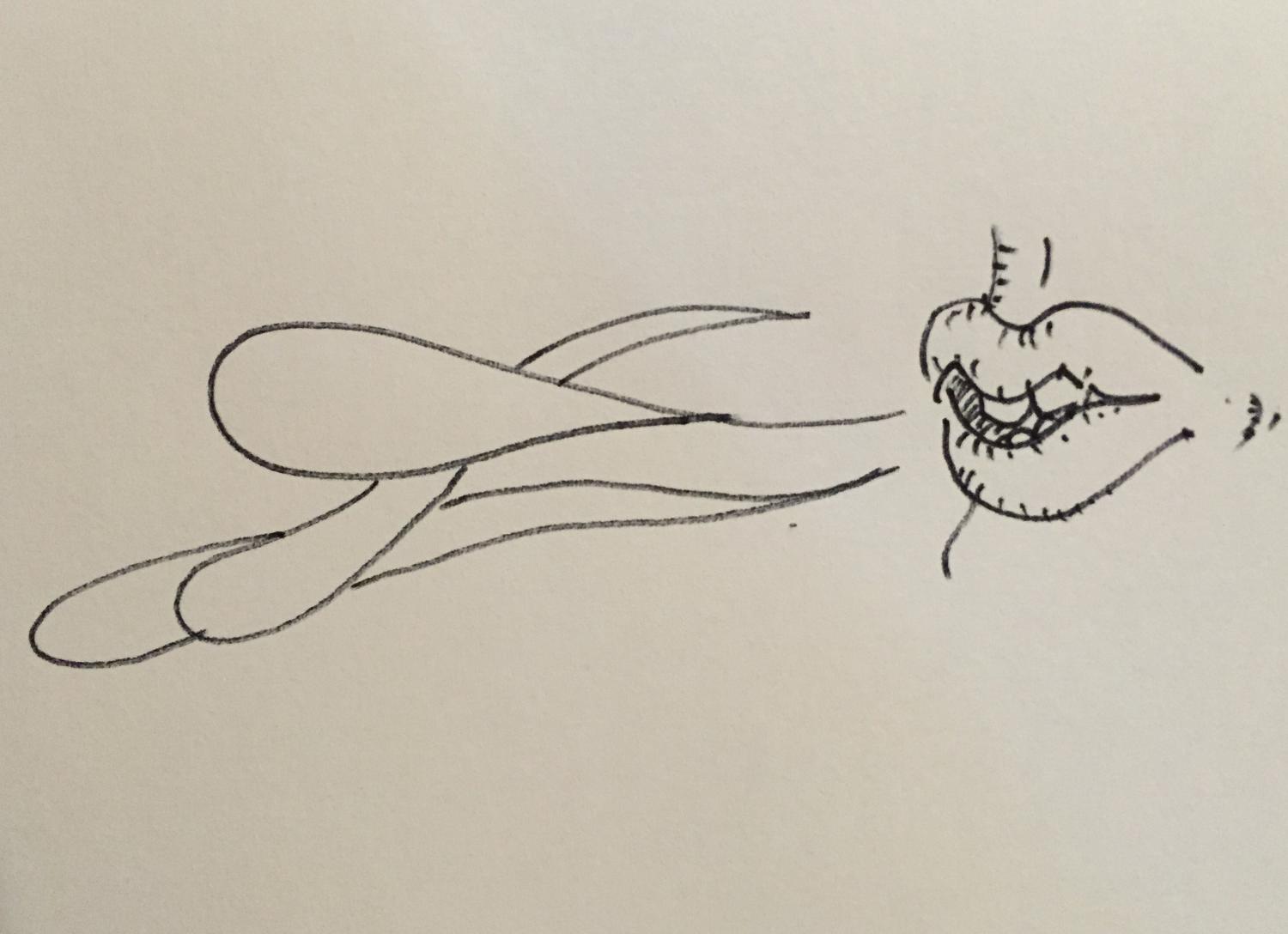
(2015.09.27公開)
最近はあまり顔を出せていないが、大阪に拠点をもつNPO法人近畿近畿水の塾は、市民活動を始めたばかりの私にとっては、学校のようなところだった。そこには近畿一円の、河川環境・水辺環境に関心のある市民、専門家、公務員などが集まっていつも情報交換したり議論を戦わせたりしていた。シンポジウムの企画などもよくやっていた。中心メンバーの一人である久保田洋一さんは都市計画の専門家で、住民参加のためのワークショップの実務で取り組まれていた。私たちはそこで久保田さんからワークショップのファシリテーョンを学んだのだった。世間でコミュニティ・デザインが話題になる15年ほど前だろうか。まだ20世紀の末頃のことだった。
ワークショップについて詳述することはしないが、そこで学んだのは、声の大きなおじさんや顔役の意見だけでなく、声の小さなふつうの住民の意見や知恵を拾い上げること、さらには立場の異なるいろいろな人の言葉を出会わせること、そんなことを可能にする場作りの方法であった。それは学級会的な議論のしかたとは全然違うものであった。多様な人々がフラットな立場で意見とアイディアを出し合えるようにするための、参加者に共有してもらう心がけ、議論のルールといったものを教わった。それは「しりあう」「リラックス」「つぶやく」「ききあう」「否定しない」という5項目であった。これは今でもワークショップ型の演習をするときに使わせてもらっている。フラットで創造的な場を作る上で大事なことが簡明に表されていると思う。
今回注目したいのは「つぶやく」「ききあう」である。一つのテーブルで、模造紙を囲んでみんなでいろんなアイディアを出すときに、「つぶやく」。そしてそれを「ききあ」って活かしたり、ヒントにしたりする。ちょっとした言葉が非公式な形で場に現れるのを許容し、それを活かす、ということである。トーキング・オブジェクトによって話者が設定されるワールド・カフェの方法と少し異なるところだ。
この久保田式ワークショップにおけるつぶやきは、「誰かに語りかける」という言葉ではない。もちろんそういう言葉も場において活かされていくのであるが、意見としてまだまとまりきっていない、朗々と述べることのできない不定形のものも、場において受け止めるということである。このことが「否定しない」とあいまって発言をしやすくし、多様なものをテーブル上に呼び寄せることになるのである。特定の聴き手は想定されないが、場において共有される断片的な言葉、としてこの場での「つぶやき」がある。
「つぶやき」は「ひとりごと」に似ているが、少しちがう。「ひとりごと」の聴き手は自分自身である。「つぶやき」はほとんどひとりごとのように発されるが、かすかに誰かが聴いていることが本人に予感されている。それは目の前にいて目を見て聴いている人ではないかもしれない、しかしある特定の一人ではなく、場にいる数人の耳にはひっかかっているかもしれない、そういうことばである。向かい合って買わされる言葉が単一指向性の言葉だとすれば、「つぶやき」は無指向性の言葉だといえるだろう。
「つぶやき」は小声でなされる印象がある。大声で相手のいない言葉を吐き続ける人は、ちょっとどうしたんだろう、という目で見られる。私もときどきそういう目で見られるが、それは大きな声は、相手に聴かせるためのもの、という了解が一般にあるからだろう。物理的な音声の場合、一般に小声だと到達距離は小さい。しかしそれは誰も聴いていないということではないし、聴かせるつもりがないというわけでもない。むしろ小ささは、これは特定の人に話しかけているのではありませんよ、という身振りなのかもしれない。実際、ふたりしかいないときにつぶやかれる言葉というのは、実質的には聴き手は決まっているのだが、まるでその人には語りかけていないかのようなふうな装いでつぶやかれる。
また先にあげたように、「つぶやき」は多くの場合断片的である。論理的なつながりをもった一連の論述という形はとらない短くて余白のある言葉である。途切れているようでもあり、誰かの「 」を待つようでもある。「つぶやき」は目の前の人と話すときの言葉、大勢の人に語りかけるときの言葉、それらの明瞭でつながりのある言葉とはずいぶん趣の違う言葉である。
「つぶやき」は、断片的で、定められた聴き手を持たぬかのように発されるひそかな言葉であった。それは、ちゃんと筋道立てて話すとか、相手の納得と合意を得つつ云々といった、「機能的な」言葉の運用とは異なるもののように見える。しかし、こういう言葉が有効に働く場があることは、先のワークショップにおける「つぶやき」の意味のところで見たとおりである。
ここまで読んでくださった方々は当然思い至っているだろうが、ネットにおけるtwitter上の言葉も、この「つぶやき」によく似ている。twitterという語は日本語の「さえずり」にあたるのだそうで、スピーカーの高音部を受け持つ一番小さいやつ「トゥイーター」というのは、これらしい。「さえずり」というと甲高い小鳥の声のようであり、「つぶやき」とはずいぶん雰囲気がちがう。鳴き交わしのイメージなのだろうか。これも樹々の間にばらまかれる対象の定まらない声なのかもしれない。にしてもツイートが「つぶやき」とされたのはなかなか妙味を感じるところである。
twitter上での「つぶやき」がとりあえず届くのは、そのフォロワーの範囲に限られる。特に誰かに話しかけたい時は@をつけたメンション(返事の場合はリプライ)を送るが、これはフォロワーの人々の人垣の中で特にその人の名を呼ぶことになる。時に、ある人を想定してのほのめかしを含みつつ、@のない無指向性のつぶやきとして放流される言葉がある。こうしたものはリプライの形をとらないリプライとして「エアリプ」と呼ばれたりする。当の人以外には、一般的なツイートか、あるいは意味をなさないものとしてしか受け取られない。もしかしたら、当の人にもそのようにしか受け取られないかもしれないが、それでも発語されるのだから、ひとりごとのようでいてなかなか意志のこもったことである。それは現実におけるある種の「つぶやき」と変わるところがない。
twitterの140字制限は、かつてのポケベル的・ガラケー的な文字メッセージサービスの名残なのだそうである。今日の水準で考えれば、トラフィックの問題はあるのかもしれないが、より多い字数を交し合えるようにするのは簡単なはずだ。ほかのSNSにはそんな制限はないようにみえる。他のサービスと組み合わせたり、「連投」という形をとることでこうした制限は克服することはできる。とはいえ、この短文であるがゆえの舌足らずさが、このサービスの独特の魅力につながっていることは間違いない。それはその断片性であり、余白である。
twitterでの発話には、政治について論を立てるようなものももちろんあるけれども(そしてその役割も大事なのだけれども)、おかしたなものをたまたま見つけたり、美しい夕日を見たりといったときに、「おもわず」といった感じで放たれるものも多い。それは論壇に上がって大きな声で話し始める、といったものではまるでなく、まさに「つぶやき」である。
一方facebookのエントリーは、twitterに比べて「発言する感」が強いような気がする。もちろんSNSとしての自由さはあるのだが、twitterと少し雰囲気がちがう。同じテーブルであっても、facebookの方は、「トーキングオブジェクトが回ってきている私」として発言しているような、ワールドカフェっぽい雰囲気がある。twitterの方は久保田式つぶやきに似ているような気がする。
断片的で、余白が多くて、あまり長くなくて、誰に言ってるんだかよくわからない言葉、といえば、twitter以外にも思い当たるものがある。前回の私のコラムにつながってくるのだけれど、詩の言葉に少し似ているように思うのである。詩語というのは実用的な機能をほとんど持たないようにみえる。それはなんの証拠も提示しないし、仮説を検証してくれるわけでもない。しかし不定形の「つぶやき」がワークショップにおいて一定の積極的な役割を演じていたように、それはなんらかの場において有効な言葉でありえたはずのものだと思うのだ。久保田式ワークショップではそれは、アイディア生産と同時に、立場を超えた理解と合意の形成といったところだった。詩の言葉がそんなに明瞭に企図された社会的機能を持つとは限らないが、というかそういうものを裏切っていくものだと思うが、それでもそうした言葉が、越境的、横断的に響き、ある人たちの耳に捉えられ、次の何かに関わっていく、ということはありうるのではないか。こうした詩的な言葉とそれに関する想像力を、単に個人的な内奥の問題としてだけでなく、テーブルの上でこぼれだし、共有されるものとして捉え直すことはできないか。
「つぶやき」は聴かれることを、「 」を待つ言葉でもあるが、それをかならずしも確かめるような言葉でもない。人ではないものの「 」を待つことだってあるかもしれない。それは別に怪談じみたことを言っているのではなくて、風土との交流というのは、共同体の言語においてはそのような形式をとるのではないだろうか(中路正恒責任編集「地域学への招待」の詩をめぐる議論はそうしたところに繋がっていくのではないか)。和歌や俳句の「つぶやき」性を思うと、そうした叙景が日本の詩歌の相当部分を形作ってきたのかもしれないとも思うのである。
地域や環境に関わる人は、その土地をめぐる「つぶやき」を風土と人々の間に見出し、余白を想像する力が必要なのではないだろうか。その土地自体を模造紙の広がりとした「つぶやき・ききあう」試みが、風土を機能的に消費してしまうことや、その豊かなディテイルを捨象してしまうことから救い出すものがあるはずである。






