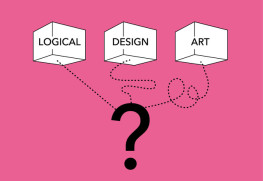(2016.05.08公開)
「レポート」という文章のジャンルがある。学校勤めをしていると、この書き方がわからん、辛い、さらには嫌で嫌でたまらない、といった苦情を持ち込まれることがある。レポートが苦手なばかりに、教科書も教員も学校も嫌いになるということすらあるだろう。桜花の咲き誇るころ胸膨らませて入学したのに、青葉の瑞々しさ滴るころにはもうレポートのせいで学校嫌いになるというのは、陽気ますます盛んになる季節とは裏腹の、実に残念な事態である。レポートへの苦手意識は、世の中で決して珍しいことではないのだろう。実際、論文やレポートを書くための参考書や手引きは数多く出ている。それだけ需要があるのだろう。
レポート指南の書物は、読めばそれぞれに良書である。学識ある著者たちが長年の経験を踏まえて懇切に明快にレポートの書き方を説いている。さまざまな教育現場でもきっとそれぞれに導入的な科目を用意して、レポートの書き方を教えているのだろう。それなのに、レポートが苦行である学生が減らないのはどうしてだろうか。新入生だけでなく、卒業間近の学生にとってすら、四苦八苦している学生は珍しくない。
おそらく理由には2種類のものがあるだろう。そしていずれもレポートの問題提起とか論理構成とかの以前の理由だ。
ひとつはレポートというジャンルの存在意義が理解できない、という問題である。「レポート」というからには何事かを報告するものだし、その報告は書き手の勝手気ままな意見や「私の思い」を語るものではない。あくまでレポートしようとする何かに即してその実情を伝えようとする文章であって、自分の思想を披瀝する場ではないのである。ところが他方でややこしいことに、レポートは個人の信念を綴るものではないとしても、個人の責任で著されなくてはならない。どういう情報をどこから得ているのかを示しつつ、それに対して自分がどういう立場で書いているのかはっきりさせなくてはならない。無責任な匿名者のレポートであっては信用できないのである。しかし世間には思想家でなければ無責任男が溢れている。いや実際には、誰の心のなかにも無責任な思想家が居座っていると言うべきか。自分の責任できちんとした報告文を作るというのは、どんな職業であっても、またいくつになってもなかなか面倒な仕事である。本当のところは、まさにそのややこしい仕事をこなすことができるようになるために、レポートの書き方を学ぶのだ。そうはいっても、またそれだからこそ、レポートの書き方を習得するということは誰にとっても不慣れで億劫な仕事なのである。そこには世の趨勢に逆行するような原理的な困難がある。
もうひとつの問題は、まさにその「趨勢」に関わる。趨勢とは方向をもった運動である。運動は、一旦それに慣れてしまうとなかなか逆らえない。レポートを書くという作業が難しいのは、その意義や性質が頭で理解できていないからというだけではない。そもそも「しんどい」のだ。人間はふだんは積み上げてきた経験を踏まえて行為する。いちいち立ち止まって判断しなくてもすむからだ。人生に日々立ち現れる諸事全般をひとつひとつ熟慮して、しかるのちに断行するほど人間はヒマではない。大体のところで見当をつけて、さくさく行動することで、本当に大事な局面での自由な意志決定に時間を割くことができる。ルーティン・ワークや惰性的な行動、要するに習慣のおかげで、自分の時間を稼いでいるのである。レポートはそんな速やかな判断とは違い、七面倒臭いプロセスを要求される。客観的な記述、証明や検証、説得のための手順など、大空を思いのまま飛翔しようとする心の働きにくびきをつけて、地面に縛り付けるようなものだ。そんな煩わしいことを常日頃やってられない。先入観を疑わず、慣例にしたがった即断即決こそが楽だし、そうしていないと苦痛なのだ。
他方で、これは裏を返せば、そんな辛気くさい仕事ではあっても、レポートはある程度の習慣づけで改善できるところもある、ということになるのではないか。習慣の問題を解決するのは習慣である。勿論、役にも立たない習慣を身につけるのは大変そうにも見えるが、嗜好品や趣味道楽などに溺れていく人の多さを見るにつけても、人間は案外あまり役に立たない習慣にも親しめるのではないか。
書くことは、思考の動きでもあるが、同時にそれは身体運動でもある。考えをあれこれとまとめ、伝えるという作業は、言葉を句切って順に発話したり、筆記したりする中で可能となる。言葉を繰り出す適切なリズムやスピードがあってはじめて、思考が思考になる。思いつきやひらめきは瞬時のもので、取り返しがつかないし、他人にはおろか自分にも伝わらない。どんなに可能性をはらんだアイデアでも、どんなに凝縮した直観でも、それは録音の超高速再生にも似ていて、まだ十分な思考に展開していない。伝達可能で参照可能な思考は火花というよりも水の流れに近い。言葉という、否応なしに発話や筆記の物理的な運動と結びついたものは、その流れにとって抵抗となる場合もあるが、むしろそれは障碍物というよりも、流れを方向付け、水の豊かさを支えるものである。どこで声を出し、どこで息を継ぐか。どこで語気を強め、どこで音を延ばすか。そうした一連の言葉を繰り出す動きは、考えるスタイルも作り出す。性急過ぎて早口にまくし立てる思考は放恣な惰性に流れる。かといって鈍重に途切れがちなら思考は停滞し行き先を忘れてしまう。緩急を意識的につけつつ、語り手と聞き手(書き手と読み手)の呼吸を整えてゆくことが、結果的に伝わる内容の文章を作ることになるのではないだろうか。相手を思いやりつつ呼吸を合わせる。器楽の合奏や球技のラリーでのように、言葉を発しては反応を待ち、相手の様子を感じ取りつつ、次の言葉を投げ返す。そうした息づかいを持つだけで、不断の性急な生活から一歩踏みとどまって、静かに語りあうモードへと態勢を転換することが可能になる。文体の「体」は書き手ひとりのものではないのだ。思考する文章、そしてまたレポートは、仮想の読み手と息を合わせて共同で作る、ひとつの運動体なのである。