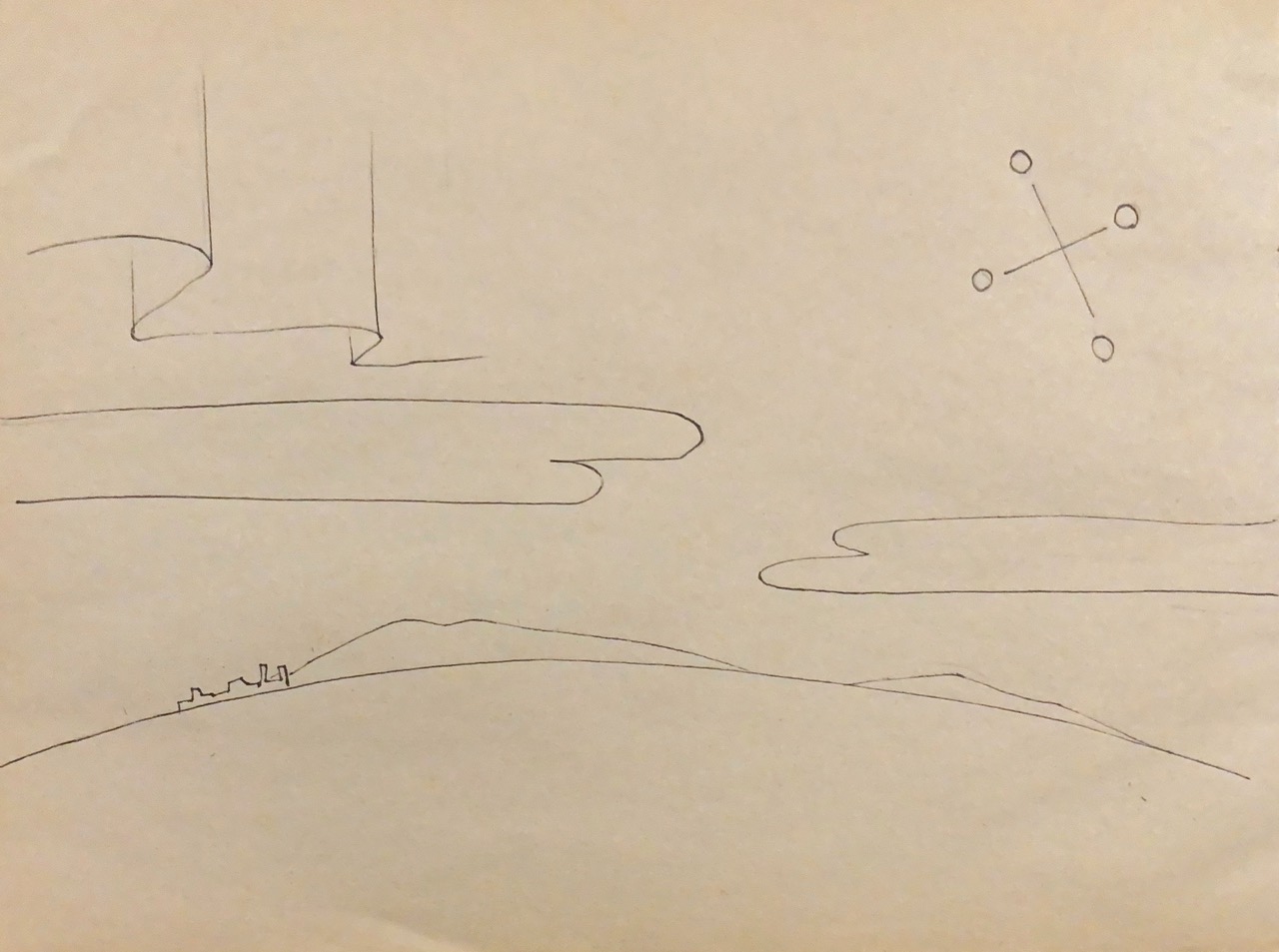
2024年になって、はや一月が経つ。一月というのは、毎年思うのだけれど、長いのか短いのかわからないところがある。あっという間だった気もするのだが、元旦などは遠い昔のような気もする。
一月以上向こうに流れ去ってしまった2023年であるが、多くの音楽家が亡くなった年でもあった。まず思い出すのは青春期によく聴いた坂本龍一、高橋幸宏といった方々だが、ギタリストもずいぶんなくなった。ジェフ・ベック、デヴィッド・リンドレー、鮎川誠、トム・ヴァーライン…。中でもあとからじわじわと効いてきたのが、ザ・バンドのギタリストだった、ロビー・ロバートソンの訃報だった。
ザ・バンドについては聴いたことはあったし、ロック映画の名作と言われる「ラスト・ワルツ」のDVDも持っていた。しかしそれほど強い印象を持っていなかった。昔風のアメリカン・ロックという印象しかなかったのである。
たまたま買ったギター・マガジン誌11月号のロビー・ロバートソン追悼特集を読んでいくうちに、もう一度丁寧に聴いてみたいという気になってきた。そして改めて注意深く聴いてみると、なんとも言えない滋味に満ちた自在なアンサンブルや、さまざまなアメリカ音楽が溶け合っている様子、繊細なポエジーに富んだ歌詞、そして素晴らしい3人のボーカリストにすっかり魅了されてしまった。ギタリストのロビー・ロバートソンはこれみよがしな長いソロは弾かないが、多くの曲の作詞作曲を手掛けている。そしてこの人の構想力に、このバンドの秘密があるようなのだ。
ザ・バンドの音楽の中にはさまざまなアメリカ音楽が渾然一体となって響いている。その中にはカントリーやブルーズ、R&Bといったものだけでなく、移民たちが奏でた19世紀あるいはもっと古い民謡のようなものも含まれているらしい。それだけでなく、歌詞においてもアメリカのさまざまな時代のさまざまな人々の暮らしを歌っているようなのである。
「南十字星」と邦題が付けられたアルバムがある。もともとは「Northern Lights – Southern Cross」というタイトルで、南十字星だけでなく、北の大地でしか見られないオーロラにも言及されている。広野の焚き火に照らし出されるメンバーたちが写るジャケットの写真とあいまって、大地の広がりが主題化されていることが伝わってくる。
このアルバムに「Acadian Driftwood(アカディアンの流木)」という美しい曲が収録されている。ピッコロのような可愛らしい笛のイントロダクションから始まるのだが、曲が進展して再びそのフレーズが登場するころにはフィドルが乗ってきて、時間とともに様相を変えていく。この歌で歌われているアカディアンというのは、もともとは17世紀にカナダの最西端のノバスコシア州のあたりに入植したフランス系の人たちであったらしい。それが、18世紀半ばのイギリスの進出により追われ追われて、アメリカ南部のルイジアナに至ったという。このアカディアンの人々の苦難の流れ旅の中で聴かれるフィドルは、このルイジアナに伝わるケイジャン音楽を特徴付けるものだ。こう言ってしまうとひどく要素主義的な音楽のように聞こえるかもしれないが、ザ・バンドらしい渾然一体感のある自然なまとまりのあるものになっている。
この曲については、『ミュージック・マガジン』2023年10月号(第55巻15号)に、高橋健太郎氏が「ザ・バンドはフランス領ルイジアナを旅したバンドだった」という素晴らしい文章を書いているので、興味のある方は是非参照されたい。
ザ・バンドは一人を除きカナダ人からなるバンドである。カナダからアメリカ南部に至る空間的な広がりは、まさに「Northern Lights – Southern Cross」である。彼らはアメリカ的な音楽に精通し、アメリカン・ロックの原型を作ったともいわれるが、そこで踏まえられていたのは、カナダ人だから見えた、アメリカの多様な風土と文化、そしてそこに生きる人たちの姿だったのだろう。
1960年代末、世の中はサイケデリックで、多くのバンドが七色の服をひらひらさせて派手な音を出していた。若者たちが裸になって愛と平和を訴えていたその時代に、ザ・バンドは老人のようないで立ちで、伝統的な音楽をこれまでなかった形で混ぜ合わせながら、風土に生きる人々の姿を描き歌ったのだ。これは、まったく新しい音楽のデザインだった。
ロビー・ロバートソンは、伝統文化を掘り下げ、歴史と地域に生きる人たちの姿を調査・観察し、同時にそこから新しい語り方を編み出して世に発信する、ということをやってのけたのだ。
私が所属している京都芸術大学芸術教養学科の学びは、「デザイン思考」と「伝統文化」の両輪から成っている。「デザイン思考」を学べる大学・学科はこの10年くらいでだいぶ増えたが、「伝統文化」を併せ学べるところは、今でもここ以外にそうないだろう。この二つを有機的に関連づけて未来を構想するということを考えた時、ザ・バンドはそうした志をもった大先輩だったのだということに気付く。
関わりのある他者としての視点、徹底的なリサーチと鍛錬による血肉化、そして高度なコンセプトワークと詩精神。これらがどのように折り重なり溶け合っているのか考えながらその音楽の森に踏み込んでいくのは、ロビーが提示した風土像の中を旅することでもあるのだろう。
ロビーは、バンドを抜けた後は、映画音楽の仕事を多く手掛けながら、自身の出自であるネイティブアメリカンの文化の紹介と振興に努めたという。風土に生きる人々のありようについて考えることは、彼にとって終生のテーマだったのだと思う。






