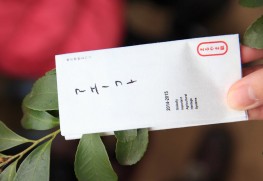3)松井さんのこれまで2
「民芸」と「八木一夫」
大学時代の松井さんには、もうひとつ大きな出会いがあった。棟方志功への関心から行き着いた「民芸」である。なかでも特に、陶芸家の河井寛次郎に惹かれていった。
——河井寛次郎の記念館に行って感動して、河井寛次郎になろうと思ったんです。1年生のときやったな。僕にとって河井寛次郎は陶芸家というよりは彫刻家に近くて。造形も好きやったし、ねばっこい感じとたくましい感じがすごく好きだった。青森の棟方志功、漂泊の山下清、そして河井寛次郎。全部一緒になって、これは民芸運動をせなあかんと思った。
民芸運動を始めたひとたちはものすごくハイカラで、近代主義の先頭に立ってたでしょ。ロダンを日本に紹介したのは白樺派だったし。今考えられてる民芸と、当時の民芸は絶対に違ったと思う。今に置き換えると、ナガオカケンメイとか、原研哉がやってるような仕事を当時やってたわけですよ。めちゃくちゃ格好いい運動だったと思う。
2年生で自治会長になった松井さんは、自治会の運動と民芸運動を重ねて見ていた。執行部のメンバーを各学科から揃えるなどして、芸術運動体のようなイメージを持っていたのだった。
——2年の夏に、民芸にも関わりのある丹波の立杭焼に弟子入りしたんです。
きっかけは、1年の冬休みに読んだ河井寛次郎の本。『六十年前の今』ですが、彼のふるさとの大山のことが書いてある箇所を夜中に読んでいて。「すっきりと大空にそびえたつ、火山独特のあの円錐形の姿はこんな土地に産みつけられた人々にはかけがえのない大きな賜物であった。出雲にはやさしい母、伯耆には厳しい父」と書いてあって、ひとつの山がふたつの視点によってまったく違う表情! これは行かなあかんのちゃうの、と。夜中の2時に思い立って、「心配しないでください」と書き置きして、寝袋持って、翌朝には家を出たんですよ。
始発の山陰線に乗って、大山周辺の民窯や河井寛次郎が修行した窯場などを訪ねながら、1週間ほど暮らしたね。その途中で偶然知り合った陶芸やってるひとに、丹波だったら弟子入り紹介できるよと言われて。それから準備に入って、夏に丹波の陶芸家・市野さんのところに行ったわけです。
そこは「蹴ろくろ」でつくる伝統的な工房でね。朝6時から8時まで土もみして、8時に朝食、夕方まで仕事して5時に犬の散歩、晩ごはんの後に蹴ろくろの練習という生活を2ヵ月してたの。「こんなこともできひんのか!」って職人に怒られながら。でも最後には、もむのがものすごく難しい丹波の土をもめるようになって、蹴ろくろも高台削りもできるようになって、秋に大学に戻ったの。そうしたら担当だった近藤豊先生に「こんな高台どこで習ってきた!」と怒られて、京風に戻させられた。京風は楚々とした感じで、全然違うんですよ。
民芸のものづくりが少し身についたところで、京風に戻される。民芸の作家になるか否か、分かれ目である。ところが松井さんは第3の道を見つけてしまう。
——その年の12月、陶芸科の八木一夫先生の展覧会が「立体ギャラリー射手座」であって、観に行ったの。それにすごい衝撃を受けて、民芸のものづくりじゃなくて、オブジェをつくろうと思ったんです。
「立体ギャラリー射手座」は1969年に前衛芸術を扱うギャラリーとしてオープンしてから、当時は絵画や彫刻など美術作品の展示をよく行っていた(2013年に閉廊)。陶芸の従来の枠にとらわれず、自由な造形を行う八木一夫さんの作品との出会いは、松井さんにとって決定的なものとなった。工芸のなかの陶芸ではなく、広い意味でのアートとしてある造形。大学3年以降、松井さんは八木一夫さんに師事し、土による立体制作を模索することになる。
——もし八木一夫展に行ってなくて、そのまま民芸やってたら、全然違う世界に行ってたと思うな。今ごろ菜の花の咲くような田舎に住んで器つくって、大金持ちですよ。
当時は欧米ではミニマルアートやプライマリーアートが盛んで、日本でもミニマルな世界とモノ派が面白かったから、陶芸でそっちのほうをできないかと考えてたなあ。(先生である八木一夫や鈴木治が関わっていた)走泥社でも伝統工芸でもない、彫刻の世界に憧れてた。日本はずっと彫刻が元気だったんですよ。野外彫刻も盛んだったし、彫刻世界に興味があったから彫刻家になりたかったんです。
民芸に関心は残しつつ、彫刻的陶芸にかける思いは大きかった。こうして松井さんの目は、日本の内と外の両方に向けられていく。