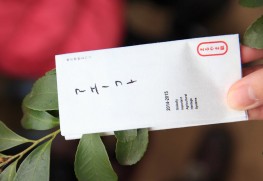2 )売上だけではない本屋
かつての書店が持っていた公的な役割を、市が保護し、運営する。市民の文化レベルを守り、高めるという意味では八戸ブックセンターの存在意義は図書館にも通じる部分がある。
いちばんの問題は、公共性と経営の間には大きな溝や矛盾が存在するということだ。
売上や集客を無視して税金を投入し続けるようでは市民の理解は得ることが難しいだろう。かといって売上を重視しサービス機関と化してしまえば、かつての書店が売れない人文書を切り捨て、求められるがまま雑誌やコミックの割合を増やしていったように、同センターのコンセプトはなし崩しになってしまうだろう。ここで求められているのは、市民を啓蒙し、これまでになかった需要を生むことだ。売上を至上命題としないことで、本屋の持つ役割や視野は大きく広がる。
———このブックセンターを立ち上げるにあたっていちばん心配したのは民間の書店とどう連携するかということでした。最初に地域の店を歩いて回って、ヒアリングをしたんです。極端な話をすれば、商売敵だと思われないかと。
地域の本屋が1階だとすれば、八戸ブックセンターはかつて市長が足繁く通った「本屋の2階」だ。1階と2階の棲み分けをすることで、街全体が大きな本屋として機能することもあるだろう。競争ではなく共存を目指せるのはこのセンターならではだ。
例えば「客注」の扱いにも特色が見られる。例えば雑誌やコミックなどいわゆる「1階」の役割とする本の問い合わせがあれば近隣の他店を紹介し、「他店にないから」という問い合わせがあればそれはデータとして保存し、八戸ブックセンターの商品構成にもフィードバックする。
館内のところどころ、書棚のなかに「わたしの本棚」という小コーナーが設けられ、地域の住民による選書本が並ぶ。ここにはライトノベルや、専門書など、同センターのラインナップには入らないような分野の本もあるが、このような区分けをすることで、お客さんの要望に応えながらも、センターのコンセプトは維持するという絶妙なバランスが保たれているのだ。
あらゆる店は客との「綱引き」が重要だ。店側の影響力が強ければその店のカラーに合わせたお客さんが増える。反対にお客さんの影響力が強ければ、店はお客さんの需要に染められてしまうだろう。そのバランスを売上とともに考える力を既存の書店は失いつつある。売上という最優先事項を一度担保することで、店側の力は格段に強くなる。やみくもな拡大を考え続けた末、出版社、取次、本屋は長いあいだそのことを忘れつつあったのだ。



テーマを決めて、8冊から10冊の本を選書する企画「わたしの本棚」は、有名無名の別なく、さまざまなひとがさまざまな視点から本をセレクト。カウンターやホームページで応募できる / 身近で親しみやすいカテゴリーで本が並ぶ。眺めて手に取り、そのまま座って読むことができる / アートディレクションを行なったグルーヴィジョンズによる本の紹介も