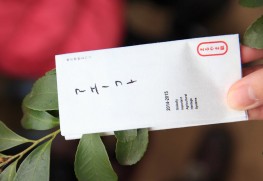4)地元のパンを食べる日常を「あたりまえ」にする
フードハブの活動の多くは、地域にもともとある食材や暮らしの営みを生かすことに重きを置く。ところが、パンと食料品の店「かまパン&ストア」はちょっと生い立ちが違っている。パンを焼こうにも、まちの人たちが食べていたのは、全国に流通する大手製パン会社の食パンである。かまパンのパン職人・笹川大輔さんは、ほとんど真っさらな状態から、「このまちのパン」をつくらなければいけなかった。特に力を入れてきたのは、毎朝食べてもらう食パンだ。



かまパンでは、レーズンと小麦粉からつくる自家培養発酵種(天然酵母)を育て、すべてのパンに入れている / いつもの食パンと超やわ食パン。朝の幸福度が確実に変わる
かまパンの食パンは2種類。湯種製法でつくる「いつもの食パン」はもっちり、ずっしりした食感で、やや酸味がある。「超やわ食パン」は、まちのおじいちゃん・おばあちゃんの「もっと柔らかいパンがいい」という声に応えて開発した。香川・大山牧場のジャージー牛乳だけで仕込んだ生地はふんわり甘く柔らかい。
当初に比べると、「いつもの食パン」の酸味はずいぶんまろやかになったのではないか。そう伝えると、「生地がこの土地の気候に馴れてきたせい」と笹川さんは言う。

かまパン&ストアの製造責任者、笹川大輔さん
———実は、以前よりも酵母の量、酸度を倍以上に上げているんですよ。「自分がつくっているパンは、自分のパンなんだ」と受け取れるようになって楽になれたし、自信をもてるようにもなりました。その結果として、ものとして伝わるパンに変わっていったんじゃないかと思います。同時に、「パンを食べてもらえる可能性を増やそう」とパンの製造量を増やしました。当然、余ることもありますが、利益とのバランスを考えて誤差の範囲に収まるのであれば配ればいい。
笹川さんは、いつお店に行ってもパンがあるように、毎日焼きつづけることに大きな意味があると考えている。かまパンに行くと、いつものパンに加えて、季節ごとの商品やパンチームが開発した新しいパンが並んでいる。休みの日や空き時間にはメンバーが試作品をつくる姿も見られる。厨房の窓の向こうに、何かが生まれてくる気配が満ちているのは、やはり「食べてもらいたい」という思いがあるからなのだろう。
かまパンが地元の味になったのは、いくつもの季節を経て生地が馴染んだせいだけではない。笹川さんたちが「地元の人に食べてほしい」と願って焼いたパンを、地元の人が「おいしい」と食べる。その応答のなかで、「地元のパン」が育まれていったのだと思う。そんなパンがあるという日常の風景をつくるのは、決してあたりまえではない。しかし、それをあたりまえのようにやってのけるのが、かまパンチームの人たちなのだ。





焼きたてのパン、採れたての野菜、フードハブの加工品やかま屋で使っている調味料など。最近はかまパンの材料である小麦粉の量り売りもはじめた / 焼きたての新鮮なパンたち。いい表情をしている / 作業の合間に、最近読んだ本を片手に語り合うかまパンチームのみなさん。こうした日常の会話から、また新しいパンが生まれてくる