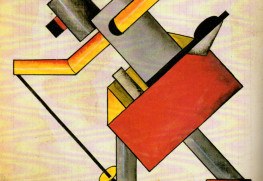(2015.11.29公開)
わたしが「能」という芸能を知ったとき、笛や小鼓の音が耳に残り、それ以来能の音楽面に興味を持つようになった。そんなわたしが能を“演劇として”観るようになったのは、恥ずかしながら自分が仕舞の稽古を始めるようになってからであった。
その日、わたしは「葵上」という演目の稽古を師匠につけてもらっていた。「葵上」は、光源氏の元愛人の六条御息所が源氏の正妻の葵を怨み、怨霊となって葵を呪い殺そうとする作品である。稽古はその一部の「枕之段」といって、御息所が葵に鬼のような嫉妬心を燃やしながら、源氏への尽きない想いを見せる場面であった。
わたしは初心者なので、稽古が始まると、いつものように舞台上で手本を示す師匠のあとをくっついていった。親ガモを追いかける子ガモのように、師匠の動きをただひたすらに真似ていく。師匠からは「次はこうして」とか「こういうふうに動いて」というような言葉がかけられるが、「こうして」の「こう」が具体的にどうであるかほとんど説明はない。足の運びの方向、足数、上半身と下半身の向き、顔の向き、扇の扱い方など自分のなりにその意味するところを推測し、できるだけ忠実にそれを再現していこうとしていった。
そのようななかで、「水暗き沢辺の蛍の影よりも、光る君とぞ契らん」という詞章のところに差し掛かった。この場面で、御息所は沢辺に光る蛍をかき分けるかのように右へ数歩、左へ数歩さ迷って、愛おしく懐かしい源氏の姿を心に想う。師匠からは「扇をこうやってかざして」「扇をかざすときは、このように上から下を見る」「かざしたら、さっと手を下ろす」などの指示が出されたが、わたしは真似ることに精一杯で、その意味するところが判然としないでいた。そうして稽古が終わって、一息ついて雑談をしていると、師匠はこの場面についてこう語ってくれた。「扇をかざした時に、上から下を覗くように見ることに定まった解釈はないのだけどね、ぼくは沢辺の水に源氏の姿を映し出していると思う。そこに源氏の幻を見ているのだと思うのだよね。」と。源氏の姿を恋しさのあまり水鏡に見ているのではないか、でもそれは一瞬のことで、源氏が消えてしまうと、御息所はかざした手をさっと下ろし沢辺から離れてしまう、というのである。
それを聞いて、わたしは思わず身震いした。「扇をこうやってかざして」や「かざしたら、さっと手を下ろす」というような簡素な所作に何と深い奥行きがあることだろう。所作だけを見れば非常に単純だけれど、その動きの内に『源氏物語』のドラマが詰まっていたのである。能の動きが単純で簡素であるのは、もしかしたら演じ手がこうして色々な解釈を示せるからなのかもしれない。抽象的な動きの連続で演じられる能という演劇には、決まりきった一つの見方はなく、演じ手や観客にその解釈が委ねられているということなのだろうか。
思えば、稽古で師匠が指示するのは動作の大筋なのであって、細部の形をどうすべきか事細かに注意することはあまりない。師匠からは表現の大きな枠組み、すなわち「型」だけが伝えられている。型という枠組みだけが伝えられることで、細部の表現は一つに固定されることがない。師匠が事細かに指示しないのは、何が大事であるかを一人ひとりが汲み取り、他人の芸から盗み、みずから判断していくように促しているからなのだろう。型の継承を通してそこに流れる心を伝えるという伝承の在り方は、能に限らず日本の芸道全般に通じるようにも思う。
ところで、このような、ある意味「与えすぎない」教育は、あらゆる情報を提示する現在の教育とは反対の方向を向いているかもしれない。しかし、一見すると「親切」とは言えないその方法は、考える力を培い、自発的な創造力や発想力を高めることにもつながるだろう。応用力を兼ね備えた教育方法として、いま改めて注目してみたいとも思うのである。
注)文中の「師匠」とは、宝生流の故近藤乾之助師(1928-2015)である。