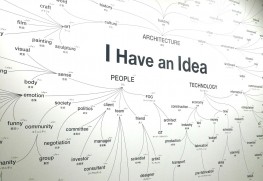(2017.04.09公開)
熊野詣にやってきた若くて美しい男僧に恋慕した女が、男僧を追い求めるあまりに、恋の炎を燃やす毒蛇と化してしまうという、恐ろしい物語をご存知だろうか。これは和歌山県にある道成寺を舞台に成立した「道成寺説話」である。毒蛇の女は、最終的に道成寺の鐘の中に逃げ隠れた男僧を炎で焼き殺してしまうのだが、その劇的な展開のせいか、道成寺説話は古くより親しまれ、語り継がれてきた。平安時代の『大日本国法華経験記』『今昔物語集』などの仏教説話集や、鎌倉時代の『元亨釈書』という仏教書に収められており、加えて、後日譚まである。後日譚では、焼かれた鐘を再興しようとするところに女の怨霊が現れ、鐘を引きずり下ろそうとする。
興味深いのは、道成寺説話は、説話という枠組みに収まらず、連続して新たな世界を切り開いていったということである。後世に、説話の世界は形を変え、芸能の世界に進出し、数々の作品を生み出していったのだ。例えば、中世には能「道成寺」が生まれ、近世には歌舞伎舞踊の「傾城道成寺(けいせいどうじょうじ)」や「京鹿子娘道成寺(きょうがのこむすめどうじょうじ)」、義太夫節「日高川入相花王(ひだかがわいりあいざくら)」、新内節「日高川」、長唄「紀州道成寺(きしゅうどうじょうじ)」などが成立した。そのほか、地歌・箏曲や、河東節、一中節にても作品化されたほか、現代でも数々の創作曲が生み出されており、これらの作品群は芸能のジャンルを越境して「道成寺物」と呼ばれている。説話の形成した世界が形を変えて異なるジャンルに摂取され、横断的に広がり、さらに新しい趣向が次々と付け加えられていく。その連続のなかで、おそらく観客は、おなじみの世界の思いがけない展開を喜んだのだろうし、周知の場面が作品を超えて受け継がれている様子を見ては、もとの世界と重ね合わせて楽しんだのだろう。このような、もとの世界を膨らませて新しいものに仕立てていく連続のあり方は、和歌の手法に例えるならば、「本歌取り」的な発想に基づいていると言えようか。そこでは、世界が重なって映し出されるのだ。
一方で、中世に爆発的に流行した連歌などは、「本歌取り」的な連続とは少し違ったあり方をしているように思われる。連歌は「三十一文字(みそひともじ)」の和歌を二分して、「五・七・五」の長句と「七・七」の短句を二人で別々に詠むものであるが、そこに主題はなく、長句が詠まれたのを受けて、その場で即興的に短句が作られる。また、何人もの人が寄り集まって、長句と短句を交互に詠むこと繰り返していく「長連歌」では、百句をつなげる「百韻」を基本とするが、百韻を十回重ねる「千句」や、百回重ねる「万句」のものもあった。前の人の詠んだ世界を踏まえつつも、また新たな世界を展開させ、それを鎖のように連続させていくから先が読めない。しかも、どのような歌を付けるのかを集団で考えて、いい歌を選んでいくので、自分では思ってもみなかった新しい世界が他人によって開かれる。ここにおいて、世界は一句ごとに変わっていくし、その瞬間的な変化を集団で追うことになるのである。
「本歌取り」的な発想と「連歌」的な発想とでは、その連続のあり方は異なっているが、世界を転換していくという点では一致している。そして、世界を転換するには、もとの世界に自分が入り込んでその主体となり、そこからまた新しい世界を築くための想像力が必要になってくる。当然、それを受ける側にもその世界を解釈するための想像力が必要である。このような、送り手と受け手の双方の想像力に基づく連続は、芸能や連歌に留まらず、私たちの文化全体を支えてきた重要な要素の一つのように思えるのだが、いかがだろうか。現代でも、身の周りの生活を見渡せば、そこかしこにその気配が感じられるだろうし、なおもそうした連続が文化を豊かに彩っていることに気づくに違いない。