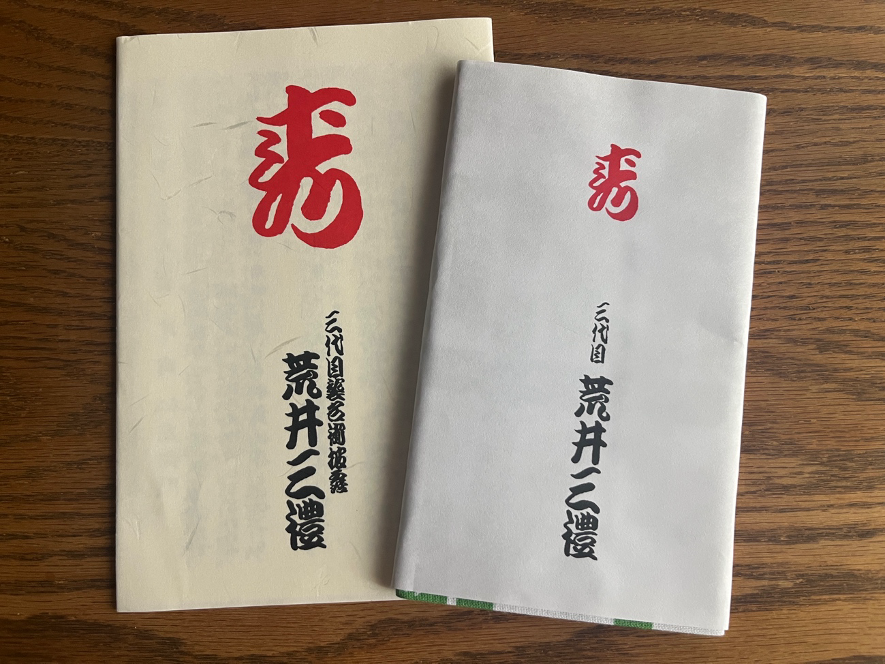
ひとりの人間が、いくつもの名前を持っているというのは、いったいどういう感じなのだろうか。
幼名から成人名、さらに当主名など、人生の節目において改名することが自然であった江戸時代には、身分や環境によって名前が変わっていくのは、至ってありふれた感覚であったのだろう。たとえば、「たらちね」という落語には、言葉の丁寧すぎる女性が名前を尋ねられ、その由来を長々と語るくだりがある。こんなふうに。
自らことの姓名は、父は元京の産にして、姓は安藤、名は慶三、字(あざな)を五光、母は千代女と申せしが、わが母三十三歳の折、ある夜丹頂を夢見てわらわを孕めるが故、たらちねの胎内を出でしときは鶴女(つるじょ)、鶴女と申せしが、それは幼名、成長の後これを改め、清女(きよじょ)と申し侍るなり。
じつはこの言い立て、上記のバージョンのほかに、三代目三遊亭金馬から桂南喬、さらに入船亭扇遊へと伝わった型もあるのだが、それはさておき、幼名の鶴女から成人名の清女への変化は、江戸時代の人々にとって、ごく普通の習慣であった。
だが、明治時代になると、国民国家の形成に向けて全国民を正確に把握するため、新政府は新たな戸籍の編纂を進めていくこととなる。明治4年(1871年)には、「戸籍法」が制定され、苗字の登録が推奨されるとともに、翌明治5年には、「複名禁止令」「改名禁止令」といった布告が相次いでだされた。個人を識別するために、複数の名前を持つこと、また名前を改めることが禁じられたのである。これ以降、いくつもの名前を使い分けることや、なにかの折に改名すること、つまり、どのような名前を名乗るかについての自由が大きく制限されていくこととなった。
おそらく、いま多くの人は自分の名前に対して「かけがえのないもの」と感じているのではないだろうか。だけど、その感覚は、それほど古くからあるものではない。それは近代になって芽生えたものといってもよいだろう。
こんなことをぼんやりと考えるともなしに考えていた。どうしてこういうことになったのだろうか。もちろん、暑さのせいもあるだろう。が、それだけではあるまい。ひょっとすると、このあいだ寄席文字の橘右橘(たちばなうきつ)師にお会いしたからではないだろうか。
寄席文字とは、寄席の看板や高座のめくりなど使われる独特の書体。筆太で字の右側が上がっているのが特徴。余白を空席に見立てて、それが少なくなるようにと太い字で、客の入りが伸びるようにと右肩上がりでしたためられる。古くからあったビラ字をもとに、右橘師の師匠である橘右近師によって編みだされたのが橘流寄席文字。芝居文字や相撲字、提灯文字などとともに江戸文字と呼ばれている。
この右橘師の本名は「中村泰士(なかむらやすひと)」という。寄席文字書家のかたわら、落語会の企画・公演、三遊亭小遊三や桂吉坊といった落語家のマネジメントを手がける、大有企画という芸能事務所を経営しているが、その際は本名を使っている。
また、演芸評論家やプロデューサーの仕事のときには「中村真規(なかむらまき)」。文化庁芸術祭の委員や芸術選奨の選考審査員、そうそう、本学園の日本文化藝術財団の専門委員もこの名前で務めている。
さらに、歌舞伎の興行で用いられる勘亭流の書家として「荒井三鯉(あらいさんり)」の名で長く活躍してきたが、2025年には、師名でもある三禮勘亭流の家元「荒井三禮(あらいさんれい)」の名前を三代目として襲名した。
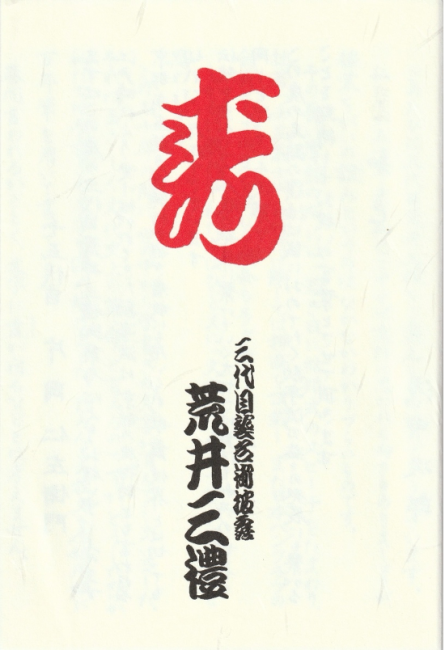
三代目荒井三禮襲名披露の口上書き。片岡仁左衛門、中村福助、浅田次郎が祝辞を寄せている。
いやはや、ちょっと混乱してきたので、ここで少し整理しておこう。
本名は「中村泰士」。会社経営者としても、この名前を使っている。
演芸評論家やプロデューサーとしては「中村真規」。
勘亭流書家としては「三代目荒井三禮」。
橘流寄席文字書家としては「橘右橘」。
いったいこの4つの名前をどのように使い分けているのだろうか。もしかして名前が変わると、人格も変化するのだろうか。「一身にして二生を経る」とは、福沢諭吉が『文明論之概略』(明治8年)の緒言で用いた言葉だが、まさか「一身にして四生を経る」ということになるのだろうか。なかなか想像が及ばない。それは、私には「宮信明」というたった1つの名前しかないからだろう。
だとすれば、私にも別称や二つ名があればよいのではないか。私的な日常生活では、もちろん本名の「宮信明」を。大学教員としては、例えば「宮仁左衛門(みやにざえもん)」(宮家の当主名)を。テレビやラジオに出演するときは、「西園寺律(さいおんじりつ)」(ChatGPTに聞いた知的でかっこいい名前)なんていかがだろうか。
もちろん、複数の名前を名乗ることの困難や重圧、葛藤もあるだろう。そんなことはつゆ知らず、のうのうといい気なもんだ、といわれれば、ぐうの音もでない。けれども、現実からの逃避、あるいは新たな人生への願望のあらわれなのか、異世界転生ものがブームとなるような昨今の社会情勢において、別のなにものかになりたいという感覚は、きわめて真っ当で、健全な欲求ではないだろうか。
私もいくつもの名前をうまく使い分けてみたい。それだけで、ちょっと自由になれるかも知れないのだから。






