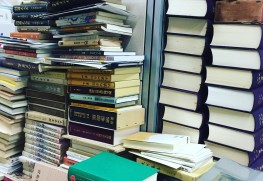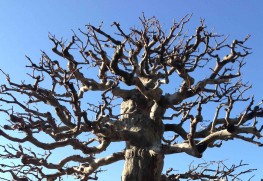SNSが人々の生活に入り込んでどのくらいになるだろう。
私自身は、東日本大震災の時点ではすでにTwitter(現X)に親しんでいた。学内誌の編集会議の後、職場近所の路上で大津波が迫っているという報せをTwitter上で見たのを覚えている。
それ以前のTwitterはほのぼのとしたもので、みんな一斉に夕空の写真を上げたりしていたのを覚えている。多くの友人ができて、一部の人は実際に親しくなったりもした。そうした人たちから、人権や尊厳といった考え方などを改めて学んだりした。その頃のTwitterには、いい思い出がたくさんある。もう15年くらいも前のことだ。
東日本大震災とその後の福島第一原子力発電所の事故では、SNS上でいろいろな情報が飛び交った。この頃から、ほのぼのとした友愛の感覚よりも、流言飛語のようなもの、攻撃的なものなどが増えてきたように思う。ネットの方がテレビより情報が早い、とかネットの方が真実だ、といったことが言われるようになってきたのもこの頃だ。このいやな感じは、今のSNSでは常に鳴っている基調音のようになってしまった。
震災、安保法制、コロナ禍といったことが起きるたびに、Twitterは怒りの声で満たされるようになっていった。私の知り合いたちもいろいろな形で怒りを吐くようになっていった。そして、私自身はそういう風景に辟易としてしまって、Twitterから降りたのだった。アカウントの消去は、さまざまなつながりの中から自分自身の存在が消えるような気がして、少し勇気の要ることではあった。他のSNSを覗くことはまだあるけれども。
SNSが怒りのメディアになり始めた頃、だいたい議論は「あっちとこっち」という感じであったように思う。わかりやすい敵が設定されていた感じである。コロナ禍や政変などを経るうちに、その感じは変わってきたように感じている。よく知った人が、ある問題では陰謀論者のように見えたりといったことも増えてきた。あんなに思慮深かった人がなぜこんな動画をシェアしてるのだろうといったこともあった。これまで見解を共有してきた「こっち」の仲間や友人の中にもさまざまな角度の亀裂が見られるようになってきた。それは「こっち」だけでなく「あっち」でもおそらくそうなのだろう。大きな対立軸はなんだかはっきりしなくなり、小さな対立軸がいくつも生まれているように見える。
ネット上の怒りを観察していると、どうやらその怒りのもととなっている倫理観や正義感はもはや問題ではないようだ。怒って見せている、その身振りやポーズが大事なのだ。あることについて私は目覚めている、真実の情報に近いところにいる、という優越感や、あることを批判してみせる論理や舌鋒の鋭さのアピールなどが、むしろ中心的な関心事のように思われる。そしてそれに共鳴してくれる人たちが、理解者なのだ。それがミクロな「こっち」を新たに作っていく。問題の是非ではなく、そうした怒りのポーズの示し方の選好性によって、人々が組織化されているように思う。
改めて投稿する自分自身を振り返ると、何についてどのように批判するかも大事だけれど、どのような立場からどのような切り口でどのように語ったら共感が得られるか、という配慮もしていることに気づく。いつのまにか、ややおおげさな身振りが、仲間のように思える人たちへの媚びのようになっていることもあるだろう。SNSはそういう身のこなしの、見せ合いの場というところがあるように思う。また、SNS上で異様な人と不快なやりとりが生じることがままあるが、こういう場合も、その人の発言にも相まって、その語りやそれが感じさせる佇まいに恐怖するのではないか。
ものごとを批判するには自分の頭で考えることが大事だと言われる。だが、自分の考えのどこまでが人の考えで、どこからが自分の考えなのか、きちんと峻別するのはそんなに簡単なことではないのかもしれない。それ以前に、SNSという場ではそうした自分自身の発言の根拠はあまり問われない。そうした内容に、怒り方、怒りの見せ方といったもののほうが、演劇的な効果をもって人を動かしていくのだろう。
今はこうした怒りや非難の身振りばかりが目立っているが、他の感情の他の身振りといったもの(映えの演出というのはその一つなのかもしれない)を見つけ出したり作り出していくことはできないだろうか。根拠を踏まえて何を問題化するかといったことよりも、そうした工夫のほうがネット世論を風通しのよいものに変えていくのではないかと思う。そんなデザインが求められているのではないか。