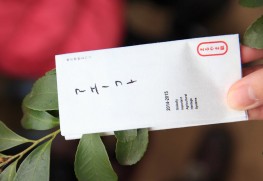2)問いと沈黙と過ごす
2018年春、東村山市にある小学校と行った連携授業がある。ハンセン病の方の療養所「国立療養所多磨全生園(以下、全生園)」への社会科見学を、感想文を書いて終わりにするのではなく、図工の授業として深める試みである。
6年生の2クラスで12チームつくり、そこに大人がひとりずつ入って授業を行う。その大人が「市民スタッフ」と呼ばれるひとたちである。どんなひとに声をかけたのかときくと、「同情することは悪いことではないけれど、“かわいそう”と言ってしまうことによって、自分が高みに立ってしまうことにセンシティブで、“待つこと”のできるひと」と事務局長の宮下美穂さんが答えてくれた。

宮下美穂さん
まずはじめに、参加する大人はハンセン病に関する本をみんなで読んで、歴史について学ぶ時間を持った。それを踏まえて、どのようにこのことに向き合ったらいいのか何度も話し合ったそうだ。
———在日2世の趙根在(チョウ・グンジェ)さんという方が、ハンセン病を撮り続けていて、その写真集をみんなでよく見ました。全生園は大きな差別を被った場所として考えられていますが、実は亡くなった方の遺体を運ぶ仕事などは、在日の方がやっていたという記述もありました。そうした二重、三重の差別構造のようなものがあった。それを単にかわいそうとか悪いとかではなく、子どもたちにどのように伝えるのか。そもそも自分たちがこのことを伝える責務を負うことができるのかと何度も自問しました。でもそれは教えられることじゃないので、子どもたちが自分でそこに気づくといいよねって。「教えない」「導かない」ということを大事に、みんなで七転八倒しながら挑みましたね。だって、急に偉そうなひとが来たら嫌じゃないですか(笑)。
最初の授業は、司書さんに全生園にまつわる本の読み聞かせをしてもらい、それから1日かけて全生園の見学へ。そのあとクラスごとに90分授業を3回行いました。子どもたちは図工だからつくりたくてうずうずしている。でも「今日はつくらないよ。全生園に行ってみてどうだった?」っていう問いかけをくり返したんです。話しやすくするために、全生園の敷地の300分の1の模型を大人がつくって、それを囲みながら。
おもしろかったのは、模型をつくっている最中に「もしかしたらここでの暮らしには、いまのわたしたちの暮らしより自治がある」って、大人がぽろっと言い出したんですよ。生きていかないといけないから、自分たちでルールを決めて、牛や豚を飼い、畑や森をつくった。その自治力は、わたしたちが近代化のなかで失ってしまったものかもしれないと。ほかにも「不幸っていうよりは、フェアじゃない」という声もありました。
1回の授業が終わる度に、大人たちは2時間ほどふりかえりを行って、その後も何度もメールでやりとりをした。写真集を眺め、模型をつくり、対話を重ねたからこそいろいろなことばが生まれた。大人と子ども、学びはどちらか片方にだけ起こるということはないのかもしれない。

提供:NPOアートフル・アクション
———わたしが関わったチームのひとつは、すごく元気がよかったんですよね。『てっちゃん ハンセン病に感謝した詩人』という本の帯に《らいになって良かった》って書かれていて「なんでよかったと思う?」と聞くと、「ハンセン病を伝える役割を担ったから」って言うわけ。それは“国語”的には正解かもしれません。でも「あなたならどう?」って聞くと、10秒ぐらい考えてから「俺、やだ」とやっとぼそっと本音を言う。沈黙との戦いでしたね。
このチームは、話し合いながら「良い/悪いじゃない」という結論に辿り着きました。「じゃあ、それを伝えるにはどうしたらいいと思う?」とまた問いかける。最終的に、ものごとの二面性を伝えるために椅子を背中合わせにして、大きくした趙さんの写真を眺める展示をつくりました。趙さんのことばを拾って天井からぶら下げて、見る位置によっていろんな見方が見えるように工夫したものでした。
自分、そして自分たちは何を感じたのか。それをどのように他者に伝わる「表現」にするのか。一筋縄ではいかないが、表現という段階を踏むことで、より感じたり、考えたことが深まっていく。沈黙と発話をくり返しながら、いつの間にか「かわいそう」ということばは減っていったという。

提供:NPOアートフル・アクション