現在、ファッションの世界では「持続可能性」という言葉をよく耳にする。21世紀初め、グローバルに大量生産・大量消費を展開するファストファッションが台頭、環境や社会へ悪影響が明らかになり、欧米で「サステナイブル・ファッション」が提唱された。それ以前からエコ、ロハス、サステナイブル・デザインなどの動きはあったが、業界が組織的な取り組みを始めたのはこの時期だろう。それが日本にも伝わってきた。さらに2015年に国連が「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals =SDGs)」を掲げてから、一般にも広く周知されるようになり、服飾界ではいまやバズワードとなっている。
私は大学で服飾を教えているが、2011年から授業でこのテーマを取りあげている。東日本大震災がきっかけであった。それ以来、自分なりに講義で話したり、ゼミで議論したり、学生たちによるワークショップ、イベントなどを見てきた。しかし、これまでの年月を振り返って、気候変動や環境問題に少しは改善の兆しがあるのか、またファッション業界や消費者の心理に根本的な変化が生じているのかというと、いささか心許ない。むしろ、最近は流行と現実とのギャップを感じる。この言葉もやはり一過性のものとして消費されてしまうのか、そんな疑問も頭をよぎるようになった。
サステイナブル・ファッションに何がおこっているのか、今後どうなるのか、自らの目で確かめたくなり、イギリスに調査に行くことにした。イギリスはサステイナブル・ファッションの最前線であり、研究書や一般向け書籍も出版され、ブランドも少なくない。もしかしたら、日本の状況を違った角度から考えることができるかもしれない。
とりわけ関心があったのは、ロンドン・ファッション大学(London College of Fashion、以下LCF)に設置されているサステイナブル・ファッション・センター(Centre for Sustainable Fashion)である。このセンターは2008年に設立されてから、さまざまなプロジェクト、イベント、教育、研究、出版を精力的に展開してきており、同国でのムーブメントの台風の目となっている。他の国にも似た施設はあるかもしれないが、その規模や成果の大きさでは、おそらく世界に例のない研究拠点だろう。このセンターの人たち、またイギリスを拠点とする研究者たちは課題とどう向き合っているのか。この記事では、彼らとの対話を通して、見えてきたこと、そして考えたことを述べてみたい。
センターに所属する3人の方にインタビューを申し込んだ。
一人目は若手研究者のフランチェスコ・マザレラさん。彼はセンターの社会変革デザイン分野主任研究員であり、「ファッション・アクティビスト」を名乗り、イギリスの難民の支援、東ロンドンの地域活性化に取り組んできた。彼の活動はファッションと関係ないようにも見えるが、実はイギリスならではのサステナビリティの価値観が込められている。
2番目はセンターの戦略責任者であるナオミ・ブイヤールさん。彼女はセンターの戦略立案の担当者だ。彼女の話から、センターがどのように社会を動かそうとしているのか、多様な活動実態が見えてきた。
そして最後に、サンディ・ブラックさん。ブラックさんはファッション・テキスタイルデザイン及び技術の教授。センター創生期からのメンバーであり、サステイナブル・ファッション研究の第一人者である。彼女にこの動きがどのように生まれてきたのか、経緯をふまえて振り返っていただいた。
これらの話に加えて、私がイギリス滞在中に取材した他の方々の話も踏まえて、イギリスの事例からサステイナブル・ファッションの現在を見てみたい。それは、日本でのこれからの展開を考える一助になるかもしれない。


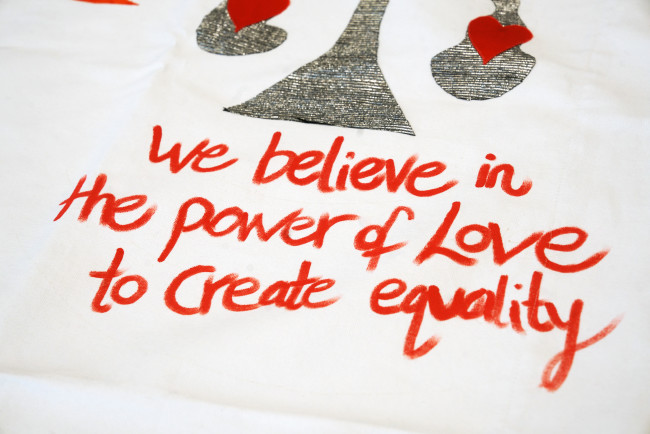
フランチェスコ・マザレラさんの難民支援プロジェクトの成果物より。難民たちとともに作品をつくる
- 1)ファッションの社会運動 フランチェスコ・マザレラさん1
- 2)ローカリズムとクラフトマンシップ フランチェスコ・マザレラさん2
- 3)布のアイデンティティ 難民プロジェクト フランチェスコ・マザレラさん3
- 4)文化から持続可能性をさぐる フランチェスコ・マザレラさん4






