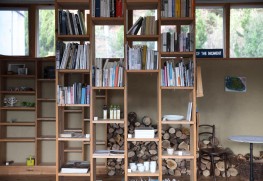2)伊東豊雄さんの「みんなの家」
多木さんは「控えめな創造力」をキーワードとするようになったきっかけは、イギリスの社会人類学者のティム・インゴルドの著書『メイキングー人類学・考古学・芸術・建築』にある。その中で、インゴルドはhumble(控えめな、謙虚な)を用いて「つくる」ことを記述していた。多木さんはそこに目を留めて、自身の思考を深め、育ててきた。
インゴルドがいうように、自分のイメージを一方的に押しつけるのではなく、素材や人、社会、環境などの声を聴き、ともに創造に向かうこと。さらに、それらと関係性を育みながら、ともに新たな価値を生み出していくことを多木さんは思考してきた。
そうするうちに、ハンブルを象徴するような建築物に出会う。東日本大震災の後、伊東豊雄さんたちが被災地に建てた「みんなの家」だ。たいへん著名な建築家でありながら、伊東さんは作家性とは別の次元で建物をつくっていた。
———僕にとって、衝撃的な出会いでした。建築の世界だとこういうことがあり得るんだ! と、初めて伊東さんに見せていただいた気がしています。
伊東さんは、被災地の人のために家をつくるとなったときに、自分の表現を控えたわけです。完成したのは一見ただの小屋じゃないですか。伊東さん的な建物ではないでしょう。被災地で建築家が何をするのか考えたときに、自分の表現を探求するなんてことは全くナンセンスだと悟って、そこにいる人たちが本当に必要としているものを聞き出してつくられた。それは伊東さんにとっても大きな挑戦というか実験だったわけですよね。周りから「これでいいんですか?」と言われても、「いいんだ」とはっきりおっしゃっていて。
それは「控えめな創造力」なんですよ。自己表現じゃなくて、人間が必要としているものをつくるというところからスタートする。そのときはまだ「ハンブル」という形容詞は使っていませんでしたが、その後、「控えめな」という言い方をすることで、自然に対して、あるいは人に対しての新しい建築のつくり方の基本がつくれるんじゃないかという気がしました。
「みんなの家」は、震災直後に伊東豊雄さんをはじめ、5人の建築家によるボランティア団体「帰心の会」によって提案されたプロジェクトだ。住む家を失い、避難所や仮設住宅に暮らす人々のあいだの、人間的なコミュニティの場に最低限のかたちをつくろうという試みである。伊東豊雄、妹島和世、山本理顕が中心となって若い世代の建築家たちに呼びかけ、被災各地にみんなの家が完成し、利用されてきている。


伊東豊雄さんの「みんなの家」。(上)竣工式の後は芋煮会を行った (下)お茶会のようす。みんなが集える場所があることがどれだけ大切か 写真提供:伊東豊雄建築設計事務所
———伊東さんがつくった1軒目に伺いました。彼の表現じゃないかもしれないけど、すごく素敵で使いやすい建物になっていました。作家性にこだわらないというのは、本当に控えめかどうかの境なんですけど、それまで自己主張してきた人の中には、それを手放すのが怖い人もいると思うんです。
でも、プロジェッティスタのことでいえば、カスティリオーニさんたちはずっと作家性を手放してやってきたわけです。それでも、「すごい作家だ」と思われていた。カヴァリアさんも自己主張ってことは全然意識しないとはっきり言うけれども、手を抜くのかっていったらそうじゃない。最終的な成果のために100%努力するけれど、自分の名前を持ち上げようなどという野心は全然ないんですよ。
コスパ、タイパという言葉が幅をきかせる現代、特にZ世代のような若い層においては、プロジェッティスタの方法論はおとぎ話のようであるかもしれない。控えめであることの境界線は具体的にどこにあり、そのふるまいはいったい何に根ざしているのだろう。