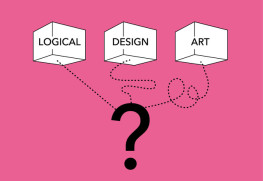ご承知のように新型コロナウィルス感染症による影響が世の中に大きく黒い影を落としている。このような厄災は、医療が発達し衛生環境も改善された現代社会に住うわれわれにとっては非常に稀なできごとといえるが、歴史的にみればこれまでに人類は幾度となくこうした経験を重ね、その都度乗り越えてきた。
たとえば14世紀の中頃からヨーロッパで断続的に発生・拡大したペスト(黒死病)では甚大な被害が出た。とくに1348年にイタリアで猛威をふるった流行においてはおびただしい数の人々が亡くなった。そうした悲惨な状況が、社会のあらゆる局面に大きな衝撃を与えたことはいうまでもない。それが中世的な価値観の瓦解を導く一つの要因となり、やがてルネサンスへと至る大変革が準備された。
件のペストによる被害は、われわれの想像を遥かに凌ぐ規模であった。たとえば、フィレンツェにおける1347年末の人口はおよそ9万人だったが、翌年に発生したこの疫病により、その約6割が死亡。短期間で4万人を割るまでに激減したといわれている。この恐るべき死亡率は特定の都市に限ったものではなく、おおむねイタリア全域が同じような状況にあったらしい。
これほどの大事件に遭遇すれば、その惨状についてつぶさに報告した芸術作品がいくらでも残されているように思えるが、実はそうではない。まったく不思議なことではあるが、14世紀中頃にイタリアを襲ったペストの様子を直接表現した当時の美術作品はあまり存在していないのだ。これは驚くべきことである。なぜなら、見たこと、聞いたこと、感じたこと、実体験はもちろん、想像したことまでも表現し、それらを他人と共有しようとするのが人という存在であるからだ。これは昨今のInstagramやfacebookあるいはYouTubeなどを見れば容易に理解することができるであろう。
しかし人口が激減するほどの大事件にもかかわらず、なぜそれを表した作品が少ないのか、その理由はまだ定かではないが、少なくとも以下のことは言えそうである。つまり表現することができないような、多くの人々に重大なトラウマを引き起こすような筆舌に尽くしがたい経験(疫病・災害・戦争など)というものがこの世には存在するという事実である。こうした事実を、人間と表現、人間と芸術との関係について考える際に忘れてはならないだろう。
はたしてCOVID-19が拡大する今、そして今後にどのような芸術作品が生み出されるのだろうか?などと考えているうちに匿名で活動するストリートアーティストのバンクシーが、この感染症の治療にあたっている医療従事者たちを称える作品《Game Changer》や、今回のコロナ禍と底層で呼応していると思われるミネソタ州で発生した白人警官による黒人男性殺害事件とそれを契機に広まったブラック・ライヴズ・マターを題材にした作品《This is a white problem》を発表した。ブラック・ライヴズ・マターについては著名な現代芸術家の村上隆氏もこの運動を支援するための作品を制作している。
とかく非常事態下において芸術といったものは不要不急とみなされがちであるが、こうした例をみてくると張りつめた雰囲気の社会においても芸術は求められていることに気づく。今春から京都芸術大学人間館入口前のピロティにヤノベケンジ氏が制作した勇壮で屈強な2頭の狛犬(図1)が置かれている。狛犬とは悪しきものから神や聖域を守る存在である。これら一対の神獣は昨年の秋に比叡山延暦寺でおこなわれたカルチャーイベント「照隅祭」で奉納展示された後に、新型コロナウィルスによる禍からわれわれを守るために現在の場所へとやってきた。もちろん芸術によって有害なウィルスが駆逐されることなどないのだが、これらの聖なる獣の勇姿を見ていると不思議と勇気づけられる。美術館の閉鎖に始まり、コンサートや演劇の中止、新作映画の公開延期など未だに厳しい状況にあるが、芸術のもつ力と存在意義を見失うことのないようにしたい。
COVID-19に苦しまれているすべての方にお見舞いを申し上げると共に、人類に平穏な生活が1日でも早く戻ることを切に願う。
図:ヤノベケンジ《KOMAINU―Guardian Beasts-》(2019)(撮影者 加藤志織 2020/4/6)