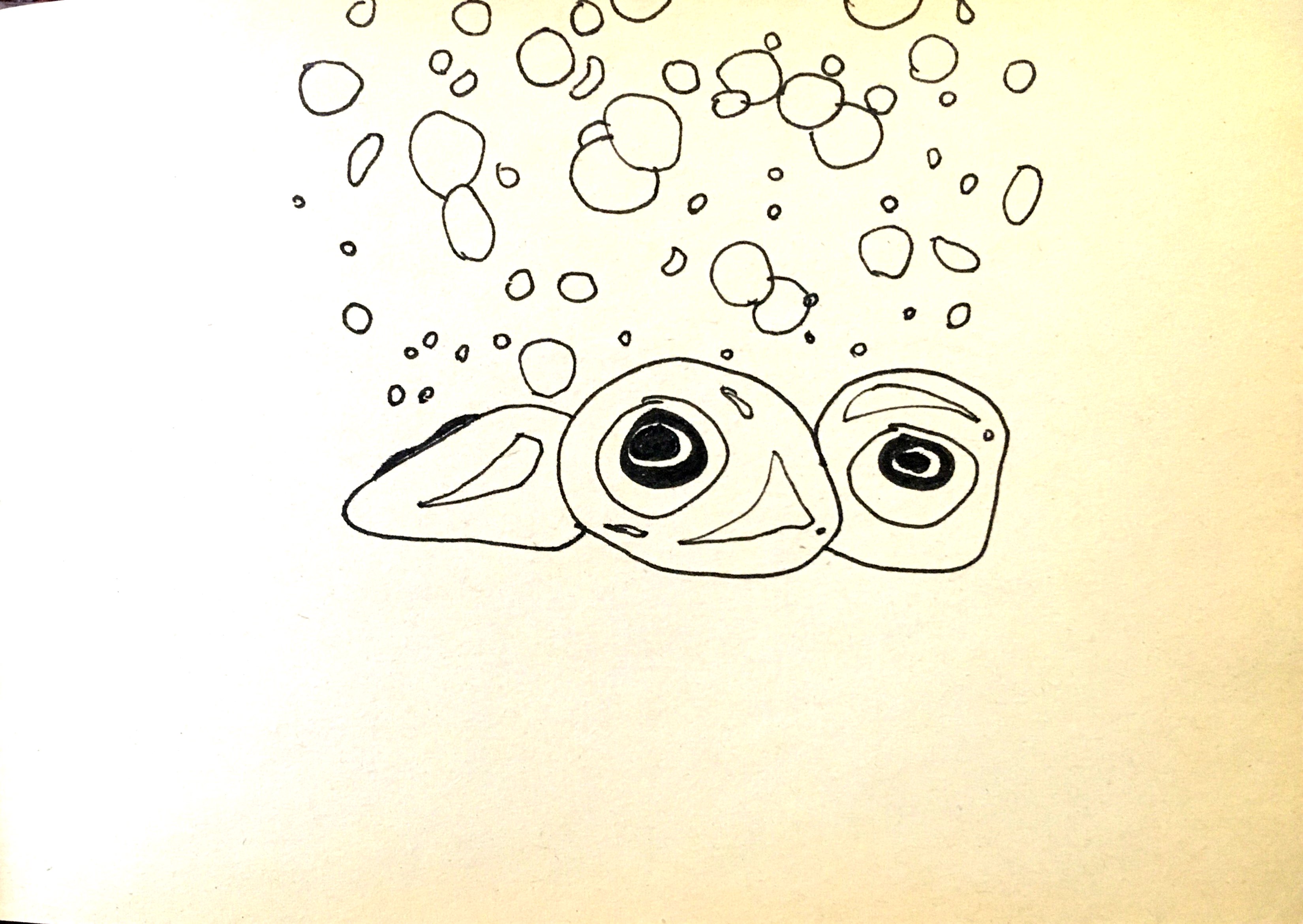
(2018.09.09公開)
いささか旧聞に属するが、2016年OECD理事会での安倍首相の発言が話題になったことがある。それは
「〜私は、教育改革を進めています。学術研究を深めるのではなく、もっと社会のニーズを見据えた、もっと実践的な、職業教育を行う。そうした新たな枠組みを、高等教育に取り込みたいと考えています」
というものであった。これについては、学術研究に取り組んでいる大学人の間で多くの異議の声が上がっていたのを覚えている。
さらにこれに先んじて2014年には、冨山和彦という人が教育改革に際して大学を「G型大学」と「L型大学」へ二局化させていくべきとの提言をして、注目された。「G型大学」は、学術研究において国際的な競争力を発揮する大学、「L型大学」はローカル経済圏に実践力のある人材を輩出する大学、というものだったように思う。これについてもいろいろな批判があったと思う。こういった一連の議論の中で、地方国立大学の教育学部や人文系学科が整理されていった。人文系が苦境に立たされる中で、デザイン思考系の学科がさまざまな大学で台頭してきたのも、こうした実践性重視の傾向と関係があるのだろう。
ところがこの、学術研究より大事とされる「実践性」というのがよくわからない。何か「役に立つ」知識を得て「役に立つ」「使いやすい」人間になることなのか。首相の言う「職業人」に限定すればそういうことになるのだろう。冨山氏的には、ローカル経済圏で技能を活かして食い扶持を得る人、というということになるのだろう。いずれにせよ「稼ぎ」ベースの視点に限定されているように思う。だが人間は別に「稼ぎ」だけに生きているわけではない。
人は自分の人生をより意味深くよいものにしていきたいと願う。そして生きることは選択の連続である、その判断をどう行うのかというのは極めて実践的な課題である。しばしばそれは、金だけでは答えが出ないものである。生きていく中で、どのような芸術に触れていくのかもそうだし、どのような政治的な選択をしていくのかもまた、同様に実践的な課題であると思う。このどちらにおいても、単に自分が気分良くなれればいい、というのもいいのだけれど、それを巡って他者と意見を交換できる、理解を作り出すことができるというのも大切なことだ。そしてこれは生きる上で不可欠な、「実践的」な課題である。そうした理解の欠如が、見知らぬ他者の命を奪うこともあるからだ。例えば排除や差別について、戦争やテロリズムについて、どのように考え、どのように行動するのか(例えば投票行動もその一つ)は、生存に関わる現実的な問題なのである。
安倍首相や冨山氏の発言に異議を唱えた人の多くは、高度な基礎科学や人文学の学術研究に深く取り組んでいる方々だったように思う。ただ、大学が「学術研究を深める」だけの場でないことは、首相に言われるまでもないことである。
たとえば、私が勤務している京都造形芸術大学の芸術教養学科は、もちろん伝統文化とデザイン思考についての一定の専門性はあるけれども、高度に専門的な学術研究方法論の伝授ということは、必ずしもやっていない。そういうことが目標の学科ではないのである。むしろ、先に挙げたような、生きるための「実践的」教養を身につけるところなのだと思っている。
芸術教養学科のどこが大学なのか。もしかしたら私たちがやっていることは、学術研究を深めている普通の大学の先生方からは、そうは見えないかもしれない。しかし私はここに大学の一つのフロンティアがあるように感じている。
芸術教養学科が取り扱っているような、ワークショップの技法やデザイン思考、ソーシャルなプログラムの企画といったことについて教えてくれるところは多い。「○○大学」と銘打たれた、NPO等によって運営されている面白く洒落た学びの場でも、そういったことを取り上げているのをよく見る。そういったところと一番違うのは何か。それは学的コミュニケーションを大事にしているところだと思う。レポートや論文執筆のルールやマナーについては、かなりきちんと教えようとしている。
芸術について少し物知りになりたいだけなら、別にレポートの構成などは学ばなくてもよいのかもしれないし、面白いイベントを企画したいだけなら、引用のルールなど知らなくてもいいのかしれない。しかし、私たちはこれは大切なことだと思っている。きちんと根拠を示し考えを提示すること、そしてそれに一定の批判(吟味)を与えること、そうした構えを作ることが、市民として本質的に重要だと思うからであるし、それを伝授することが大学の使命だと思うからである。そして、これは市民として生きる上での「実践的」な技にしてなくてはならないと思うからである。
ここからは私事になるのだが、私自身は実務家教員として大学に来たので、その時点では学位を有していなかった。ある意味研究者としては白紙の状態からのスタートだったのである。博士の学位を申請するためには、博士論文だけでなく、その基礎となる査読付き学術雑誌への投稿実績が必要になる。この論文の査読におけるやりとりというのが、私の場合には大変勉強になった。
学会誌に論文を提出すると、未知の査読者からの批判が寄せられる(査読者にもこちらの所属や氏名は伏せられている)。これはかなり厳しいことが書かれていることが多く、結構受け取ったときには凹むのだが、その批判を杖として論文を磨き上げて返すのである。それでパスすることもあれば、さらに疑義を提示される再査読、さらには却下、ということになることもある。真剣勝負であり、なかなか厳しいやりとりなのだが、これは大変勉強になった。未知の他者の正当な理解を得るために、どのようなことをすればよいのか、学ぶよい機会になった。これも学的なコミュニケーションに他ならない。そして気づいた方もいると思うが、このやりとりは通信教育にとても良く似ているのである。通信教育におけるディスカッションには、対面の講義とはまた別の可能性があると思う。
学的なコミュニケーションというと難しいが、要はスジの通った議論ができるということである。今までこうしたフェアな議論の方法が、「学術研究を深く極める人たち」に独占されてきたところがあると思う。しかし、こうした議論は、世の中の方向を見出していく公論形成に不可欠なものでもある。これは、「よく生きる」ために一般市民にこそ共有されるべき技能なのだ。アカデミズムから切り離される「実践的」大学が、これからは増えてくると思うが、それらが大学としての意味を持ちうるかどうかは、そこでの教育がこの学的コミュニケーションを真面目に扱うか、それとも便利でおもしろいノウハウの伝授に終わるかにかかっているように思う。
教育改革における「実践的」人材像には、「めんどくさいことをいわない」「むずかしいことをかんがえない」人材がどこか含意されているように思われるが、むしろ大学における「実践的」人材とは、専門性を超えたところでもフェアな議論ができる大人なのだと思う。
虚偽と恫喝が堂々とまかり通る日本の言論状況・言語状況はかなり切羽詰まった状況である。そこでは「批判するなら代案を出せ」といった論法も多く見受けられるが、これもワークショップ的なルールの劣化版というべきものだ。嘘でも論点のすりかえでもない、正当な見解の表明と批判が、納得できる形で行われなくてはならない。これはきわめて高い「実践的」意味のあることである。
そして大学は、大学である限りそうしたコミュニケーションの可能性を、その学びのプロセスの中で常に提示しつづけるべきであると思うし、大学を志す人は、そのことを胸においておいてほしいと思う。






