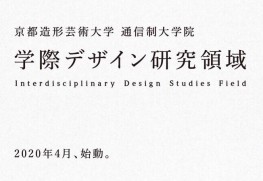(2015.02.08公開)
本誌『アネモメトリ』の8号、9号の特集は、「京都 西陣の町家とものづくり」として織物の町・西陣に残っていた空き町家について取り上げている。
さまざまなものづくりをしているアーティストの集まった西陣。織物だけではない、常に変化する街としての側面を示している。さて、今回はそんな西陣の基の姿である織物、ひいては養蚕について取り上げてみたい。
空き町屋が活用されている西陣だが、本来はいうまでもなく、織の街である。分業専業で技術は高度に進化し、高級絹織物を産する街として今日でも、そのイメージは定着しているだろう。正保二年(1645)に著わされた俳諧論書の『毛吹草』を紐解くと、諸国の名産品を取り上げており、洛中の「西陣」の項で「撰糸、厚板物(綾、練嶋紋嶋等)、金襴、唐織、紋紗、戻、絹縮(後略)」とある。西陣織は中世後期にはブランド化されていくが、最も栄えたのは元禄から享保年間、富裕層の町人たちによって支えられてきた。かくして高級ブランドとしての西陣織は確立され、今日へと至っている。
こうした西陣織をはじめとする絹織物は、しなやかで美しく強さも持ち合わせている繊維として、日本の伝統的な服飾に多く用いられてきた。この絹織物の原材料は、蠶(蚕)が作り出す繭である。4~5世紀には、帰化人である秦氏が蠶養と絹織の技術を日本に伝えたと考えられている。秦氏の拠点の一つである京都市西部の太秦には、養蚕神社があるのも頷ける。
平安時代中期に編纂された法律書である『延喜式』をみると、産糸国は48ヶ国あり、日本全国で養蚕が行なわれており、養蚕は時の政府からたびたび奨励されていた。
主要な産地としては、丹波・丹後(現在の京都府西部)がまずあげられる。今日でも遺されている地名の北桑田郡・南桑田郡は、蚕の食餌である桑が植林されていたことを示している。
時代は下り、江戸時代の文化十年(1813)に成田重兵衛が著わした『養蚕師篩』でも「蠶業を営む国々は、東山道八ヶ国、并武蔵、甲斐、加賀、越前、若狭、三丹州、およそ十六ヶ国なり」とある。「三丹州」とは丹波・丹後・但馬国を指し、絹糸を産していた。
こうして全国で産した繭・絹糸だが、江戸時代の17世紀末になるまでは、質が高いものではなく、西陣織などの高級品にはもっぱら中国から輸入された白糸が用いられたという。それが白糸輸入制限や諸藩財政に資するための奨励策が相まって品種や技術の改良が行なわれ、生糸(絹糸)の品質向上が行なわれるようになった。
そのため、近代日本では輸出品の大半を生糸(絹糸)が占めた。国策として生糸の品質向上と増産に力が注がれ、群馬県の富岡製糸場が設立される。生糸は日本の代表的な産業の一つとなったのである。
しかし、第二次世界大戦で輸出市場を失い、更には人絹(レーヨン)などの化学繊維の発展と、着物を着ない生活様式への変化によって、生糸需要は激減している。
つまり今日の呉服屋で見かける反物は国産と記してあるものの、織る前の生糸は輸入品に頼らざるを得ないのが現状なのだ。
一例をあげると、先にあげた丹波・丹後などの京都府西部の養蚕業は、最盛期3万軒を数えたそうだが、現在では4軒しかないという。こうした中、国産の生糸の復興を目指す織元の塩野屋さんと知り合う機会を得て、先月京都府亀岡市に見学へ行ってきた。織元である塩野屋さん自らが繭・生糸を生産するため、桑の木を植える活動を行っている。
桑の木を見学し、日本の伝統文化である着物文化の維持・発展への熱意を聞くと、伝統文化を守ることとは、まさに時間と想いを費やすことで維持されるものなのだと、改めて思う。
こうした伝統文化を支える活動が広がっていくことを願ってやまない。