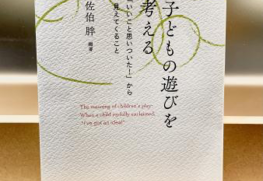(2016.06.26公開)
私たちの大学には、「京都学」なる科目がある。オムニバス形式の講義で、その回の担当者が自分自身の専門分野に絡めながら京都を語るという趣旨だ。そのお鉢がついに回ってきてしまった。
私の研究テーマといえば、フランス語圏のカリブ海文学である。日本からは一万キロ以上離れた熱帯。コロンブスによって「発見」され、近代にはヨーロッパに植民地化された島々。私にとっては重要なテーマだが、一般に日本人がイメージできるのは、海賊と客船クルーズぐらいだろうか。カリブ海と京都。これほどイメージのかけ離れた場所同士をどう結びつけることができるのか?
無茶なオファーにしばらく頭を抱えたが、そのうちに、ふと取り上げてみようかと思いついたのは「食」のテーマだった。
カリブ海の島々には、干した鱈(たら)を使った料理がたくさんある。かつてヨーロッパの各国は、植民地とした島にプランテーションを作り、砂糖やカカオを栽培するため、アフリカから奴隷を連れてきた。その奴隷たちがたんぱく源としてあたえられていた安価な食糧が、今も人々の日常食となっているのである。なかでも、潰した山芋と干鱈を丸めて揚げたアクラはビールによく合い、どこの店でも必ず用意されている人気のメニューだ。
さて京都にも、干鱈を使った「芋棒」(いもぼう)と呼ばれる名物料理がある。頭を切り落とさない丸のまま干した鱈を、その形状から棒鱈と呼ぶ。硬く乾燥した棒鱈を水で戻し、海老芋と炊き合わせた一品だ。
名前だけで一度も味わったことがなかったが、昨年、同僚の先生がこの料理を出す老舗の有名店に同行してくださった。店を訪ねてわかったのは、円山公園の敷地に同じ店名の店が二軒あるのだが、それぞれが江戸中期から「本家」「本店」を名乗る別々の店だということだ。それなのにウェブサイトは互いを模しているとしか思えない、茶色を基調としたそっくりの作り。料理の内容も値段もほぼ一緒なだけでなく、川端康成が愛したのも、松本清張が小説に登場させたのもそれぞれが「うちの店」と書いているのはどういうことか。そのうえ、うっかり予約したのとは別の店を訪ねても、正しいほうの店へと誘導してくれるのだから、本当にライバルなのかと疑ってしまう。
疑問はさておき、私は「本家」のほうを(初めは唯一の「本家」と信じて)訪ねた。件の芋棒は干鱈と芋が甘辛く炊かれたもので、鱈は身がほろほろと柔らかく、ねっとりした芋との組み合わせもよく、「名物に旨いものなし」とは言うけれど、予想していたより美味しかった。じっさい、芋の灰汁が鱈を柔らかくするのに対し、鱈の膠成分が芋を包んで煮崩れを防ぐとのことで、互いを補う相性のよい食材同士だといえる。
店の入り口のガラスケースのなかに、戻す前の棒鱈が積まれていた。大ぶりだが、鱈としてはこれでも小さい方だろう。同じように数尾が束になり積まれたものを錦市場でも見たことがある。もちろん内陸の京都の町でもとから手に入る食材ではない。日本海沖や北海道で水揚げされ、素干しにされた鱈は、かつては北前船などで京都まで運ばれており、茶会の懐石料理にも使われていたそうだ。
赤羽正春の『鱈』(法政大学出版局、2015年)によると、京都に(若狭あたりから)干鱈が持ち込まれ、食され始めたのは、応仁の乱の頃だという。当初は武士たちがこれを保存食とし、腰に下げて戦ったそうだ。飢饉や天災も多かった時代、足りない米を補う食品としての役目もあった。その後干鱈を食す習慣は、1600年頃から武士から庶民へ、また京都から他の地域へ広まっていったとの記述がある。
あらためて言うが、鱈は地球上どこであれ、北の深海に生息する魚である。カリブ海の島にとっても、本来身近な食材ではない。それがなぜ熱帯で働く奴隷の日常食になるのか? この背景には、近代における鱈の供給過剰とその保存技術の発達がある。
17世紀、現在のカナダ東部にあたるニューファンドランドはテール・ヌーヴ(新しい土地)と呼ばれ、フランスの植民地にして最良の漁場だった。ここで大量に水揚げ・加工される鱈は安価なうえ、塩干しにすれば高温のもとでも数年間は腐らない。当時のフランス経済を支えていた熱帯の植民地で、奴隷の栄養源とするには最適だ。
戦乱と飢饉の時代、日本海産の干鱈が京都の武士から広まったのとまさに時を一にして、カリブ海のフランス植民地では、現在の食文化の起点といえる干鱈を北の海から迎えることとなったのである。(つづく)