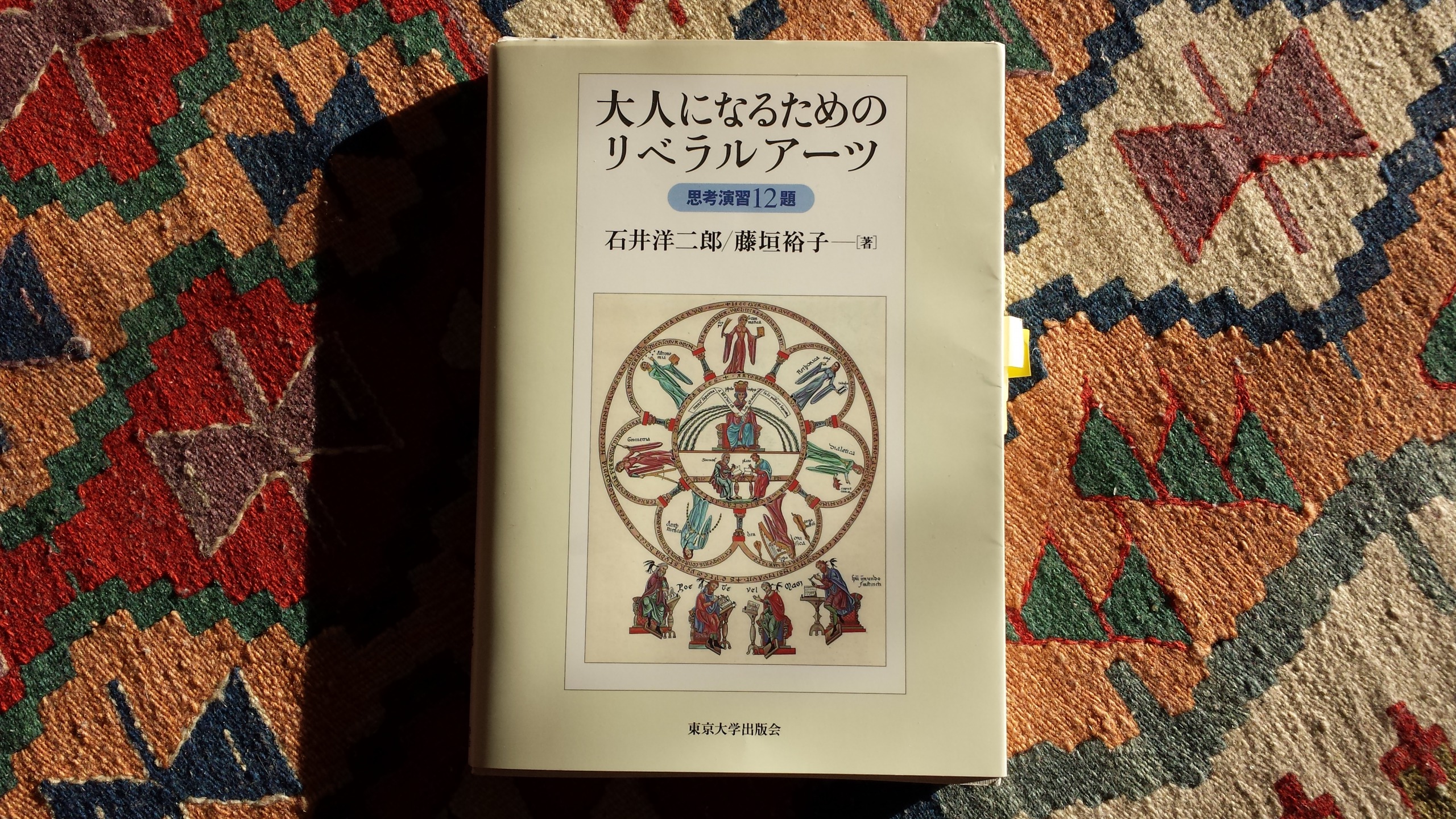
(2016.04.17公開)
あなたは自分を理系、それとも文系と思っている?
私自身は数学への苦手意識と文学への愛のコントラストが鮮明すぎて、十代の頃、進路に迷う余地はなかった。人によっては、それほどはっきり自分を定義できないこともあるだろうし、若いうちから芸術の道を志すなら問われることもないだろう。そもそも「文系」「理系」などという区別は、大学の受験科目に即したクラス分けのための便宜的なものでしかないかもしれない。
しかし、この便宜的かつ制度的な文系・理系の二分法は、意外に人の意識の奥深くまで影響しているようだ。とりわけ日本では、自分の専門領域を重視するあまり、それ以外の事象や考え方に関心をもたない「専門バカ」となる傾向は強い気がする。ひとつのテーマを巡っても、お互い自分の分野の論理だけで対処しようとするから話が噛み合わない。相手のことを「わかっていない」と切り捨てて終わることも多いのではないか。
さて、大学には教養課程というものがある。大学という教育機関は、専攻する領域の学問を高度なレヴェルまで学べるところだが、準備段階として、いわゆる文系・理系を問わず、広くさまざまな分野の授業を取り揃えたこの過程がかならず用意されている。私たちの大学を例にいえば、美術、デザイン、建築といった分野は各種学校でも学べるけれど、同時にそれ以外の学問、たとえば外国語や民俗学や生物学を学べるのは大学であればこそだ。いい換えれば、教養課程を備えているのが大学の大学たる所以ということになる。
でも「教養」ってなんだろう。たんに幅広い「知識」ということだろうか。一般にいう教養課程の担当教員でありながら、「専門バカ」代表、いや好奇心だけは広くあるから、かろうじてその名は免れたいと願っている者として、教養の意味をどう伝えるか考えを巡らせていた矢先、かつての恩師から一冊の本を贈られ、目をひらかれる思いがした。『大人になるためのリベラルアーツ』(石井洋二郎/藤垣裕子著)というのがそのタイトルである。
この本の魅力をひとことでいえば、単一の主張の記述でなく、多声的かつ生成的であること。というのも、これが東京大学でおこなわれたアクティヴ・ラーニング実践の生きた記録だからだ。
まず教員がひとりでなく、フランス文学と科学技術社会論――いわゆる文系と理系――を専門とする2名いる。参加する学生と院生(TA)も、法学、工学、文学など互いに異なる分野を学んでいる。このメンバーが12回にわたり、提起されたテーマを巡って討論を重ねる。問題提起は2名のうち一方の教員がおこなうが、最後に議論を振り返り、引きとるのはもう一方の教員という役割分担がなされている。つまりここでの議論は、支配的な立場や思考方法に回収されてしまうことがない。
テーマは「芸術作品に客観的価値はあるか」「学問は社会にたいして責任を負わねばならないか」「差異を乗り越えることは可能か」など、かんたんにイエス、ノーで答えられない問題ばかりだ。さらに具体的な論点として、「『学問が役に立つ』とはどのようなことと考えられますか。みずからの専門に即して具体的に考えてみてください」「自分の分野の『真理』が、他の分野の真理と対立するケースを想像し、それを他者にもわかる形で言語化してください」といった、各人の専門をメタレヴェルで意識させるような問いがなされ、それを全員で討議する。
最初は誰もが普段の思考の仕方によって考えたことを言語化し、それを皆の前で発言する。だが、自分とは異なるバックグラウンドを持った学生たちの思いもかけない発言と出会うことで、それぞれの思考が別方向に発展してゆく……まさにアクティヴ・ラーニングというべき実践である。
問いを分析したり、論を組み立てるといったことは論じるさいに多くが意識しているだろうが、それだけでなく、前提を疑ったり、立場を入れ替えてみることで、自分の硬直化した思考から抜け出すことが可能になるのだ。
今一度、「教養(リベラルアーツ)」という言葉に立ち戻ってみよう。もともと「リベラル」liberalという形容詞には、解放され自由になることが含意されている。古代ローマでは、文法、修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽の自由七科のことを指し、これらを学ぶことで自由な人格を得られると考えられた。
専門分野をきわめることは、個人にとって社会的にも精神的にも重要な基盤となる。だが一方で、文系か理系か、あるいは〇〇学、〇〇業界といった外的な区分が内面化されてしまっては思考も感性も活性化しない。そんなとき、一面的なものの見方を相対化できる視野を授け、学問のタコツボ化から解放する手立てとなるのが教養なのではないか。
「専門分野に進む前に幅広い教養を」といういい方はあまり否定はされないだろうが、どこかぼやけていて耳を素通りしてしまう。しかし、「閉じた専門分野から思考の自由を取り戻すのがリベラルアーツの本義である」という提言なら私は強く頷けるのだが、いかがだろうか。






