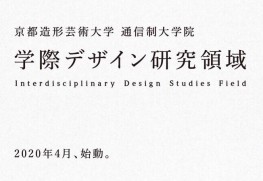昨年に新型コロナウイルス感染症が突如出現していらい生活がおおきく変化した。手洗いの回数がおおはばに増えたとか、手指消毒を頻繁にするようになったとか、外出する際にはマスクを必ず付けるようになったとかだけではなく、外出しなくなった(正確には「できなくなった」)。そのため美術館に行っていない。その感染症が注目されはじめた去年の2月以降、訪れた企画展はたったの3つである。
しかも、すべて仕事関係だったため、プライベートはゼロという状況であった。緊急事態宣言は全国を対象に常時発出されているわけではないので、その気になれば美術館へ赴き企画展や常設展を鑑賞することは可能な状況ではあったが、仕事のことやみずからの健康あるいは周囲の人のことを思うと足は動かない。こんな理由で注目すべき展覧会をいくつも見逃してしまった。
今、鑑賞したいのがパナソニック汐留美術館で開催されている「クールベと海展―フランス近代 自然へのまなざし」である。ギュスターヴ・クールベ(1819~1877)は言わずと知れたフランス近代絵画の巨匠で、リアリスム表現を確立した画家である。この男の故郷でとりおこなわれた一市民(被葬者については諸説ある)の葬儀の場面を描いた《オルナンの埋葬》(1849~50年、オルセー美術館)は、名もない庶民の日常を美化することなくありのままに描写した点でレアリスム(写実主義)絵画の金字塔とみなされている。
ちなみにレアリスムを、対象の形態を写真のように克明に表現することであると考える人がいるが、描写の細かさや忠実さ以上に重要なのは、画家が見出した「現実」を美術アカデミーの先例や決まりごとにとらわれることなく、「見たまま」あるいは「あるがまま」に描くという点である。それ以前にアカデミーの約束に従えば、無名の庶民の埋葬を画題に取り上げることなどありえないことであった。
このようにレアリスムの画家として知られるクールベではあるが、その画業の後半になると当時のフランス社会の状況、その暗部も含めた現実を描くというよりも、風景画、寓意画、狩猟画、あるいは肖像画などに制作の重点を移して取り組むことになる。件の「クールベと海展」が扱うのがまさに風景画、とくに海辺の景色、「波」の連作である。この画家は、1860年代にノルマンディ地方のル・アーヴルを訪れて、ウジェーヌ・ドラクロワ(1798~1863)やウジェーヌ=ルイ・ブーダン(1824~1898)がそうしたように海景と向き合ったが、他の画家たちと異なっていたのは、風光明媚な海辺の様子や観光地として賑わう様子ではなく、暗く深い緑色をした荒々しくうねる波を頻繁にモティーフに選んでいることだ。本展は入館に制限が設けられてはいるが、幸いにも6月1日から公開を再開している。会期は6月13日(日)まで。
じつはクールベの画業で忘れてはいけないものが、フランス社会を描いたレアリスム絵画、波を描写した風景画の他にもある。それは女性の裸体画だ。レズビアン的な関係性を想起させる2人の全裸女性が抱き合いながら寝そべる《眠り》(1866年、プティ・パレ美術館)や開脚した女性の局部を中心に胸から太ももまでを描いた《世界の起源》(1866年、オルセー美術館)などがよく知られている。ちなみにこれらの2作品はパリに住んでいたトルコの外交官カリル(ハリル)・ベイの注文とされる。後者については、「世界の起源」というもっともらしい名称で呼ばれてはいるが、顔が描かれず露わになった性器を中心に描かれていることから、男性の性的な欲望を満たす目的で制作されたことは間違いない。20世紀のフランス人精神分析学者のジャック・ラカンが生前にこの絵を所有していたことでも有名である。また、本作品の前で、局部を見せるパフォーマンスが女性美術家によって実行されたりもしている。このスキャンダラスな絵画のモデルはながらく不明であったが、依頼者であるカリル・ベイの愛人であった元バレリーナのコンスタンス・クニョーであることが判明している。
画像
クールベ作《眠り》1866年、プティ・パレ美術館