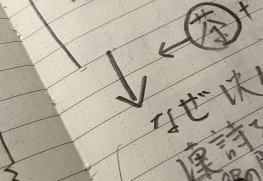(2014.03.05公開)
「角がツンと立つくらいの硬さがちょうどいい」
これは、樹脂の混ぜ具合いを教えてもらった時のフレーズ。造作の要領は時々お料理に近い。ボウルに入れて泡立てたり、混ぜる様子。粉から溶く石膏も、見た目はもったりとしたクリームだ。もちろん、現場には樹脂や塗料などの匂いがあるので、その妄想はすぐにかき消されるけれど、分量を計り混ぜ下ごしらえしていく過程は、リアルおままごとのよう。
私は、ナフタリン素材の彫刻を、シリコン製の型を使って制作している。シリコンは最初、とろんとした液体だが、硬化剤を入れると化学反応が起こり、数時間かけて柔軟性のあるゴム素材に変化する。それは原型の痕跡を無理なくそっと残し、ナフタリン彫刻の雌型となる。
何年も愛用しているのは、ゴムになってからも伸びの良い、柔らかく、真っ白なシリコンだ。液体のものを、缶から必要な分だけ容器に移し替え使うのだが、素材自体の重みで滑らかに容器になじんでゆく工程は、ただ移し替えるだけなのに、優雅で美しくすらある。良質な型どりには、このとろーっとした重みが重要で、シリコンが原型の隅々に届くことで、そのものの呼吸をしっかりトレースすることができるのだ。例えば革表紙の本の模様や、使い古した靴の癖の皺など、小さな傷まで、さまざまな時間の痕跡をシリコンはうつしてくれる。
ナフタリン彫刻を象るうえで大切にしていることは、そのものが経過してきた時間をとどめるということ。実際の世界では、時間はとどまることはないから、ナフタリンの彫刻は型から取りだされた瞬間から、日常の空気に触れ変化をはじめる。ケースの中で彫刻がフォルムを失い、少しずつ結晶が育つ様子は、形が消滅するということだけではない。そのためシリコンには、しっかりと日用品の持つ時間の痕跡を内包してもらわねばならない。
シリコンの真っ白な膜に包まれた日用品たちは、さっきまで触れあっていた空気から遮断され、繭のように時間を内包し発酵しながら、「進む時間」から切り離され、その役割や過去の所在からも解き放たれる。
型どりまでの作業工程の中で、日用品が白いシリコンの蛹になっている姿を眺めているのが好きだ。シリコンが硬化すると、ふちのきっかけ部分を起点に、ゴム部分をぐいーっと引っ張って、中の原型を取り出す。すると、一気に原型の表面と現実の世界が出会い、また新しい時間がはじまる。ものに溜まっている歴史の時間が、しっかり白いシリコン型にとどまっているのを確認し、ようやくナフタリンを流し込むという次の段階に入る。
「角がツンと立つくらいの硬さがちょうどいい」
そうだ、このフレーズはスポンジケーキの卵白の泡立ての表現と同じだ。
小学校の卒業文集の「将来の夢」に、こう書いた。「つくることを続けたい」
今も昔も凝り性な私は、当時、スポンジケーキ作りに熱を上げていた。おかげで今では、レシピがなくてもスポンジはすぐ焼くことができる。あの時まわりのみんなは、花屋だとか先生とかアイドルになりたいだとか書いていたけれど、ませた私は、ケーキ屋さんとも作家とも告白することができず、格好をつけて可愛げのない書き方をしたのだ。
ボウルのへりをヘラでくるんとすくうと、くすんだ草色のスライムみたいな樹脂がぷりんとなった。なんだか可笑しい。あの頃のませた私は、幼少の下ごしらえを経て、リアルおままごとをとうとう職業にしてしまった。
宮永愛子(みやなが・あいこ)
美術家。1974年京都市生まれ。2008年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。ナフタリンや塩、陶器の貫入音や葉脈を使ったインスタレーションなど、気配の痕跡を用いて時を視覚化する作品で注目を集める。常温で昇華するナフタリンを使った日用品のオブジェは、代表的なイメージのひとつで、時の経過により形を変えていくが、ナフタリンはケースの中で再結晶ししなやかに存在を続けていく。2013年「日産アートアワード」初代グランプリ受賞。主な展覧会に「日産アートアワード2013」BankART Studio NYK(神奈川、2013年)、「house」ミヅマアートギャラリー(東京、2013年)、「宮永愛子:なかそら―空中空―」国立国際美術館(大阪、2012年)、「景色のはじまり―金木犀―」ミヅマアートギャラリー(東京、2011年)、「あいちトリエンナーレ」愛知芸術文化センター(愛知、2010年)など。