3)創造性、持続可能性、ビジネスのバランスに向かって
サンディ・ブラックさん3
私はイギリスのサステナイブル・ファッションを理想として、彼らに追いつくべきだ、などと主張したいのではない。各国にはそれぞれの事情があり、日本でも持続可能性に取り組んでいる人たちはファッション業界にも少なからずいる。それでは、イギリスと日本は何が違うのだろうか。
———他国と比べたときのイギリスの独自性は何でしょうか。
私は「サステイナブル・ファッションの可能性の地図を描く(Mapping Sustainable Fashion Opportunities)」という欧州委員会のプロジェクトをフランス国立ファッション学院(IFM)、ミラノ工科大の研究者たちと共に行い、ヨーロッパ各国の活動を調査しました。その結果、最も活動が多いのはイギリスで、次いで小国ながらオランダが続いていました。活動が盛んなのはオランダやスカンジナビア諸国ですが、イギリスは群を抜いていました。
イギリスは「店主の国」と言われるように、起業家精神が強く、小規模事業が圧倒的に多い国です。99%が中小企業です。だからこそ「目的を持ったビジネス」が情熱とビジョンをもって行われてきました。政府の支援は十分とは言えませんが、2004年に私が最初の取り組みを始めて以来、確実に意識は高まってきています。
———政府の支援は十分とは言えないのですか。
はい。政府からの財政的な支援や税制優遇はまだまだ不足しています。小規模企業が正しいことをしても報われず、そうでない大企業が罰せられることもない。公平な競争の土俵には程遠いのです。
———英国の人々は持続可能性に取り組む小規模ブランドを支持しているのでしょうか。
確かに支えようとする人々はいますが、問題は価格です。サステイナブル・ブランドは素材や労働者への配慮のため、どうしても高価になります。たとえばレイバーン(RÆBURN)のように高い評価を得ているブランドもありますが、「最も安い選択肢」にはなりえません。
フィニステール(Finisterre)のように従業員50人ほどの中堅規模の企業もありますが、苦労を重ねています。レイバーンもスタジオ規模を縮小し、商品展開を絞っています。成功はしていますが、財政的には常に困難と隣り合わせです。

フィ二ステールのWebサイトより転載
———日本では、政府がサステイナブル・ファッションの事業者に支援をするような政策はありません。ミナペルホネンのようなブランドは独力で成長してきました。
ええ、ミナ、皆川明さんは知っています。彼らは非常に独自性があり、アーティスティックで、長く続いているブランドですね。こうしたブランドは、日本国内で根強い支持を得ています。日本は全体として、大規模生産というよりは、職人的で緻密なものづくりに価値を置く文化があり、消費者もそうしたブランドを尊重する傾向があると感じます。ただし、それが必ずしも環境や持続可能性の意識と直結しているわけではありません。
一方で、英国の小規模ブランドは、環境・倫理的な意識を前面に出して事業を行うことが多い。つまり、ブランドの存在理由やストーリーに「社会や環境への影響を変える」という明確な目的が含まれている場合が多いのです。
だからこそ、日英それぞれの文化的背景を理解したうえで、小規模ブランドやデザイナーが互いに学び合い、良い実践を共有していくことが、これからさらに重要になると思います。
———イギリスの服飾学校では若者たちの意識も変化しているようですね。
実は、教育現場のファッションデザインの教員や学生を巻き込むのが最も難しかった。長い間「次の天才デザイナーになる」という個人の創造的成功が中心だったからです。今は創造性と持続可能性、そしてビジネスのバランスを取ろうとする動きが出てきました。それは簡単ではありませんが、誰もが現状のファッションのやり方には問題があると認識していて、テキスタイルデザインやアクセサリーなどの分野でも意識が高まっているのです。
———アメリカなどでは気候変動を否定してSDGsに逆行する大統領が選ばれました。
ええ。ヨーロッパでは前向きな動きが見られますが、アメリカではまだ十分に主流とは言えません。新しい政権が気候変動を軽視する姿勢を見せていることも懸念材料です。気候変動の否定などは非常に深刻です。持続可能性を軽視することは、将来にとって危険だと思います。
———これまでの経緯を見てこられて、これからどのように変化していくと思われますか。
SDGs(持続可能な開発目標)が広く知られるようになったことは大きな助けになったと思います。大規模なファッション産業の中でも「変えなければならない」という認識が強くなり、やるべきことを理解するようになっています。カスケル(サステイナブル・アパレル連合より改名)やコペンハーゲン・ファッション・サミット、英国の政府資金による「廃棄物・資源行動計画(WRAP)」のような複数のステークホルダーによる取り組みもあり、法制度も少しずつ整いつつあります。ただし時間がかかり過ぎています。
私たちは時間切れに近づいています。1.5℃目標もほぼ達成不可能となり、落ち込むこともありますが、声を増やし、組織を増やし、私たちだけではできないことを多くの団体が担わなければなりません。
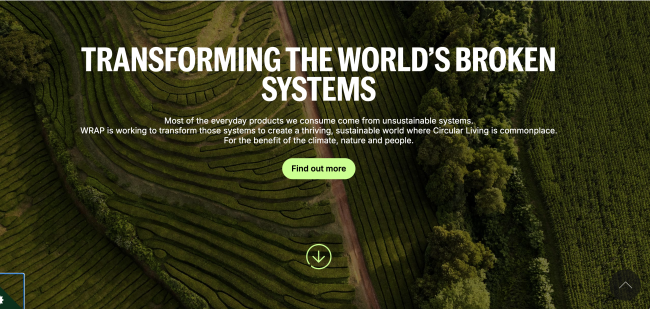 WRAPのWebサイトより転載
WRAPのWebサイトより転載
取り組みを大きく進めてきたイギリスでさえ、現状はまだ十分とは言えないところに、この「厄介な問題(=ウィキッド・プロブレム)」の困難がうかがわれる。イギリスでもコロナ禍によってファッション業界は打撃を受け、老舗百貨店や有名アパレルが倒産の憂き目にあっており、値段の安いファストファッションの人気は高いのだ(個人的な印象としては、ロンドンの繁華街にはファストファションが目立って多い)。サステイナブル・ファッションをどう進めていくか、イギリスでも模索が続いている。






