5)ファビオさんの話2 地道に、一歩ずつ
これまで紹介した以外でも、ファビオさんたちがかかわる、さまざまな人が集まれる場や就業支援の組織などがいくつもある。地区の家の向かいにつくった「ポルト・イデー(PORTO IDEE)」は、コワーキングスペースや大学生が自主的な企画を行うスペースなどが共存し、「カンバラーチェ協会(Cambalache Sociale)」は、主に移民の職業訓練を行い、養蜂をはじめ彼らの就業をサポートしている。
話を伺っていくうちに、人と人がつながるとは、本来こういうことかと実感する。かたちだけではない、有機的で優しさがある。張り巡らされたつながりはまちに生気を与えてもいる。たとえ部分的であったとしても、たしかな希望がここにあると思える。
———アレッサンドリアで仕事を始めたときに、すぐに「これは1人ではどうにもならんわ……」ってなるぐらいに、ここの社会問題は複雑で難しいなと思った。でもそう思っていたのは自分たちだけじゃなくて、保健所の人もそうだし、ここで社会的な仕事をしているいろんな人たちみんなが無力感を抱いていた。それはみんながバラバラだったから。それが一緒に仕事することで、だいぶできるようになってきた。自分たちが無力だと認めざるをえない状況があったために、他の人たちと協働してやっていこうと考えはじめたのです。イタリアではみんな「自分が誰よりもできる」って思いがちなところがあるんですけれど、それは絶対無理だという現実に直面して、すごくいい学びでした。
信頼を結んだ人たちと、ともに問題の解決を試みること。互いを尊重しながら、いっしょに知恵を出し合い、動いていくこと。ひとりひとりは無力でも、「みんなで」立ち向かえば可能になる。ここでの「つながり」や「みんなで」は決して大義名分や精神論ではない。実際の積み重ねがあるからこその、圧倒的なリアリティの言葉だ。
———自分たちが始めた仕事のしかたとしては、先にかかわる人とチームをつくっておくことです。何かイベントなどをやる場合、ふつうはまず、市長や文化担当のところに行って話します。そうではなくて、例えばコンサートをやるときには舞台を作ってくれる人がいるわけだけど、行政に話をする前に、先にその人のところに行き、あらかじめ確約を取っておいて、そのあと市長に話すんです。それで「いい案だけど、舞台をつくるチームは大丈夫かな?」と言われたときに、「全部約束取れてます」と答えると、市長も安心してお金を出すことにサインしてくれるし、舞台を作る側も信頼されていると感じていい気持ちで仕事ができる。そうすると、うまくことが実現するじゃないですか。
何か提案があったときに、必ず実現するっていう確信がみんなに広がると、信頼感が高まるわけです。うちに頼めば絶対になにかできるとか、行政との手続きもちゃんとできる人たちだとか、そういうことをわかってもらえるのは、まちで仕事をしていく上で大事な要素です。


ポルト・イデーは地区の家の向かいにある / コワーキングスペースをオーガナイズするジョルジョさん(左)とミコさん(右)。「会員たちがなるべくふれあい、つながりあうようなかたちでデザインしてきました」


カンバラーチェ協会は養蜂業のプログラム「Bee My Job」のサポートをはじめ、女性や子どもに畑仕事を教えたり、地区の家とコラボレーションして郊外に住む人たちの問題を助けたりしている
ファビオさんたちは自分を差し出すような利他的な精神で動きながら、悲壮感はなく、いきいきとしていて人間的な魅力がある。そのエネルギーの源はいったいどこにあるのだろう。
———ドン・ガッロ神父から受けたことが大きいんじゃないかと思います。彼はこうやりなさい、と教える人ではなかったですけど、25年そばにいましたから、かなり大事なことを受け取ったと思っています。何が一番大事かっていうと、人を好きになって、どんな人のなかにもポジティブな部分があるっていうのを見出すことを学びました。イタリアの男性版のマザーテレサみたいな人でしたが、ガッロさんはもう少し怒るし、面と向かって権力者を批判することもありました。
実は、自分も社会とうまくやれない青二才で、誰からも認められていなかったのですが、アレッサンドリアを飛び出してガッロさんのところに行ったら、100%信頼してくれて、いろんなことを任せてもらったんです。盲目的ではなくて、君を信頼するけど実現するのは一緒にやろうね、一緒に見ていくよ、という人でした。
ガッロ神父に助けられたのは、ファビオさんだけではない。組織にいる古参メンバーのほとんどが学んでいる。彼らがいかにガッロ神父を敬愛しているかは、地区の家に飾られている数々の肖像画や写真からも伝わってくる。ただし、活動に関しては宗教とはまったく関係ない。ファビオさんたちを支えているのはイタリアの憲法だ。
———イタリアの憲法は、市民に対してそれぞれの尊厳を認め、いろんなかたちで市民が自分たちの生活を実現するための条件を認めてくれています。選挙権やアソシエーションをつくること、政党もそうだし、人と人がつながることも。これは私が勝手に言っていることではなく、憲法に書いてあります。そういう活動を通して市民が自分の生活を実現することが謳われているんだけれども、私は非常に素晴らしいことだと思っています。
ガッロ神父は福音書と同時に憲法の価値を教えてくれました。そこにそれだけのことが書いてあるのだから、自分がイタリアという国と一種の契約を交わしたようなものだ。自分も責任をもって果たさなかったら、他の人たちの生活を貧しくすると同時に自分自身をも貧しくしてしまう。そこに書いてあることを全うすることが義務だと思っています。
*
隣人を信頼して、地道に、一歩一歩。社会を変えるとはその積み重ねでしかないのだと、ファビオさんの話を聞いて、あらためて実感する。もっとも大切なのは、特別な能力でも、ふんだんな資金でもない(もちろん、あったほうがいいけれど)。市民ひとり、ひとりが自立して、手をたずさえていけば、変化は起こりうる。アレッサンドリアはそうして変わりつつある。
ファビオさんは、私たちの小さな手土産を、行く先々でみんなに配っていた。これ、もらったんだよ。どうぞ食べて、と。彼らの活動の原点をみる思いがした。
最終回となる次回は、批評家でアーティストの多木陽介さんに話を聞いていく。イタリアに住み、この特集で取材した人たちと関係をむすびながら、彼らを見つづけ、イタリアデザインについて思考を深めてきた。そのことをまとめた多木さんの著書をひもときつつ、イタリアのデザインから日本をみていきたい。


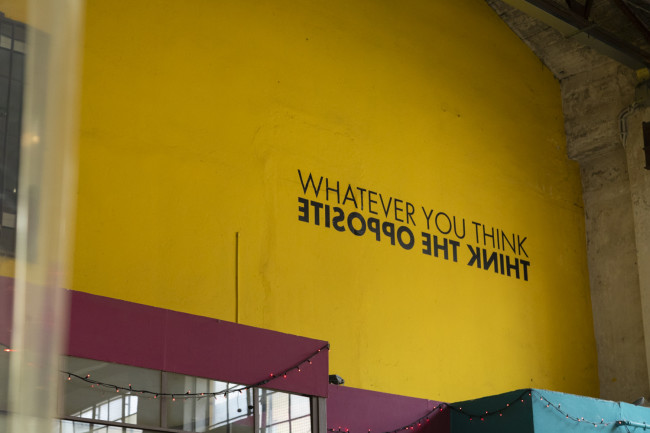
文筆家、編集者。東京にて出版社勤務の後、ロンドン滞在を経て2000年から京都在住。書籍や雑誌の執筆・編集を中心に、アトリエ「月ノ座」を主宰し、展示やイベント、文章表現や編集、製本のワークショップなども行う。編著に『辻村史朗』(imura art+books)『標本の本–京都大学総合博物館の収蔵室から』(青幻舎)限定部数のアートブック『book ladder』など、著書に『京都でみつける骨董小もの』(河出書房新社)『京都の市で遊ぶ』『いつもふたりで』(ともに平凡社)など、共著書に『住み直す』(文藝春秋)『京都を包む紙』(アノニマ・スタジオ)など多数。2012年から2020年まで京都造形芸術大学専任教員。
山形県出身、京都市在住。写真家、二児の母。夫と一緒に運営するNeki inc.のフォトグラファーとしても写真を撮りながら、展覧会を行ったりさまざまなプロジェクトに参加している。体の内側に潜在している個人的で密やかなものと、体の外側に表出している事柄との関わりを写真を通して観察し、記録するのが得意。 著書に『ヨウルのラップ』(リトルモア 2011年)
http://www.naritamai.info/
https://www.neki.co.jp/






