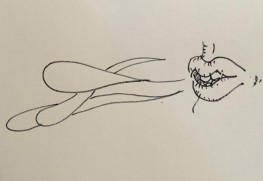(2018.03.18公開)
お彼岸が近づき、ことのほか厳しかった寒さもようやく緩んできた。新年が明けたとたんにやれ学期末試験だ、卒論の口頭試問だと目まぐるしく、慌てふためいているうち1月どころか短い2月がいつの間にか通り過ぎ、ふと我に返った時すでに3月半ばにいる自分を発見するというのは、何も今年にかぎったことでなく例年の倣いである。
来月には新学期が始まり、その準備で日々は埋まっていくのだから、3月後半のこの時期は個人的な研究に時間が充てられる貴重きわまりない一時期だと言うことができる。自分なりに当面のテーマを決めて資料を集め、考え見出したことを文章化する。こうした自律的な態度でゆったり仕事を進めたいものだと思う。だがじっさいは、個人的な仕事のはずが、外から枷に嵌められたなかですることがほとんどなのだ。
ありがたいことに、周期的にさまざまな原稿や口頭発表の依頼を受ける。たいがいは「フランス語圏文学」や「現代文学」と掲げているこちらの専門をふまえてくれてのことだ。とはいえ、「あなたの今現在の研究テーマについて自由に書いてください」などという依頼はまずない。どのシンポジウムもどの雑誌の特集も、それぞれが個性ある独自のテーマを用意しているわけで、依頼してくる相手の要求は「こちらが決めたテーマにあなたの専門をうまく合致させるような内容を用意してください」ということなのである。つまり自分の研究の範疇ではありながら、外から頂戴した新たなお題に取り組まなくてはならない。
ふり返ってこの2、3年を考えれば、たとえば「越境とリミックスの世界文学」といったテーマは、自分がふだんから考えていることの直接の延長にあり、与えられた大テーマと手持ちの具体的な事例を無理なく結びつけ提示することができた。「環境文学の視点でのフランス語圏文学」についてグループで語ることをもとめられた時は、一瞬不意を衝かれた思いでしばらく考え込む日が続いた。しかし結果としては、自分の研究を新たな方向に開く可能性を教えてもらったように思う。フランスの哲学者シモーヌ・ヴェイユの仕事をポストコロニアリズムの文脈で論じよとのお題が、これまででもっともむずかしいものだったかもしれない。テーマそのものについて深く考えるに先立ち、まったく詳しくない哲学者の膨大なテキストを読み込まねばならず、それを年度末のわずかな日数で論考にまとめるのである。短期間で修士論文をひとつ書いたようなものでもあり、それが専門家の書いた論文のなかに並ぶのだから、考えるだけで冷や汗ものだった。
さて、この春最大の目標は、3月末に東京で開かれるシンポジウムでの発表である。「フランス語圏カリブ海の女性作家について」というテーマは、ほぼ自分のテーマ通りなのでやりやすい。だがこのようにストレートなテーマを与えられた時こそ、何とかこなすのではなく、新しく価値ある内容を示さなければという気もする。ふだん業務の忙しさを理由に後回しになっている資料の解読やその考察に、慌てふためいて向かうことになる。
具体的な話になるが、大学院在学中から私が研究対象として扱っているのが、フランス語圏カリブ海のふたりの女性作家、マリーズ・コンデとシモーヌ・シュヴァルツ=バルトの作品群である。どちらも存命の現役作家で、そのコーパスは未だ流動的とはいえ、コンデは1937年、シュヴァルツ=バルトは1938年生まれで80歳を超えており、そろそろ創作活動に終止符を打っておかしくない。私だけでなく、多くの読者がそのように受け止めてきた。
それがここ数年、もう引退と思われてきた彼女たちのどちらもが競い合うようにして新しい大作を次々繰り出してくるようになったのだ。高齢での創作発表は、彼女たちが人一倍恵まれていて、体力も旺盛ということを意味しない。コンデは数年前から病気でワープロを打てなくなっており、それでも創作の欲望に抗えず、夫の介護を受けながら口述筆記で作品を仕上げた。数十年ぶりに突如新作を世に出したシュヴァルツ=バルトは、その著書に自分だけでなく12年前に亡くなったユダヤ系作家の夫アンドレ・シュヴァルツ=バルトの名も併せて記した。夫の生前ともに構想し、夫が断片として残していた草稿をつき合わせ、本のかたちに仕上げたのである。
それら精力的な仕事を読むだけでも大変だが、本が発表されればその分メディアへの露出も増え、新たな発言も追わねばならない。シュヴァルツ=バルトは、これまで長らく質の高い小品を書く寡作の作家と受け止められてきた。だが数十年の沈黙を破って突如2015年新作を発表し、そのことにより夫婦が長らく抱いてきた構想――近代ヨーロッパによる奴隷制、さらにユダヤのホロコーストのテーマが重なり合う壮大な連作小説――が明らかにされ、これまで発表されていた夫婦の個々の作品もその文脈のなかに位置づけられることがわかったのだから、読者にはまさに衝撃であった。この新たな共作としての作品群の刊行は2015年より順次始まり、今年もそして来年も続くことが予告されている。今年80歳の作家だが、引退するどころではない。コンデも口述筆記という手段を得て、たとえ身体が老い衰えても、表現にはさまざまな方法があることを示してくれた。
そしてふたりの作家の活動において方法は違えど共通しているのが、伴侶との共作――コラボレーション――ということである。共作を意味するフランス語に「4本の手で書く」écrire à quatre mainsという表現があるが、ワープロを打つ現実の2本の手のほかに、かつては生きて草稿を書きつけていたアンドレの、あるいは――彼らの祖先がした口承文芸のように――今は声に表現の座を譲ったコンデの、それぞれ見えない2本の手がそこには寄り添っている。
シンポジウムでの発表を目前に、これら作家たちの濃密な新事実を次々と知り、すぐには消化しきれずただ瞠目するばかりである。こちらの理解を深めるにはじっくり時間をかけたいものだが、しめきり、そして他の仕事との兼ね合いでそういうわけにもいかない。
仕事を受けるたび、「もっと早くから読んでおけばよかった」「この分野ももっと勉強しておけばよかった」と深く後悔する。だが逆に、余裕がないなかでのしめきりや難物のテーマ指定があるからこそ、少しは先に進めていると言えなくもない。放っておいたら何も生み出さず無為に時間を過ごしてしまう私にとって、嵌められる枷こそが「生み」を助けてくれるチューターなのかもしれないと思う。