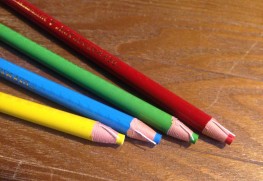(2018.02.11公開)
先日藝術学舎の訪問型授業に同行して、谷中のギャラリーSCAI THE BATHHOUSEさんにお邪魔する機会があった。ちょうどジョージア出身の芸術家、ヴァジコ・チャッキアーニの展覧会を開催していたのだが、そこで展示されていた映像作品《そこにはなかった冬(Winter which was not there)》が印象的だった。犬を連れた中年男性が、海底から巨大な石像をクレーンで釣り上げ、それを車で引きながらジョージアの風景のなかを走っていくという筋書きの映像である。恐らくは近代の英雄か偉人を象った像なのだろう、巨大で存在感に満ちた像は、車に引きずり回されるうちに徐々に砕けて、形を失っていく。
ただちに推測されるのは、その像がソ連の指導者たちの巨大な銅像を模したもので、ジョージアとロシアとの軋轢を象徴したものではないか、ということだろう。実際、あとで解説を伺ったところによると、その像はスターリンにも見えるようになっているそうだ(スターリンはジョージアの出身で、出生地の都市ゴリでは市中心部広場に設置されていたスターリン像が2010年に撤去されている)。しかし鑑賞者は、映像の冒頭でクローズアップされるその像の容貌が、実は、車を運転する当の主人公の顔によく似ていることに気づくはずだ。終始言葉なく進行するこの映像からは、明快なたった一つの解釈を導くことはできない。海底から引き上げられ、無残にも破壊されるその像は、いったい「誰」だったのだろうか? 結局主人公は、像にたいしていったい「何を」していたのだろう?
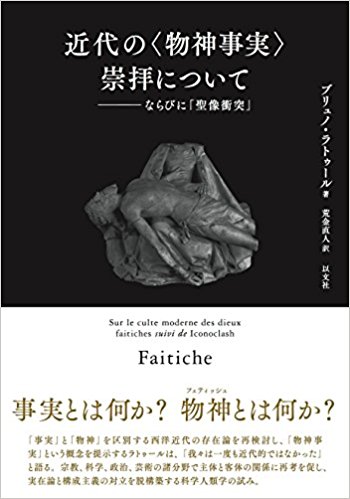
世界各地で、現在もなお、像をめぐる戦いは止むことがない。現代アートに限った話ではない。失われたバーミアン遺跡の石仏を、慰安婦像の設置をめぐる論争を、思い出してみれば良い。なぜ像は、これほどに人間の情熱と憎悪を駆り立てるのか。
昨年翻訳出版された哲学者ブリュノ・ラトゥールの著作『近代の〈物神事実〉崇拝について――ならびに「聖像衝突」』(図2)に付録として付された論考「聖像衝突」は、この問題を考える上で重要な視点を提供してくれる。このテクストは、もともとは2002年にカールスルーエのZKM(芸術メディアセンター)で行われた展覧会「聖像衝突――科学、宗教、芸術における像論争の彼方へ」のカタログ序文として書かれたものである。そこでラトゥールは、宗教論争において聖なる像の破壊を意味する「聖像破壊(iconoclasm)」に代えて、新たに「聖像衝突(iconoclash)」という言葉を提唱する。それは、像に対する行為が、破壊であるのか構築にあたるのか、俄かには判断できない状態を示唆する概念である。
どうしてそのような状況が生まれ得るのか。それは「破壊行為」とみなされるものが、その行為の動機や、像にどのような役割を認めているかといった点で複数の意味を帯び得るからだ。ラトゥールはそうした聖像破壊的所作を大まかに5つのタイプに分類しているが、このうちもっともわかりやすいのは「意図せずに破壊する」場合だろう。たとえば、修復行為がこれに相当する。芸術作品を制作された当初のオリジナルな状態に戻すことが修復だと考える人にとって、くすんだ色合いのような経年変化は、取り除かなけばならないものである。その一方で、経年変化もまた作品の一部だと考える人にとってそれは、「破壊」でしかない。それ故、そのとき修復家は、作品を直すはずの行為を通じて、「無邪気な破壊者」になる可能性があるのである。そして、これとは逆に、破壊行為がむしろ像を構築する可能性もある。「破壊行為」とは、その目的や効力について、人々のあいだに一定の了解がある場合にしか成立しないのだ。
一連の議論によってラトゥールが問題にしているのは、一見したところ「破壊行為」にしか見えないものが、いかに曖昧な意味をはらんだ行為であるかということである。そのような意味で「聖像衝突」が現代アートにおいてこれほどに問題になっているのは、宗教や科学の場合と異なって、芸術においては像が「人間的製作によるものであることを疑うことが不可能」であり、そのために像行為がはらむ曖昧さを問い直す契機を有しているからだろう。
このテクストを日本語で改めて読んでいたら、昨夏第57回ヴェネツィア・ビエンナーレのイタリア館でロベルト・クオーギ《キリストにならいて(Imitazione di Cristo)》(図1)を見たときの奇妙な印象を思い出した。アルセナーレ(造船所跡地)の薄暗い空間に、実験室のようなさまざまな機材と、ビニールハウスが広がっていて、そこに男性の身体を模した無数の像が置かれている。《キリストにならいて》というタイトル(中世の修道士トマス・ア・ケンピスによって書かれた同名の書に由来している)から察せられるように、それはキリストを模した像たちである。像は、培養基に使われるゼラチン質の有機物でできており、時間の経過とともに表面に黴が生えて乾き、固まるのだ。私が訪れたときは像に生息する黴や細菌の臭いで、しばらくそこにいるとほとんど気分が悪くなるほどだった。言ってみればキリスト像の製造工場のような体であるが、冷静に問い返してみると、それは本当に像の「製造」だったのだろうか。それはキリスト像の「破壊」ではなかったのか。いやしかし、キリストの「死」と「復活」こそがキリスト教にとって重要であるからには、むしろそこで示されていたのは、時間をかけて像が変容していく過程そのものであり、キリスト像は「破壊」されながら新しい像へと「製造」されていたのではないのか。
政治から宗教まで、社会の様々な局面に登場し、幾度も論争の対象となる像は、しかしけっして無くなることはないだろう。像を破壊することさえもが新しい像を生む。このとき重要なのは、信仰や崇拝の対象となる像の強力さだけでなく、その弱さに眼を向けることなのかもしれない。
興味を持たれた方へ:
ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について――ならびに「聖像衝突」』荒金直人訳、以文社、2017年
その他の参考文献:
Iconoclash, Latour, Bruno, and Weibel, Peter, eds.,Karlsruhe-Cambridge, Mass: ZKM-MIT Press, 2002
Il mondo magico: Padiglione Italia Biennale Arte 2017, Allemani, Cecilia, a cura di, Venezia: Marsilio, 2017