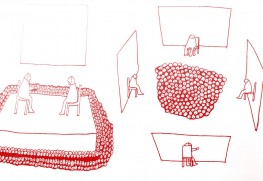(2015.06.14公開)
東京の国立新美術館で今月1日まで開かれていた「ルーヴル美術館」展が間もなく京都市美術館で開催される。イタリア・ルネサンス絵画の巨匠ティツィアーノ、バロックを代表する画家アンニーバレ・カラッチ、レンブラント、フェルメール、ムリーリョ、さらにはロココ美術の画家であるブーシェやフラゴナールそしてシャルダンの作品を一度に鑑賞することができる。世界に美術館・博物館の類はあまたある。とは言え、ルーヴルほど、質の高い貴重な品々をたくさん収蔵している美術館は稀な存在だ。またルーヴル美術館は来館者の数においても郡を抜いている。
このフランス最大の国立美術館が誕生したのは1793年8月10日とされるが、その母体となるコレクションは当然それ以前に形成されていた。その基本はそれまでの歴代国王が集めた美術工芸品などであるが、なかでもとりわけ注目すべきなのは、フランソワ1世(フランス国王在位1515−1547)がフォンテーヌブロー宮内にある「絵画室」と名づけられた部屋に蒐集した同時代のイタリア絵画である。
この王室コレクションが、ルイ14世(フランス国王在位1643−1715)の時代になるとルーヴル宮へと移動されて、さらに当時の財務総監であったコルベールが芸術を振興したことによって、そのコレクションは短期間に増加し、この頃からルーヴル宮はコレクションを展示するための館としても考えられ始める。
ルイ15世(フランス国王在位 1715−1774)の時代にはルーヴル宮で王立絵画彫刻アカデミー会員による作品展が開かれるようになり、その後ルイ16世の治世下でフランス革命が起こると、王室コレクションは国民議会によってルーヴル宮で公開されることが決められた。1793年8月10日に開館された時の名称は、ルーヴル美術館ではなく、「共和国立美術館」もしくは「中央美術館」であった。
ちなみに同じくヨーロッパを代表する美術館・博物館である大英博物館が1759年に開設、ウフィツィ美術館も18世紀末に公開されている。今回の「ルーヴル美術館」展では、開館当時のこの美術館をモティーフとしたユベール・ロベール作《ルーヴル宮グランド・ギャラリーの改修計画、1798年頃》を見ることができる。18世紀の中頃から末にかけて美術館・博物館が成立した背景には、近代的な市民社会の成立や啓蒙思想の浸透が挙げられるが、18世紀中葉に美学や近代美術史学が誕生したこともおそらく無関係ではないだろう。
近代におけるミュージアムの成立について、ルーヴル美術館を例にしてごく簡単にではあるが振り返ったついでに、コレクションについても一言ふれておこう。ルネサンス期以降になると先に述べたフランソワ1世のように、美術品を集める王侯貴族や高位聖職者あるいは上流市民が登場する。たとえば16世紀前半のイタリア人歴史家パオロ・ジョヴィオ(1483−1552)は著名人の肖像画を集めて展示するムセオ(ギリシャ語ムセイオンから派生したイタリア語で美術館・博物館を意味する)を企画した。
また16世紀後半から17世紀前半にかけて活動したイタリア人医師ジュリオ・マンチーニ(1558−1630)は、みずからの著書である『絵画論考』(1617から1621年に起草)において、画家・美術理論家のヴァザーリ(1511−1574)やロマッツォ(1538−1592)とは異なった立ち位置、すなわち好事家(ディレッタント)の立場から絵画についての考察をおこなっている。ユニークなのはこの医者が絵画を楽しみの対象とみなし、さらには絵画の愛好家となるための条件について説いていることである。
当然、マンチーニのような好事家の存在は、商品としての美術作品、それを遣り取りするマーケットの成立を前提としている。こうした美術品の取引は、イタリアよりもアルプスの北でいち早く制度化された。たとえばアントウェルペンでは、15世紀中盤から16世紀の半ばにかけて修道院の中庭などで一般の人々を対象にした美術市場パントが開かれていた。これが16世紀の中頃になると場所を株式取引所の一画に移し、常設化されてやがて近代的な美術市場へと変貌することになる。同様の動きは他の地域にも広まった。今回の「ルーヴル美術館」展の中心となる品々は、まさに美術作品を取り巻くこうした環境の変化を経て生み出されたのである。
図:《ウフィツィの鑑定家たち》、ヨハン・ゾファニー(1733−1810)
1772-78年頃
ロイヤル・コレクション、ウィンザー城
ウフィツィを舞台に目利きを自任する貴族たちが名品について語り合っている
*この作品は「ルーヴル美術館」展には出品されていません