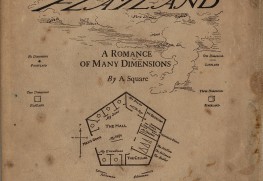(2017.01.29公開)
「待ってました」「ご両人」。歌舞伎では、場面の要所にて大向こうから役者に声が掛かる。「◯◯屋」「✕✕代目」というものや、「ご立派」「大当たり」などというものもあり、こうした声が場の雰囲気を一層盛り上げたり、引き締めたりして、劇場に心地よい一体感をもたらしている。
さて、大向こうからの掛け声のひとつに、「親父そっくり」というものがある。この言葉は、単にその役者の容姿が父親に似ていることを言い表すものではない。「親父そっくり」はその役者の芸を褒めるときに使う言葉で、とくに若い役者にとっては最高の褒め言葉である。興味深いことに、歌舞伎の生まれた江戸時代の役者評判記にも「親父どのに生きうつし」という評語がよく見られ、歌舞伎では「親父そっくり」であることが重んじられてきたことが分かる。ただ、この言葉は基本的にその役者の父親の存命中には使わない。父親の亡くなった後に、偉大な父親を慕うとともに、残された子へその芸が身体を通じて確かに伝承されていることを称える際に用いる言葉なのだ。また、「親父そっくり」であることを求める感覚は、歌舞伎に限らず、能や狂言などの他の芸能にも共通している。これらの芸能では、役者は父親の芸を受け継いでいくことを重視しているし、観客もそれを期待しているのである。
それにしても、「親父」を引き合いにした褒め方には他にもいろいろあるだろうに、父親とひと味違った個性を求めずに、父親とそっくりであることを良しとするのは、芸術に強く個性を求める現代の感覚からすれば特異なことに映るかもしれない。しかし、芸術に個性を表出するという発想は、そもそもは「芸術家(アーティスト)」や「芸術(アート)」の概念とともに近代になって西洋から入ってきたものであり、それ以前の江戸時代に生まれた歌舞伎には無縁のものであった。歌舞伎は父親から子へと代々継承する稼業であるから、役者はそれぞれの家の父親の権威を重視し、父親の身体性を繋いでいった。その意味で役者は職人であり、そこに個性をどう表出するのかということは、また別の次元の問題なのである。年齢とともに舞台経験が豊かになれば、役者は芸に膨らみを求め、若い頃に父親から受け継いだ伝承からは離れていくことが多い。しかし、次世代へ芸を伝える際には、師匠である父親から教わった土台のみを伝え、自身が工夫を凝らした部分はあえて教えない。言い換えれば、父親から習った通りに演じるというこの伝承方法こそが、歌舞伎の身体性の確かさを数百年に渡って導いてきたのである。
「親父そっくり」と声が掛かったときに、もしもそれが褒め言葉ではなくて、その芸を否定するような意味合いに聞こえてくるとしたら、それは様々な局面にて西洋の近代的な価値観がグローバルスタンダードとなっていることにも関係しているかもしれない。西洋の近代的なものはもちろん素晴らしいものであるが、しかし、「親父そっくり」という言葉から見えてくることは、グローバルスタンダードとは違ったスタンダードで捉えるべきところもあるということだ。文化や芸術を学ぶなかで、そのことは忘れずにいたいと思う。