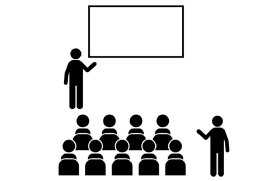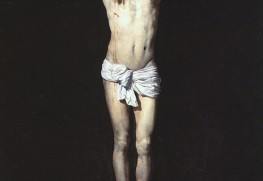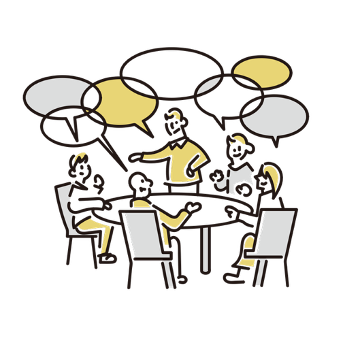
みなさんは勉強会を開催した経験があるだろうか。大学という環境にいると、自然とそのような機会に恵まれることも多い。筆者自身も、大学院生時代から多くの勉強会に参加し、ときには自ら企画、開催してきた。
ここでは、これまでに経験してきた勉強会のスタイルを振り返りながら紹介する。これから勉強会を始めてみようと考えている人にとって、何かの参考になれば幸いである。
1、読書会
読書会は、大学において最も取り組みやすい勉強会の一つだろう。読書会とは、個人的に関心のある本や話題の書籍、その分野を学ぶ上で避けて通れないような難解な専門書などを参加者全員で読み、ディスカッションするものである。
読書会の進め方には、主に二つの方法がある。一つは、各回で担当者を決めて、担当者が読解範囲を簡単にまとめた資料を作成し、議論を深めていく方法だ。この方式だと資料作成という手間がかかるものの、参加者が書籍や論文の全体像を把握しやすくなる。一番勉強になる方法だといえるだろう。特に、資料作成を担当すると、担当範囲について詳細に理解することができる。
もう一つは、その回に扱う書籍や論文だけを決め、参加者全員が事前にそれを読み、議論する方法だ。この方法だと各自の準備負担が少ないため、初めて読書会に参加する人や、忙しい人には適していると思う。
私はどちらのスタイルの読書会にも参加したことがある。どちらが良いというわけではなく、参加者のモチベーションやそれぞれの書籍に対する重要度などを踏まえて、開催形式を決めるのが良いだろう。
2、レポート/論文検討会
これは、自分が書いたレポートや論文を他の参加者に読んでもらい、コメントやアドバイスをもらうための勉強会だ。文章を他人に見せるのは、勇気がいるという方も多いだろう。しかし、回数を重ねたり、信頼できる人と開催したりすることで、徐々に不安は取り除かれていくのではないかと思う。やはり実際に読んでもらい、細部までフィードバックを受けることで、文章の構造や論点が明確になり、格段に良いものへとブラッシュアップされていく。ぜひ臆せず参加していただきたい。
こうした検討会では、どの程度のクオリティの文章を検討する会なのか、あらかじめ設定し、示しておいても良いかもしれない。例えば、すでに完成した原稿を見せるのか、アイデア段階の原稿を見せるのかによって、参加者のコメントも変わってくる。発表者と参加者の対話を有意義なものにするためにも、自分の原稿が今どういう状態にあるのかという点は共有しておいた方が良いだろう。
3、時事トピック勉強会
これは、最近友人たちと新しい形の勉強会として開催しているものだ。はじめはアイリス・マリオン・ヤング『正義と差異の政治』(法政大学出版局、2020年)の読書会として開催していたのだが、その中で、参加者それぞれが気になっているけれどきちんと調べられていない社会的なテーマやニュースの話題がたびたび出ていた。ちょうど『正義と差異の政治』を読み終わる時期と重なっていたので、読書会から方向転換し、時事トピックについて勉強する会を始めた。
この勉強会では、事前に全員が関心のあるトピックと、リサーチする担当者を決めておき、勉強会当日に、担当者のリサーチ成果を聞いて、参加者で議論し合っている。
このスタイルは、時事問題に限らず、今話題になっているテーマや専門分野で重要な概念について取り上げる勉強会にも使えるのではないかと思う。例えば芸術教養学科だと、「デザイン思考」について改めて学ぶ勉強会にも応用できそうだ。
ここまで、様々な勉強会の形式を紹介してきた。とはいえ、はじめて勉強会を開催することに不安を感じる人も多いだろう。そうした不安を一定程度解消するためにも、あらかじめ「グラウンドルール」を設定することを強くおすすめしたい。
グラウンドルールとは、参加者全員が心理的な安全を保ちつつ、意見を交わすことができるようにするための共通ルールである。盛り込むべきルールの例として、以下のようなものが挙げられる。
・他者の発言を遮らず、最後まで聞く
・批判と改善案は必ずセットで伝える
・勉強会で知り得た個人情報は口外しない
こうしたルールを明示しておくことで、主催者、参加者ともに安心して勉強会に臨むことができる。ぜひ試してみてもらいたい。
勉強会は、知識を深める場であると同時に、他者との対話を通して視野を広げる機会でもある。小さな関心から始めてもよい。自分のペースや関心に合わせて、気軽に企画してみてほしい。