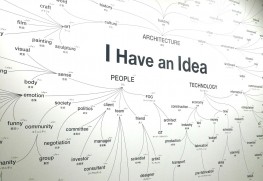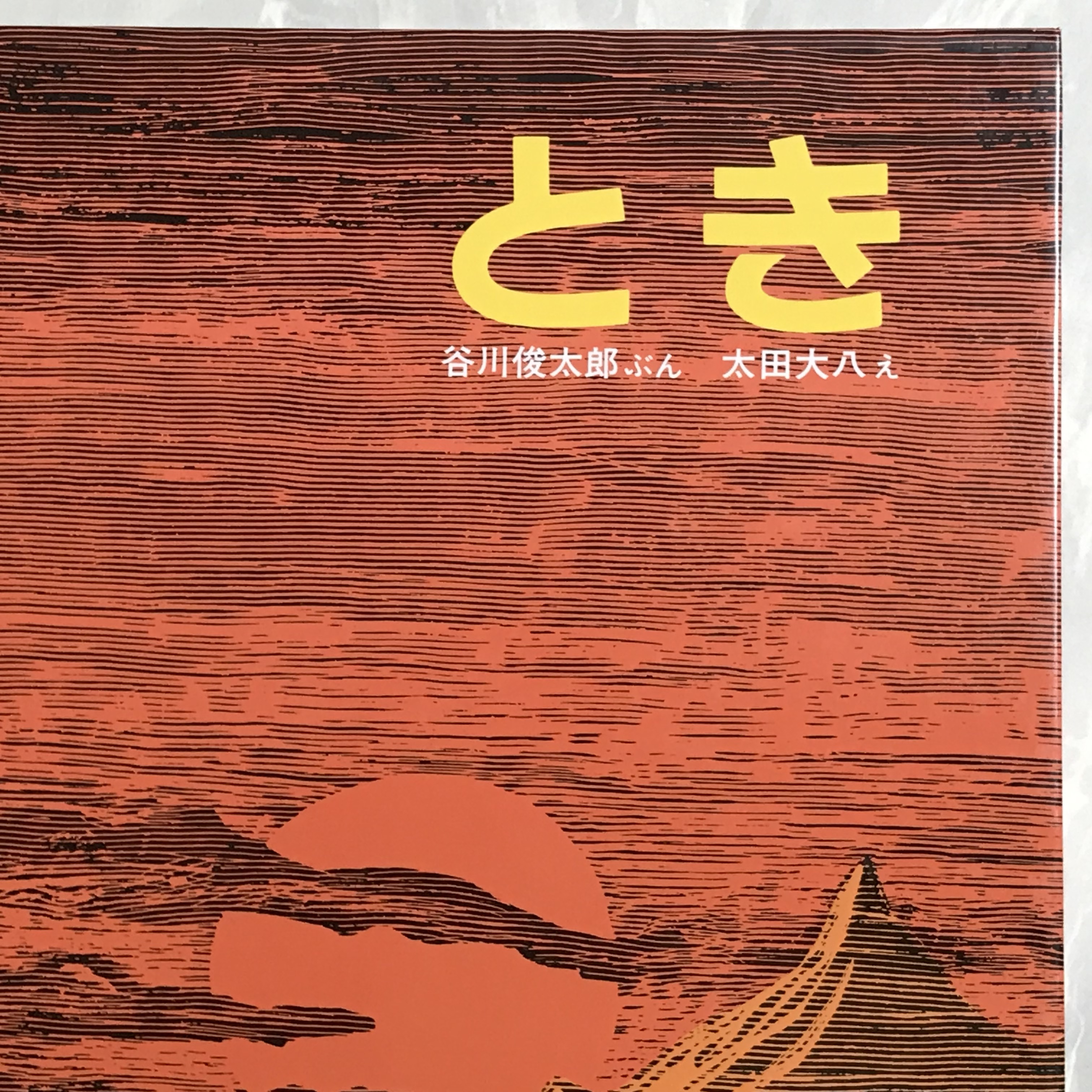
わたしと絵との最初の出会いはおそらく両親が買い与えてくれた絵本である。『きかんしゃやえもん』(著:阿川弘之/絵:岡部冬彦)あるいは『とらっく とらっく とらっく』(著:渡辺茂男/絵:山本忠敬)だったと思われる。
絵とその絵を説明することばの組み合わせ、もしくは物語とそのストーリーを説明する絵の組み合わせ、これが絵本である。幼年期のわたしは絵本に夢中になり、無意識にことば(言語)と絵(視覚的なイメージ)とを対比し、そして結びつけながら楽しんだ。しかし、やがて小学生・中学性・高校生へと成長するにつれて手に取る本からは挿絵の数が減り、いつのころからか文字ばかりの書籍を読むようになり、文字が書かれていない絵、いわゆる絵画作品を観るようになる。知らないうちに、ことばと絵を切り離し、それらを別々の存在とみなすようになったのだ。こうした変化はおそらくわたしだけにおこったことではないだろう。多くの人に共通する経験だと考えられる。
わたしは大学で西洋美術史を学び、つづく大学院では造形芸術(美術)におけるエクフラシス(視覚芸術をことばで記述すること)の問題に取り組むことになった。しかし、そもそも当時のわたしが魅力を感じていたのは、色や形そして線といった純粋に造形的な特徴から構成された近現代の芸術、とりわけ前衛芸術と呼ばれるような芸術作品であり、わたしの関心は絵画作品の主題(描かれた場面の物語)にはあまりなかった。しかし、大学・大学院での講義でイタリア・ルネサンス期の芸術と本格的に出会うや否やたちまちその虜となり、絵画作品の主題についても興味をもつようになったのである。
ルネサンス期以前の西洋美術の場合、基本的にキリスト教美術が中心を占めるため、キリスト教の教義や聖書と関連のある場面が制作されることになる。そうした絵画作品や彫刻作品は聖書のなかの一節を視覚化したイメージであるために、ただ作品の造形的な特徴だけに注目するのではなく、作品の背後にある物語(ことば)も同時に理解しなければならない。しかし、注意が必要なのは、そうした絵画作品や彫刻作品の存在意義が決して物語を観賞者に伝えることのみにあるのではない、ということである。物語を読み取ることで、絵画作品や彫刻作品のすべてを理解したことにはならないし、それらの魅力が消え失せることもない。絵本の魅力がことばと絵の両方にあるように。
冒頭で述べた二冊を含めて親に買ってもらった絵本や児童書の類は甥が引き継いだが、わたしが通っていた保育園でもらった(購入した)絵本については今も実家で大切に保管している。とくにお気に入りなのが『とき』(著:谷川俊太郎/絵:太田大八/福音館書店)である。わかりやすく、シンプルではあるが、考え抜かれた文章、そして洗練されたイラストに魅入られた。ただ、この絵本を何度も手に取り読んだにもかかわらず、こどものころのわたしはこの絵本の内容にばかり関心が向き、誰が文章を書き、誰がイラストを描いたのかということにはまったく無関心であった。それに気付いたのは二十歳を過ぎてからである。押入れを整理している最中にたまたま手に取り、共に高名な詩人とイラストレーターの共作であることを知って、驚くと同時に自分がこの絵本の世界に引き込まれた理由もわかったのである。
その文章を担当された谷川俊太郎さんが11月に逝去されました。心より哀悼の意を捧げます。
谷川俊太郎さん、太田大八さん、ありがとうございます。