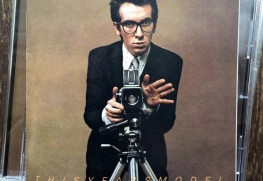(2014.07.05公開)
「カッターナイフ少年」
小学校の高学年の頃だったか、海外からやってきた透明ビニールシートを見て驚いたり、それを使って工作をした。アメリカに留学していた兄が、ボールペンシルなるものをお土産にくれたのもその頃のことで、翡翠色をしたボディは、爪痕がつくほど柔らかな初期プラスチックとでもいったもので、ペン先からはまるで鉛筆そっくりの鉛色が紙に滑り出たのを思い出す。その後国内で普及したボールペンの色は、ただの黒色でそれに赤色青色などが加わった。夏には、ペン先からブチュッとインクが溶け出るからいちいちそれを拭わなければならないのは今になっても変わらない。初期の発明品は、限りなく鉛筆のタッチに迫ったものだったと記憶する。
その頃からのぼくの必需品のひとつに、切り出しナイフがあった。朝にしっかり鉛筆を削って筆箱に納め登校したし、工作は得意科目だったから肌身離さずそれを携帯していた。凧も竹ひごを作るところから始めたし、だから友達の出来合い凧より遥かに高く揚げていた。竹笛の指孔も、切り出しナイフ一本で奇麗に仕上げてしまうのは、今に続いている。
それがカッターナイフに取って代わったのは、何時頃だっただろう‥‥‥。20歳代に上京して、デザイン事務所でアルバイトをした時、初めて手にしたような‥‥‥。ぼくなどは、様々な物が便利な製品となっていくのを体験する世代だったのかな。
これはロンドンでのことなのだけれど、カッターナイフを調達しようとしたら文具店では容易くそれが手に入れられないことが解った。ヨーロッパのどこもそうだろうか‥‥‥。
昨今は、児童が怪我のないようにとの配慮なのだろう、ある美術館でのワークショップの折に担当者が予め段ボールなどの材料を切っておくのを目にしたことがあり、過保護ぶりにはびっくりした。
アルバイトをしていた頃に培ったカッターナイフ捌きのひとつに「切り貼り」があって、その頃の印刷物は、写真植字の文字や図柄を用紙にレイアウトして原稿を整え製版に回すという行程だった。図柄を台紙の上に重ね合わせて、写真植字などの印画紙が微妙に大きくなるように刃先をやや斜めに倒してカットし、テープで裏貼りをすると製版しても原稿の貼り跡の影が出ないというぼくの技術が印刷所で重宝がられていた。
時は移って、都会を離れて暮らすようになり、1994年にベルリンでアーティスト・レジデンス生活をしていた時、カタログを制作する段になって昔取った杵柄と60ページものレイアウトを終えて印刷所に持ち込んだところ、「君の手法はオールドファッションだよ」って笑われてしまった。知らない間に、世の中はコンピューター製版に移行していたんですね。
そんな頃、カッターナイフの用途が変わっていった。ぼくは自称「あきにゃん」といって自分をとりまく毎日の暮らしぶりを猫漫画にして、「蛇足ちゃん」なる通信誌を友人たちに送っていた。相変わらずその手法はオールドファッションなので、それの通じる京都市内の印刷所にお願いをしていた。その他、葉書やレターヘッドにもその都度新しいスタンプを押していたのが「あきにゃん・消しゴム版」で、引き出しに入りきれないほどに溜まってしまった。そんな「あきにゃん・カット」が、ぴたりと止む時がやってきた。
コンテンポラリー・ダンサーの彼女が、我が人生のパートナーになってひとつの発見がそれをもたらしたのです。彼女が鼻歌まじりで机にむかっていると、決まって奇妙な絵がスケッチブックに描かれているんですね。ぼくの勧めで、二度の個展が実現しているんですが‥‥‥。その他に、ぼくは趣味のスタンプのためのカットを要求するようになって、編集者が原稿の出来上がりを待つ様子や薬の切れた患者同然に、描き上がりをもとに喜々としてカッターナイフを握る日々に変わったのですね。今は手指にナイフたこが‥‥‥。
寄る年波には勝てず老化した目なので、ほとんど心眼彫り師。日課のように彫ってきたので、溜まりに溜まったそれを今年の正月に放出するに至ったのが「けしごむアート」なる二人展で、宮北裕美(画)、鈴木昭男(彫り刷り)というものでした。
家の近くのスーパーマーケットから段ボール箱をもらってきては、カッターナイフを屈指してスタンプ画のためのフレーム制作をし、他にはスタンプ・トートバックやオリジナルノートブック、パラパラ漫画、それから透明のビニール傘も傘立てで間違って持っていかれないためのアイデアで押印を楽しんだりと‥‥‥。
少年の頃に手にした道具が、何かと生活をエンジョイし生きる意欲をもたらせてくれている。
「カッターナイフ少年」。これが、ぼくの人生リフレッシュ法なのかも。
鈴木昭男 (すずき・あきお)
1941年旧平壌生まれ。愛知県に引き揚げる。音の作家。東京から京丹後市に移住。自然に「なげかけ」と「たどり」の自修イベントを始め、創作音器のANALAPOS ’70などの制作、コンセプチュアル・パフォーマンスの時期を経てサウンド・プロジェクト「日向ぼっこの空間」を、東経135°の子午線最北の地にて遂行後、公共の場に「点 音(おとだて)」なる – 耳澄ます – イベント等を継続してきている。フェスティバル・ドートンヌ・パリ ’78 に出場の他、ドクメンタ 8 カッスル ’87、ソナムビエンテ・フェスティバル・ベルリン ’96‥‥‥近年は、AVフェスティバル・ニューカッスル ’14 などで発表。
http://www.akiosuzuki.com