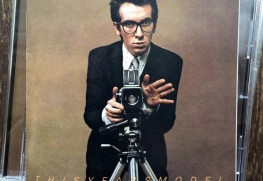(2013.06.05公開)
2,596mm×1,000mm×875mm。1,820mm×420mm×2,350mm。建築を学んでいた大学時代、建物や家具の大きさを把握するために、この距離はいくつか、この面積はどれくらいかといつも小さな物差しを持ち歩いていた。上の数字は、アイランドタイプのシステムキッチンとシステムキッチン横に設置される食器棚の縦横の長さと高さである。細やかにミリ単位で物の大きさを把握しないと気持ちが落ち着かなくなっていた。物の大きさに加えて、システムキッチンと食器棚の距離などの物と物の間、さらには人間関係ごとに微妙に異なる人と人の間まで測量するようになっていた。気になる何かがあるとすぐに測量し、その物を確認していた。
しかし、あれだけ多くの物が気になって持ち歩いていた物差しにもかかわらず、いつの間にか持たなくなっていた。わからない何かを解明しなければとそわそわしながら物差しをあて続け、測量後ほっと胸を撫で下ろしていたのに。「だいたいわかった」というニュアンスを覚え始め、物差しをかざして測量することがなくなった。物差しを持ち歩いていた大学時代には、「だいたいわかった」というニュアンスはわからず、大雑把な「だいたい」で済ますことなど許せるはずもなかった。
振り返ってみると、「だいたいわかった」という物差しを持ち始め、アバウトながら「そんな感じ」という測量をはじめていたのだ。どこにいっても「だいたいわかった」、「そんな感じ」、「いいね」という雲をつかむような雰囲気を語る言葉で済ませるようになっていた。
物差しを英語にしてみるとルーラーであり、ルールを決める物ととらえることができる。英和辞書を横においた解釈となるが、ルーラーを持ち歩いていると考えれば、「正確な長さや距離を測るための物差しを持ち歩いている」という意味はルーラーにはあてはまらない。「正確な長さや距離を測るための物差しを持ち歩いている」ということでは、既に誰かによって設定された基準にすがり、自分の中にはルールを持っていないということをさらしてしまうことになる。本当のルーラーとは、自分でつくった基準「だいたいわかった」を持ち歩いているということになるのでないだろうか。
そして、さらにルーラーとは、現実という名のライヴをいきいきと謳歌した後、そのライヴを確認するためのトレースする道具である。わからない現実にぶちあたり、右往左往しながらだいたいつかみ、わかった地点こそが、ルーラーの真の姿である。ライヴとセットとなるときのみ自分のルールが適応される。
マルセル・デュシャンは、1メートルの長さのひもを1メートルの高さから水平に落とす行為を3回繰り返し、『3つの停止原器(Three Standard Stoppages)』という定規をつくり、落下した曲がりくねったままのかたちとなっている。そしてこの定規を自身の別の作品の中で「毛細管」という名称をつけながら線をひいている。一見直線を測るという機能を喪失した定規ではあるが、この定規を使って論理的な数字に対する「純粋な偶然」を測量しようとしたのではないかと推測できる。また、『停止原器の網目(Network of Stoppages )』という作品にて、かつて自分で描いていた未完の『春の青年と少女』という絵画の上に「毛細管」がはり巡らされている。続いている男女のライヴをさらにいきいきとしたライヴ感あふれる「純粋な偶然」で測量してみたと考えることができる。
「純粋な偶然」の連なりこそがライヴであり、縦横無尽に巻き起こる現実の先頭を超高速でドライヴし続ける運転技術こそがルーラーの役割ではないだろうか。何も測らないことができる現実を進み続ける中山和也という名の定規を早く持ちたい。
中山和也
建築、プロダクトデザイン、現代美術の学習・研究機関を修了。恋人同士をありえない状況で遭遇させたり、展覧会に遅刻する作品だったり、森の中の坂道をコロコロと転がる夏みかんであったりと、展覧会場や周辺に仕込まれていたり、何かが起こったりと、今ここで起こることに注目し、日常生活と作品とのギリギリな境界線を展覧会場にあぶり出す。