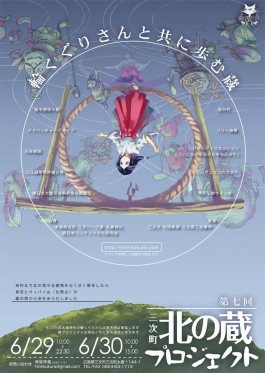(2013.07.05公開)
広島県三次市の駅横で長年経営していた喫茶店の立ち退きに遭ったのち、宇坪涼美さんが“偶然”見つけたのは130年の歴史を持つ古い酒蔵だった。酒造会社の閉鎖以来ゴミだらけだったという蔵を、現在も少しずつ改装しながら「甘味と蔵しゃぶ赤猫」「寝床と学び舎青猫」を営んでいる。人生を賭けて「再生」と「活用」のために動き続ける宇坪さんが聴いた蔵の泣き声とは。そしてその蔵の持つ力とは何だろうか。
——26歳のときに、広島のJR三次駅横で「café卑弥呼」を開かれたんですね。
20歳で結婚した後、ある料理学校の助手をしていました。私は19歳のときに大きな交通事故に遭っており、実は最初の主人というのが——というのも私は今までに結婚を3回しているのですが——その加害者の方だったんです。人生何が起こるかわかりませんよね、偶然です(笑)。その主人が駅横に土地を購入したのが始まりですね。つまり喫茶店をオープンしたのは、かっこいい野望があったわけではなく、土地のローン返済という単純な理由からでした。昭和の頃は今みたいにコンビニがなかったものだから、待ち合わせや休憩場所として喫茶店に立ち寄るというのが普通だったんですよ。結果的には賑わっているお店となりました。
——でも30年が経ったあと、駅周辺の再開発という名目で突然、喫茶店を立ち退かざるを得なくなったと。
そうですね。しかし、確かに“立ち退き”により拠点を変えなければならなくなったという状況でしたが、心境としてはポジティブなものでした。ならば新しい土地を探して、自分の好きなように家を建てようと。そう思ったときに、私は大学で空間を勉強してみようと決めました。また、今まで生きてきた中で、私は一体何を見てきたんだろうか、何ができているのだろうか、と平たく考え直していて。実は何もできていない、それなら勉強して、自分で何か家をデザインしてみたいと思うようになったんです。
旧酒蔵会社「万寿乃井」の字が今も残る
– 瓦屋根は、京都から来た瓦職人「西ヤン」が無償で直してくれた
——そんな折、人生の大きな移転先として、130年の歴史がある酒蔵を見つけられたわけですね。
交通事故がきっかけとなった結婚もそうですけれど、蔵に出会ったのも、まさに偶然によるものでした。ある5月の雨の日、知人の紹介で初めて蔵を訪れたんです。元の酒造会社「万寿乃井」が閉鎖して以来、しばらく誰も訪れることのなかった建物。暗くて、特有のむっとしたカビの臭いが鼻に入ってきました。その日、建物内に雨の音が響いていたのですが、私にとってそれは蔵の泣き声のように聴こえたんです。
古い酒蔵、と聞くと、みなさんの中で何となく“歴史のある”“いい”建物を想像されるかと思うのですが、違います。倒産した蔵というものは、お金になるものが一切なく、ゴミや廃材が散在しているだけなんです。酒蔵の生命ともいえる井戸も、放ったらかしの状態で蔵の中央に佇んでいました。
天井のベニヤ板をはずしているようす
——井戸そのものはあるのに、水が涸れていたということですか。
そうです。酒蔵にいい水は付き物なのですが、私が最初に訪れたとき、井戸はとっくに涸れていました。どうやら調べてみると、1972(昭和47)年に三次市は大水が出た(宅地が浸水した)らしいです。その災害で水脈が変わってしまって、明治時代から使っていた井戸の水が出なくなった。それから当時の社長は、隣の土地を新たに買って、ポンプを付けて、水を引いて流したそうです。社長からは「この水を使ってもいいよ」とも言われたのですが、私は結局その土地を買いませんでした。というのも、よその土地から流してきた水を、自分の体内に入れたり、お客さんにお出しするということに抵抗があったんです。そんな理由があって、無謀な挑戦ではありましたが、新しくここの敷地内で水を探すことに決めました。必ずいい水が出ると信じて。
友達にすごく勘のいいボーリング業者の方がいました。もともと建物の中央部に井戸があったのですが、「南東に掘るといいよ」と言ってくれて。彼が「ここを掘る」と決めて掘ったら、その通りに水が湧き出したんです。1分間に70リットルという、煙突に届く勢いで。そのときは本当に、天に手を合わすような気持ちでした。だからといっては何ですが、ここでお出しする地下水は、飲んでみると本当に美味しいんですよ。軟水で。正真正銘、不純物もない。
煙突のペンキ塗りをしているようす。この高さまで水が噴き上げた
——それから宇坪さんは「再生」「活用」という言葉を掲げて「蔵プロジェクト」というものを始動されますね。三次市という場所、そしてこの蔵のある土地にどういう重みを感じていますか。
紆余曲折ありましたが、結果として自分が選んだ土地です。私はここで働けば働くほど、この蔵の神様に選ばれてやってきたんだという実感が湧きます。三次市というのは、古墳がたくさん残っている地域です。霧に包まれ、3本の大きな川が流れている。その自然の恩恵を受けて、人びとは農耕をはじめとした生活を営んできました。ずっと続く血の流れを受けて自分たちは存在しているんだと、そういうことを感じさせてくれるところです。
さらにこの蔵に関わってみると、蔵を壊して新しい家を建てるものではないと気付かされました。相手は130歳の古老なんですけどね(笑)。私も含め、ここに出入りする人たちが血液となって、彼(蔵)の心臓を動かしてゆく、そういう使命感が根底にあります。
時間をかけて改装を行う中で、雨漏りなどの理由でやむを得ず一部の米蔵を壊すこともありました。あちこちにブルーシートを被せていて、埃だらけで。みっともない姿をさらし続けているんです。それを見かねて、いろいろな人が手伝いに来てくれるようになったのですが、作業をするうちに、不思議とみんな蔵にはまってしまうんですって(笑)。ライフワークになるというか。そんなみなさんの体内に潜んでいる才能を掘り起こす、というのもこの場所の魅力ですね。蔵の力を借りて、自分自身で新しい引き出しを発見できるんです。実際には泥臭い作業も多くて、とてもかっこいいとは言えないのですが。
そして知り合いはもちろん、大学時代の教授や仲間も、思い出したかのように訪ねてくれます。蔵に「帰ってくる」という言い方をしてくれる人もいますよ。幸せですね。
卑弥呼蔵パンフレット
——蔵内にある「甘味と蔵しゃぶ赤猫」「寝床と学び舎青猫」という名前は、どこから?
540坪の敷地内の道路面に「赤猫」、東側に「青猫」があります。「赤猫」「青猫」という名前は、「赤鬼」「青鬼」の意味を孕んでいて、神様も鬼も、人間も動物も、みんながこの蔵でご飯を食べたり、遊んだり、泊まったりできるという願いを込めています。みんなの居場所と出番がちゃんとあるようにと。看板猫もいるんですよ。
実は酒蔵を購入した翌年の3月に、ここの元社長が亡くなったんです。お葬式に行った帰り、私はふらっと蔵に立ち寄ってみました。どこか湿っていて、妖怪が出そうな雰囲気でした。すると案の定、蔵の奥から物音が聴こえてくるんですよね(笑)。どうしよう、昼でも出るんだ!と思って怖くなりながらも、音のほうをじっと凝視してみると、1匹の猫がそっと現れた。それから真っ黒の喪服を着た私の膝にぽんと乗っかってきたんです。何だろう、この猫は?と驚いたのですが、思わず「社長」と呼びかけてしまいました。それがこの猫なんです。彼女は、元の酒蔵会社の名前「万寿乃井」から付けて、万ちゃんと言います。今では、この猫を紹介するときは「うちの社長です」と説明するんですよ(笑)。
この蔵を自由に行き来する「万ちゃん」
改装作業は今日も続く
——それは面白いですね。宇坪さんは、これから蔵と一緒に歩む人生をどのようにお考えですか。
もちろん、再生のプロジェクトは10年間(2007年〜2016年)、責任を持って続けてゆきたいですね。ただ正直、この「延命したい」という選択が本当に正しいのか、葛藤もあります。しかし何といっても、蔵の「生命」を預かっているわけですから。
昔から「枯れ色の美しい草になりたい」という言葉を腹に据えて生きています。花ではなく、人に踏まれる「草」です。ぺちゃんこになって死んでもいいんじゃないかな。努力の果てに、蔵がこれからどのような形になってゆこうとも——たとえ形が無くなってしまう日が来るとしても——お風呂上がりのような、さっぱりとした気持ちで、笑っていたいですね。
2013年6月29日・30日に開催した「第七回三次町北の蔵プロジェクト」ポスター。イラスト:宇河弘樹
インタビュー、文 : 山脇益美
2013年6月3日 電話にて取材
宇坪涼美(うつぼ・すずみ)
広島県呉市生まれ。調理師免許取得後、26歳でJR三次駅隣に「café卑弥呼」をオープン。2008年京都造形芸術大学通信教育部空間演出デザインコース卒業、2012年同大学学芸員課程修了。2007年三次町本通商店街の北端に位置する旧万寿乃井酒造の廃蔵をコミュニティ拠点として再生するための「蔵プロジェクト」を始動。2010年〜2012年「三次さくら祭」実行委員長を務めた際、“温故知新”をテーマにし、歴史ある花見行列に広島県立三次高校生による阿久利姫のファッションショーを企画するなど、和装文化の発信、地域の活性化にも取り組んでいる。夫はコミック『朝霧の巫女』著者、宇河弘樹。卑弥呼蔵URL http://himikokura.com
広島県三次市三次町1144-1
山脇益美(やまわき・ますみ)
1989年京都府南丹市生まれ。2012年京都造形芸術大学クリエイティブ・ライティングコース卒業。今までの主な活動に京都芸術センター通信『明倫art』ダンスレビュー、京都国際舞台芸術祭「KYOTO EXPERIMENT」WEB特集ページ担当、NPO法人BEPPU PROJECT「混浴温泉世界2012」「国東半島アートプロジェクト2012」運営補助、詩集制作など。