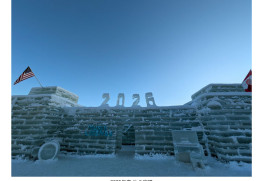ヤマトヤシキ、トキハ、リウボウ。
左から、加古川、大分、那覇の百貨店です。見知らぬ街の聞き慣れない百貨店の名称には、謎めいた響きがあって、旅情すら掻き立てられます。
かつて山口には「ちまきや」という百貨店がありました。
山口駅から北西に向かって歩くと、懐かしい雰囲気のアーケード商店街に差し掛かります。その中心に位置する大きな店舗が井筒屋です。山口市唯一の百貨店であり、古風なレンガ調とスパイラルエスカレーターを配した豪華な増築部分との異なる2つのファサードが印象的です。

山口井筒屋
この山口井筒屋の前身がちまきやだったのです。1855年創業で呉服店をルーツに持つ老舗百貨店でしたが、2008年に閉店して北九州の井筒屋傘下の経営となりました。ちまきやという不思議な屋号は、創業者である八木宗十郎氏に由来するとされます。「八」と「木」で漢字のへんにして、「宗」をつくりにすれば粽(ちまき)という字にできるため、ちまきやと命名されたとのことです(註)。

ちまきやは現在、地元企業として百貨店業以外での営業を継続されています

珍しい看板の和菓子店
山口の街を散策していると、外郎(ういろう)が名物の和菓子店が目に付きます。それもそのはずで、山口は名古屋や小田原と並ぶ、外郎の名産地なのです。一般的な外郎の原料には米粉が使われますが、山口ではわらび粉を主原料にしています。そのため、わらび餅や水羊羹のような滑らかでプルプルとした食感に仕上がっています。特に生外郎は食感と風味がさらに優れており、現地で鮮度の高いうちにぜひ召し上がってみてください。
西日本のちまきは、三角形のおこわではなく、主に外郎を笹の葉に包んで作った甘い菓子を指します。端午の節句の行事菓子や京都祇園祭の厄除け(ただし食べられません)にも用いられる縁起物と言えます。そう考えると、大店(おおだな)のネーミングとしてちまきは相応しいものと腹落ちしました。
似たもの同志のちまきと外郎は、山口で深い縁があったのかも知れません。
(註)
寺本界雄『百貨店縁起』日本百貨店新聞社、1970年、p.179。
参考
「ちまきや閉店」『サンデー山口』2008年6月8日。
農林水産省「うちの郷土料理」、
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/43_25_yamaguchi.html(2025年10月8日閲覧)。
(三木京志)