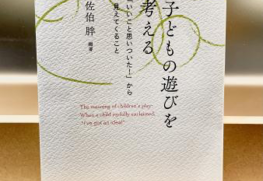(2018.01.14公開)
私の住む地域では、夕暮れ時になると、何百羽とおぼしき鳥の大群が空一面を覆い尽くすことがある。大群はさまざまな形を作り出しながら、夕空を旋回する。楕円のように長く引き伸ばされたかと思えば、ひし形に縮み、次の瞬間には横に広がる。一羽たりとも乱れないその動きに圧倒されて、つい足をとめ、見入ってしまう。近年、ムクドリが都市で大発生していることが社会問題ともなっているようだが、これがそのムクドリの襲来なのだろうか、などと思っていたところ、あるとき、彼らが飛び回ったあとに、駅前の数本の街路樹に落ち着くのを目にした。気になって、近づいてみることにしたが、樹木からは「ギューギュー」という濁音の鳴き声が猛烈な音量で響いてくる。これは相当のおしゃべりだな、と思い、目を凝らして樹の上を見るが、葉が陰となって声の主は見えない。立ち尽くす私をよそ目に、彼らのおしゃべりは途切れることがない。感心して見ていると、次の瞬間、一羽が私に「まだ家に帰らないの?」と投げかけてきたような気がして、はっと我に返った。
このときの私のように、私たちは日常的に聞こえてくる音に何らかのメッセージ性を感じとることがある。つまり、もともとその意味で発信されているわけではない音に対して、聞き手が一方的に意味をもった言語をあてはめてしまうのである。とりわけ、鳥の声については、ホトトギスが「テッペンカケタカ」や「特許許可局(とっきょきょかきょく)」、メジロが「長兵衛、忠兵衛、長忠兵衛(ちょうべい、ちゅうべい、ちょうちゅうべい)」、ツバメが「土食って虫食って口渋~い、渋~い」と鳴くとはよく言われる。このように、音に対して何らかの背景を持ったメッセージを聞くことを「聞き做し」という。日本では、鳥や虫の声などに対して聞き做しが非常に豊かである。
興味深いのは、鳥の声の聞き做しには、鳥にまつわる信仰や習俗が背景にあるともいわれていることだ。とくに、人間が鳥に転生する内容をもつ「小鳥前生譚」は見逃すことができないだろう。「小鳥前生譚」には、継母に石の弁当を持たされて山へ薪取りに行った兄が餓死してホトトギスになり、その弟が山へ行くと「おとと恋しや」と鳴くなどの話がある(長野県)。転生する鳥には、ツバメやスズメ、カッコウ、キツツキなどが多い。そして、親不孝や亡くなった肉親への追慕などが鳥に転生するきっかけとなり、そうした情念が鳥の鳴き声に表われているとされる。つまり、鳥と人間との間には、情念を介した関係があり、そもそも聞き做しはそうした文化的な土壌をもとに生まれてきたものなのだ。
一方、聞き做しは、日本だけでみられる現象ではない。たとえば、『グリム童話』の「みそさざい」では、粉屋の水車の言葉に聞き做しが多用されている。この物語では、周囲に気配を感じた水車がゆっくり回りながら“Wer ist da? Wer ist da?”(そこにいるのは誰?そこにいるのは誰?)という。しかし、すぐに自分で“Der Müller! Der Müller!”(粉屋だ!粉屋だ!)と答え、慌てて“Stiehlt tapfer, stiehlt tapfer,vom Achtel drei Sechter.”(図々しく盗む、図々しく盗む、1ガロンで3ペック。)という。ヨーロッパでは、粉屋は人目をかすめるのが得意とされてきたが、この物語で描かれる聞き做しもそうした文化的な背景が土台となっている。
ところで、聞き做しは「共感覚」という、また別の視点からも捉えられるように思う。共感覚とは、「一つの刺激によって、それに対応する感覚とそれ以外の他種の感覚とが同時に生ずる現象*1」をいう。極端な例では、形に味を感じたり、文字に触感を感じたり、音に色を感じたりするなどであり、ある感覚を意識したときに別の感覚が無意識的に生じることを示す。音と言語とが親密につながることで生まれる聞き做しも、二つの感覚が同時に生じるものであるので、ある意味、音の共感覚といえるだろう。さらに、いぜんこの「アネモメトリ」のエッセイに記した「唱歌(しょうが)」(オノマトペ)も、芸能で使われる楽器の音を言語で表現するものなので、共感覚に基づくものといえる。
このように、音と言語との関わりは文化のなかで多面的なひろがりをもっている。しかし、その文化的構造には未解明のところも多く、興味は尽きない。
*注1「共感覚」、新村出編『広辞苑』、岩波書店。参照:2012年、第6版。
参考文献:川田順造『聲』、筑摩書房、1988年。