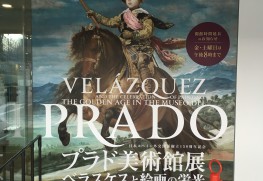(2016.02.14公開)
日本の伝統芸能の演奏には、入門曲や練習曲というものがない。あるのは、“ホンモノ”の曲ばかり。たとえば初心者が能の小鼓の稽古を始めるとしよう。多くの人が最初に習うのは、「熊野」という演目の一部のようだ。また、雅楽の場合には「越天楽」、長唄では「松の緑」が最初の曲になることが多いと聞く。いずれのジャンルにも共通するのは、練習曲ではなく“ホンモノ”の曲から習い始めるということで、初心者向けに作られた曲というものはない。
一方で、ピアノの教習について考えてみると、かつて、昭和30年代には、初心者がピアノを始める場合に定番とも呼べそうな教程が普及していたのだという*1。それは『バイエル』や『メトード・ローズ』などの教本に始まり、『ブルグミュラー』『チェルニー100番』『ピアノの練習ABC』『ピアノの練習ラジリテ-』などを経て、『チェルニー30番』『ソナチネアルバム』などに進むというものである。もちろんすべてのピアノ教室がこの通りというわけではなく、他の方法で教えたところもあるだろう。しかし、多くの場合、初心者はひたすら指の練習から進め、クーラウやクレメンティといった作曲家の作品が収められた『ソナチネアルバム』に入った頃、ようやく曲に“ホンモノ”らしさを感じとったのではないだろうか。
このように、ピアノでは最初に入門曲や練習曲をおいて、それに沿って段階的に演奏技術を向上させていく。だから、いきなり初心者に“ホンモノ”を演奏させる伝統芸能の世界とはずいぶん離れたもののように映るかもしれない。
そもそも、日本の伝統芸能において難易度が高いとされるのは、必ずしも技術的な面に基づいてのことではない。むしろ、その曲の持つ精神性が計られることが多く、「重い」あるいは「軽い」というようにその度合を表現する。当然「重い」曲ほど難しいし、芸の熟達が求められる。したがって、精神性を尊ぶ伝統芸能のあり方自体、技術を向上させて難しい曲を演奏できるようにするシステムと同一線上にあるものではない。
しかしながら、実際に教習の現場で起きていることをみると、伝統芸能もピアノもさほど違っていなかったとは指摘されているところである。ピアノの教程は暗黙のレール上にあり、それについて先生から説明されることはなく、それぞれの曲の意味や作曲家について事細かに教わることもほとんどなかった。もちろん、教わる側もそれらについてさほど疑問を持たなかったわけで、指や肘の使い方は先生のそれを真似することが求められ、理屈抜きに、そうするものだ、という刷り込みがなされていく。「学ぶは真似ぶ」といわれるが、先生にいわれるまま、まず形から入るこの方法は、まさに伝統芸能のそれと同じなのである。これについては、明治維新後の日本が西欧諸国の音楽を受け入れたとき、楽譜や楽器を介して音楽それ自体は輸入しても、音楽に対する思想や教え方は輸入しなかったことに発しているともいわれている。実際にはピアノも、伝統芸能と同じ感覚で与えられてきたといえようか。そういうなかでは、入門曲から段階的に進んでいくシステムはやりやすかったのだろうし、合理的だったに違いない。
教習のシステムは異なるが、内容としては伝統芸能もピアノもそれまでの「伝統」のなかにあり、従来の「お稽古文化」に息づいていた。謡の稽古会がピアノのおさらい会になり、着物で演奏する代わりにワンピースを着て弾くようになった。音楽大学のピアノ科を受験するには、その大学のピアノ科の先生に習ってその大学の演奏の仕方を事前に心得るようだが、そうしたある種の“流儀”に従うことが合格への道筋だとされているのを見ても、ピアノがお稽古文化で育くまれてきたのが窺えよう。
そういう目で私たちのまわりを見ると、ずいぶん多くの外来文化がお稽古文化に溶け込んでいるのに気づく。他の文化を受け入れるなかで、お稽古をする“場”は日本の文化の一つの特徴を形作ってきた。そうした文化のあり方を、改めて面白いなと思う。
*1 飯田有抄・前島美保『ブルグミュラー25の不思議 なぜこんなにも愛されるのか』(音楽之友社、2014年)に詳しい。