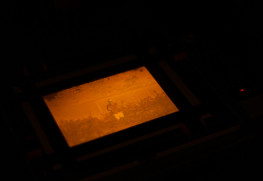(2013.05.05公開)
中学生のころから眼鏡をかけているので、この道具とは30年以上のつきあいになる。きちんと数えたわけではないが、これまで20本くらいは所有してきたはずだ。コレクターというにはほど遠いけれど、平均的ユーザーよりは多いと思う。
なぜそんな数になったのだろう。どんどん視力が落ちていくからではもちろんない。眼鏡に強いこだわりがあるわけでもない。生来の飽き性でしばらくすると新しいものに替えたくなる。そして似たようなものを買ってしまう。私にとって眼鏡とは視力矯正器具というより、気分によって着替える洋服のバリエーションなのだ。
眼鏡のデザインは洋服ほどの多様性はない。フレームは金属かセルか、色は黒か茶系かそれ以外か、レンズは丸か四角か、玉は大きめか小さめか…などがせいぜい選択できるくらいである。多くの人間は目は2つ、鼻は一つなのだから、基本の形は決まってくる。
『メガネの文化史』(リチャード・コーソン著)によれば、複玉眼鏡が発明されたのは西欧では13~14世紀らしい。それが顔に固定するつる付き眼鏡に進化したのは18世紀初頭。私たちが目にするベーシックな形が誕生して300年たつわけだが、それ以来の変遷を見てもデザインは驚くほど変化していない。18世紀ころのデザインのほうがよほど新鮮で奇抜に見えたりする。まあ毎日顔の前に乗っけるものだから、どうしても保守的になるのだろう。
そんな定型をどう料理するかが作り手の創意と工夫だ。およそデザインにはお国柄があるが、眼鏡もだいたい同じことである。ドイツ製はシャープで質実剛健、知的に見えるが面白味に欠ける。アメリカのメーカーはスポーティ、若々しさ、ポップなルックが得意。フランスはアラン・ミクリのように遊び心、カラフルさ、洗練さを感じさせるテイストに定評がある。ベルギーのテオもユニークなデザインだが、かけてみると意外に顔なじみがいい。イギリスはコンサバを基本として、ときにエキセントリックな変化球を投げてくる。国民性同様、少し変わったデザインを好むらしい。
日本の眼鏡はそれほど明確な特徴は感じないが、職人による制作をアピールするものをよく見る。セルを削り出したトラディショナルなフレームにはどこか無骨な職人気質が感じられる。「職人謹製」が売りになるのも、日本人がものづくりに思い入れをもち、職人をリスペクトする国民性からではないだろうか。福井県鯖江市は国産眼鏡の9割を生産する産地だが、欧米の有名ブランドも福井の職人の優れた技術を求めてやってくるのです、と眼鏡屋の若い店員が誇らしげに語っていた。
日本人の平たい顔には日本製がマッチするかといえば話は別で、そこは個人の好みの問題となる。ファッションと同じく、人からどう見られたいか、欲望とナルシシズムにかかわってくるのだ。
顔は人間をその人たらしめる徴表でありアイデンティティの宿る場所なのに、その肝心な顔をわれわれは直接見ることはない、と鷲田清一は指摘する。他の人からじろじろ見られているにもかかわらず、自分では定かに確かめることができない。もっとも身近にいるはずの自分の捉えにくさ、わからなさへの不安。だから、化粧は女性が自己の輪郭を確かめるためになされるという。
眼鏡は手にとって見るのと、顔にのせて見るのとでは印象はちがう。店頭で眼鏡を選ぶときはレンズに度が入っていないから、かけた自分のイメージはぼやけている。鏡で見てもよくわからない。そもそも鏡でじっと見る自分というのも、違和感や居心地の悪さを感じさせるものである。いざ眼鏡ができ上がって、レンズ越しにはっきりと自分の眼鏡姿を見たときも、「う~ん…」という感想を思わずつぶやくことはすくなくない。さんざん気苦労したあげくに出会うのは、だれのものともわからない顔なのだ。
眼鏡をかけることもまた他者の顔を自分のものにするための実践なのだろう。「むき出し」の顔に眼鏡という「加工」をすることで、「自分」のものとして了解する。眼鏡をつけた顔こそが、私にしてみれば本当の顔なのである。フロイトの説によれば、幼児が自己を形成していく重要な契機は、他者(父、母)になろうとすることであったのだから、私たちは他者になることで自分になっていくものなのだ。
地球防衛隊員モロボシダンは危機になったら眼鏡をかけてウルトラセブンに変身する。しかし、その説明は正しくない。異星人のセブンが地球上でダンというかりそめの存在に扮していたのである。セブンはモロボシダンというコスチュームを着ていたのだ。彼は眼鏡をつけることで、それを脱ぎ捨て、ようやく「本来の自分」になるのである。
セブンが「自分」になれるのは限られた短い時間でしかない。眼鏡をつけて外すまでのつかの間、自分という存在に焦点があわせられ、眼前に浮き上がってくる。しかししょせんそれも一瞬のこと。私が眼鏡に執着するのも、そんな一瞬の自分に出会うためなのだろう。
成実弘至
文化社会学、デザイン研究。京都造形芸術大学教員。著書に『21世紀ファッションの文化史』(2007年、河出書房新社)、編著に『コスプレする社会』(2009年、せりか書房)、共著に『Japan Fashion Now』(2010年、Yale University Press)などがある。