「惑星地球の時空間」展のチラシには「札幌国際芸術祭2017 吉増剛造×北大総合博物館」が「同時開催」であるとの表記があるが、この「同時開催」という言い方は、重要だ(わたしが知る限りこのチラシでしか見かけなかったが)。なぜなら、1階企画展示室の吉増剛造の展示もまた、明らかに「地球」を相手にしているからだ。
「吉増剛造 火ノ刺繍−『石狩シーツ』の先へ」では彼の長編詩「石狩シーツ」(1994)を本人が朗読する姿を映像化する試み「石狩の時間の皺皺皺皺……」(2017)を中心に、当時と今の「時間の痕跡」を展示する。3階で目にした「全球凍結」や「エディアカラ生物群」などから見れば、わずか23年、人間サイズの時間ではある。しかし、78歳になる詩人が、寿命の少なからぬ時間を使って、言葉、文字と対峙し、それを声に出している姿は感動的である。

その朗読は、観客を前にしてなされるのではない。では観客はいないのかといえばそうではない。彼は「地球」を相手に朗読しているのである。当然地球は聞く耳を持たず、むしろ風によって朗読を妨害すらするだろう。しかしそれでも、目を紙に密着させながら、聞いてもらえようが、聞いてもらえまいが、ともかく、かまわず、地球を唯一の「読者」や「観客」に見立て、声にし続ける。石狩川から日本海へ、大西洋から、地球を抱き込むように、ブラジルへと、その詩の生まれた源へと遡行する「声の旅」でも、それはあるだろう。わたしがこの数日肌身離さず持っている『完全コンプリートガイド 札幌へ アートの旅 札幌国際芸術祭2017公式ガイドブック』によれば「詩人の吉増剛造は、1994年、母国語の使えないブラジルで言葉を失うようにして帰国後、(略)石狩川河口に坐ってひたすら銅板を打刻した4か月間が代表作『石狩シーツ』に結実する」とある。
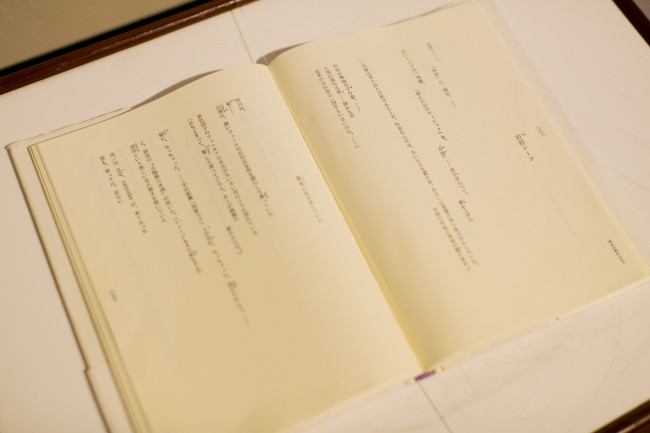
本展会場の入り口付近には、いきなり原稿を燃やす映像が流れているが、これは説明文によれば、飴屋法水によるもので、吉増剛造の原稿を託された彼が、悩んだ末、石狩川河口で燃やす。その「火」が、再び吉増によって本展タイトルへと採用された。これもまたキャプションの説明によって知ったのだが、会場の北大敷地内には、石狩川水系の再生川であるサクシュコトニ川が流れているという。遠くブラジルをここから想像するのは難しいが、不可能ではない。「不可能ではない」というのが、文学では大事なことだ。いや、そもそも生きる者にとって大事なことである。サクシュコトニ川は、石狩川へ、そしてブラジルへと繋がっている。







