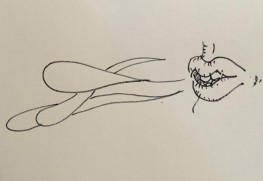(2018.01.28公開)
前回、建築家の川合健太さんが閉店してしまう定食屋さんの味について書いていた。それに触発されて、引き続き味覚について書きたい。
味は体内に取り込まれる食物によって感じられるため、触覚や運動感覚にも近い、きわめて内的な感覚であろう。しかしまた、それは身体の外にあるモノやひとや場所と強く関わっていて、単なる身体感覚ではないし、ましてや栄養成分でもない。そもそも、食べるという行為は、食物を摂取するという以上に「食事」という出来事であって、家族、同僚、友人といったコミュニティでも、またおひとりさまの孤食にあっても、暮らしの節目となる大事な機会である。どこで誰と何を食べるか、ということは舌や胃袋の問題だけではない。そして味の記憶はそのまま過去の食事の場面や、その場の人間関係の記憶と繋がっている。
特定の商品を引き合いに出すのは申しわけないが、「味の素」という化学調味料がある。人工的な化合物を食品に添加しないことが美徳になったためか、近年では余計者のように扱われることもあるようだ。しかし昔は普通に食堂にも家庭の食卓にも置いてあったものだ(いまもそうかもしれない)。こどもの頃、「味の素」を舐めてみて、このどこが味の素なのだろうかと不思議に思ったことがある。またそれが料理に使われているかどうかも、味で判別することはできなかっただろう。それでも、その白い結晶の作り出す味はしっかりと脳裏にこびりついているのだろう。
かつて、京都の木屋町沿いに、半分屋台のようなラーメン屋さんがあった。京風ラーメンならぬ京都のラーメンといえばこってりと脂っこいスープが有名だが、実はいろんなものがあって、その木屋町の小さなラーメン屋さんも、淡い澄んだ色のスープで、あっさりしつつもコクのある味だった。木屋町でラーメンを食べることは年に1回あるかないかだが、それでもたまにその味を懐かしく思いだし、その4〜5人ほどしか座れないお店に行ったことが何度かある。その何回目かに、店主の調理を見てびっくりした。カウンターに鉢を出す直前に、スプーンでさっとひとすくい、白い粉末を放り込んでいるではないか。ああこれか!と合点がいった。この薄い色のスープにこれだけしっかりした味がついているのは、味の素のおかげなのか、と。きっと小さい頃から味蕾に刷り込まれた化学調味料の記憶が秘かに親しく思い起こされていたのではあるまいか。もちろん、グルタミン酸ナトリウムのおかげでスープの味わいが濃くなったということもあるだろう。しかしそれだけでなく、化学調味料の味と、また無頓着にそれを丼に放り込む仕草とが懐かしかったということは確かにあったと思う。
そういえば、自分の母親が幼い頃、近所に「サッカリンのおっさん」がいた、という話をしてくれたことがある。「サッカリンのおっさん」はこどもたちの人気者だった。砂糖の代用品のサッカリンで作ったアイスキャンディをみんなに気前よく振る舞ってくれたからである。そのとき母親は、昔はみんな無知で、危ない食品も平気だった、とこわごわ語っていた。今は昔ほどサッカリンが危険視されることはない。そのせいか、たまに成分表示でサッカリンを見かけることがある。「サッカリンのおっさん」を知らない私も、それを見ると母親の話を思い出して、つい懐かしさを覚えてしまう。
グルメ漫画が流行ったり、食の安全が意識されている昨今は、化学調味料に頼らないお店が増えているだろうし、あるいはもっと見えない仕方で化学調味料が使われているのだろう。しかし、いまは自分の食卓には白い結晶の入った小瓶を置いていないとしても、そのひょっとしたらジャンキーな味覚はいつの間にか自分の一部になってしまっている。怖い気もするし、そんな怖い気持ち自体を疑ったりもするが、いずれにしてもその記憶は捨てるに捨てられない。それにそもそも化学調味料以前に、塩や砂糖といった結晶の匙加減のほうが切実かもしれない。