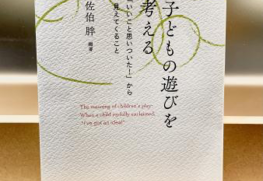(2014.07.13公開)
“音楽はいまの私たちが住んでいる社会では個性的なものであり、芸術的なものであり、すぐれた作曲家、すぐれた個性がどんどんすばらしい音楽を推進し、新しいものを創造していく、個性豊かに。そういうものが音楽だと私たちは考えがちですが、それは音楽のなれの果てだ。(笑)音楽というものがあまりにも発達しすぎちゃって、やれ著作権だの、個性だの、何だのということでもって、音楽を商品化したり、社会の中で芸術家という特別な人たちがだんだんと育ってきて、そういうようになりました。それは音楽の発達にとってはよかったのかもしれませんが、同時に人間の不幸の始まりでもあったわけです。”
小泉文夫『自然民族における音楽の発展』
(平凡社ライブラリー「音楽の根源にあるもの」pp.176-202)より
口琴という楽器をご存じだろうか。知らない人に見せると、「栓抜き?」などと返ってきたりする、そういわれてもおかしくない、そんな形の小さな楽器である。ほとんどの場合には手のひらに乗ってしまうくらいのものだ。
何年前になるだろうか。総合教育科目研究室に配属された時、そこで一緒になった藤村克裕先生が鳴らしておられて、興味を持ったのだった。この楽器には板バネのような発音体がついているのだが、これを弾いただけではほとんど音がしない。外枠を歯に押し当て、上下の唇の間で板バネを振動させて、初めて音がするのである。要は口の中で音が響き、作られるのだ。この音はおそらく皆さんも聴いたことがあるはずのものだ。音楽としてより、効果音として聴かれているかもしれない。「びよよよ〜ん」というユーモラスな音である。
舌の位置を変えたりすることで、響きに変化をつけることができる。弾きながら息を吹きかけたりすることで強いアクセントを与えたり、鼻腔や喉を開くことで共鳴部位を変えて音色を変えることもできる。指で板バネを弾くリズムに合わせて響きや音色を変化させられるようになると、大変に気持ちがよい。
「音色を変える」と簡単に言ったが、演奏中に音色を変化させることで音楽を展開していく楽器というのは、普通にはあまり見かけない。20世紀中葉に出現したシンセサイザーという楽器は、フィルターの操作によって音色(一つの音に含まれる倍音の構成によって決まる)を変化させることができ、これは現代のポピュラー音楽でもよく聴かれるものだ。それ以外だと、エレキギターのワウ・ペダルとか、電気を使わないものであればトランペットやトロンボーンのやはりワウワウ・ミュートくらいしか思いつかない。このトランペットのワウワウ音は、吉本新喜劇のテーマや笑点のテーマでも聴けるもので、やはり口琴同様ユーモラスな味わいをもっている。これらの音色は、ジャズやポピュラーで用いられることはあっても、クラシック音楽などでは例外的にしか用いられることはないように思われる。
西洋の楽器は、ピアノならピアノの音、フルートならフルートの音というのが一義的に決まっている。演奏途中で音色がふらふら変わるというのはありえない。しかし民族楽器においては必ずしもそうではないようだ。この口琴も起源は定かでないが、シベリアを一つの中心としながらユーラシア全体に分布している民族楽器で、日本でも平安時代の遺跡から出土しているという、相当に古い歴史のある楽器である。最近若い人たちの間で人気のある、オーストラリア先住民の楽器ディジュリドゥも、音色を連続的に変化させるものである。おそらくこういう楽器は世界中にあったのだが、西洋的な和声と旋律とリズムのコンポジションには似つかわしくないためか、私たちはあまり目にすることはなくなってきている。
近代の西洋音楽では、ステージと客席が画然と仕切られている。客席の市民たちに安定した音を届けるために、安定した音色とピッチ、十分な音量をもつように楽器は進化していく。今の商業音楽も基本的には同じである。優れた演奏家が大人数の観客の前で演奏する。音を大きくするために、ステレオを巨大化したようなPAシステムが組まれる。客席に届く音はCDをステレオで聴くような音像になっていく。
民族音楽に触れると、こうした当たり前だと思っていた音楽の経験のされかたも相対化されていく。例えば先の口琴小さな音の楽器だけれど、三人くらいで輪になって演奏するととても気持ちがよい。小さな音を少人数で楽しむ。微細な音色の変化に耳を澄ましあう。こういう音楽の楽しみ方というのは、小中学校の音楽の授業などでも経験しないものである。このような音の楽しみ方は、近代以降の音楽から、あるいは商業的なポピュラー音楽から、排除されてきたものなのである(※)。
口琴を始めた者が遅かれ早かれ手を出してしまうのが、ホーミー、あるいはホーメイと呼ばれる倍音唱法である。その名前を聞いたことのある人は多いだろう。これは普通に言われているところでは、「声を2つだして歌う」技術である。とはいえ、人間に喉が2つある訳ではない。一つの声を、口腔その他を駆使して2つに「分岐」するのである。もう少し正確にいうと、声に含まれている倍音成分のうち、高いものを増幅・強調するのである。なんにせよ、かなり何度の高いエクストリームな技術であるのは確かである。
至近距離でその演奏を聴いたときは衝撃的だった。まず音そのものも人間の声からくるものとは思えないものなのだが、口から出ているというより、空間が鳴っているように思われたのである。明瞭な音源の位置が感じられない不思議な音であった。こうした空間的な経験は、マイクロフォンやPAシステムを使わないことによって可能になる。そうした装置を使えば、音は「スピーカーから出た音」としての定位をもってしまうからだ。
この不思議な感じはホーメイを会得する過程にも現れた。ホーメイの高音の響きは、実は日常の発語の中にも含まれている。自分の声の中のそれに気づき、それを前景化させる努力をするのである。その響きが前面に出てくる時、私は「自分がその音を出している」のではなく、「その音が私に到来している」という印象をもった。それは具体的な振動体から直接生まれる音ではなく、口腔内の倍音のスペクトルの中から「あらわれ」「やってくる」ものなのである。こうした経験も今の音楽からは忘れられているものである。
このように、口琴やホーメイといった民族音楽の技法に触れることで、これまで意識することのなかった音楽の不思議さと可能性に気づいた。ホーメイはややハードルが高いかもしれないが、口琴は簡単に始めることができる。値段も500円くらいからとお手軽である。そして、私たちが上手いの下手だのと断じられてきた西洋音楽の基準と別のところに面白さがある。歌が上手いの、演奏が巧みだのといった私たちを苦しめてきた価値観とは関係なく、音を出す、音を聴く、ということに集中する機会をもたらしてくれる。是非これを読んでいるみなさんにもお勧めしたい。そしてそういったことを共にできる仲間を、近所で見つけてみてほしい。
最後に、昨年のスクーリング「芸術環境演習3〜8(岡山/井原)」で、私と授業参加者で録音したもの紹介しておく。
口琴ソロ:http://bit.ly/16ZXQ4Q
タンプーラとホーメイ:http://bit.ly/1e8ZIzL
いくつもの舌:http://bit.ly/1alU3yT
※:中国の内モンゴルやモンゴル共和国の「馬頭琴」も立派な音楽を多くの聴衆に聴かせるような楽器に進化しつつあり、その音色はほとんどチェロと変わるところのないものになりつつある。その原型ともいわれるトゥバ共和国の「イギル」は音量も小さくいろいろいい加減な楽器だが、その尺八のムラ音のようなノイズは私たちの意識を遠くに運び去ってしまう。