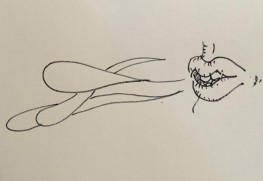(2016.06.19公開)
このところ高名な音楽家の逝去の報が相次いでいる。中でもデヴィッド・ボウイとプリンスの死は記憶に新しい。
二人とも最後まで現役であり、作り出す音楽の質において大きな影響力をもち、(多少の浮沈はあれ)世界的な尊敬を集め続けていたわけだが、私が20代だった80年代にはこの二人はヒット曲を連発し、商業的にも押しも押されもせぬ大スターであった。
東京ドームで「シリアス・ムーンライト・ツアー」のボウイを観、横浜スタジアムでプリンス・アンド・ザ・レヴォリューションのラストライブを聴いたことは、青年期の音楽体験の中でも特に印象的なものとして記憶に残っている。
革新的な天才のイメージがある二人だが、比べてみるといろいろ気づかされる。
共通するところとしては、音楽にとどまらないグラマラスな存在感、時には性についての規範を飛び越えるようなそれを持っていたことが挙げられるだろう。それと二人ともやたら大仰でドラマチックな表現とミニマムで抑制的な表現の両方に長けていたことも、共通している。それぞれの広がりは異なるが、音楽的ボキャブラリーの驚くばかりの豊富さも共通している。プリンスには20世紀アメリカのポピュラー音楽の歴史がすべて詰まっているようだ。ボウイはロックンロールからファンクに接近したりもしながら、現代音楽や現代美術にも関わりを持ってきた。
一方、ボウイが節目ごとにスタイルを変えていったのに対して、プリンスはかなり一貫したスタイルを維持したように思う。ボウイはいっときファンクに接近したが、プリンスにおいてはそれは常に基底にあった。プリンスにおいては、さまざまな時代のジャズ的なイディオム、ロック的なイディオムの中で、ジェームス・ブラウン的なもの、ジミ・ヘンドリックス的なもの、スライ・ストーン的なものは、かなり明瞭な輪郭をもって顕れる。このあたりには、プリンスが自身を音楽史上にどのように位置付けているかが現れているのだと思う。
ロックンロール・ミュージックの初期には、リトル・リチャード、チャック・ベリーといった黒人ミュージシャンが活躍していた。しかしロックという領域が産業によって輪郭付けられていくうちに、黒人ミュージシャンは同じことをしていても「ロック」の外側に置かれるようになる。それはソウルでありリズム・アンド・ブルースとして存在し、ローリング・ストーンズをはじめさまざまな音楽家に影響を及ぼしていくが、「ロック」は英米白人のものになっていく。そしてブラック・ロックは例外的な存在であり続けたように思う。そんな中で、まぎれもないロック性をさまざまな黒人音楽に溶かし込みながら爆発させていたプリンスは、かなり特別な存在だったのだと思う。黒人でもあったプリンスにとって、黒人音楽の歴史性・伝統性というものはどういうものであったのか。
話は変わるが、この芸術教養学科では「伝統」「地域的なもの」は大きな関心事である。そして「伝統」は、ある地域的な閉域で古くから育まれてきたものというイメージをまとっている。そして多くの地域おこしの物語の多くは、この閉域の「伝統」に外部のものが触れて、何かが起きる、という形式をもっている。知られざる伝統の良さが、よそから来た若者たちによって発見された、みたいなストーリーである。
地域おこしとはずいぶん違うかもしれないが、こういう構造を持つ出来事のかなり大きなものとして、60年代後半のイギリスの若者たちのブルーズ音楽への傾倒があったのではないかと思う。もちろんビートルズ以前のロックンロールも、黒人音楽をその起源にもつことは間違いないのだが、この時代のロックは、もう一度黒人音楽の祖型を問い尋ね、己のかたちを作り直したのであった。彼らは1920年代くらいからのアメリカのブルーズのレコードを敬意を持って聞き込みながら、爆音の歪んだギターによる新しい表現を生み出していった。1950年代にはすでに開発されていたエレクトリック・ギターが、うねるようなエモーショナルな表現に優れた楽器であることが改めて発見されていくのは、この時期であろう。ギター音楽としてのブルーズ・ロックは、ジミ・ヘンドリックス(彼自身はネイティブ・アメリカ人とアフリカ系アメリカ人の血を引く)のような突拍子もない達成を早い時期に得ながら、ミック・テイラー在籍時のローリング・ストーンズはもとより、クリーム、フリートウッド・マック、レッド・ゼッペリン、ピンク・フロイド…。ブルーズという伝統に触れたことで、イギリスのロック表現はさまざまな方向に急速に拡張していく。もちろんアメリカでもそうした伝統に触れる多くの優れた試みはあったわけだが、イギリスという異郷、ブルーズの伝承地から遠く離れた土地においてさえ、白人の若者達が熱心な追求を行い、新たな道を開いていったことは、興味ぶかく思われるのである。
ブルーズの伝統性というものについて、音楽学者や音楽社会学者がどのように考えているのかはよく知らない。ただそれが差別と抑圧を受けてきたアフリカ系の人々のコミュニティと結びついていること、ミシシッピ・デルタやシカゴといった土地と結びつけて語られることが多いことは確かだろう。ただこれを、閉域として語っていいのかどうかはよくわからない。そこに、海の向こうの白人の若者たち(間違いなく「外部」であろう)がのめり込み、熱心に学ぶようになった。
このあたりは、日本の地域おこしにおける「土の人、風の人」論であるとか、「よそもの、わかもの、ばかもの」論とかと通じるところがあるようにも思う。たしかにブルーズに注目した若者たちは、よそものでばかものだったのかもしれない。しかしそこから生み出されたものを考えると、今の日本に溢れる「若者が企画した地域ブランド」といったものとはずいぶ違っているように思う。彼らが生み出したものが、その「閉域」にとどまらない、新たな可能性の芽のようなものを含んでいたというのが大きかったのではないかと思う。そういうわけで、地域の古いものに向かう時に、このブルーズに傾倒した若者たちの仕事のありようのことを少し考えてみてもよいような気がするのである。そして彼らの熱中と追求は何に支えられていたのだろうかと思うのである。
ブルーズ・ロックの創始者たちは、ブルーズの音楽的資源を不当な形で搾取したのだろうか。そのあたりについては私はあまりわからないのだが、彼らの音楽が多くのリスナーや後進の関心をオリジナルなブルーズに導いたことは間違いないだろう。そしてこうした新しいブルーズ、新しいロックが黒人音楽を賦活したこともあっただろう。その残響はプリンスの音楽の中にも聞き取ることができるような気がする。
黒人音楽にとってイギリス白人の若者たちは域外者である。そして外から熱中していろいろな可能性を拓いていった。プリンスは域内者である。しかし、普通の域内者が思いつかないようなさまざまなものを生み出していった。そこには伝統に対して視点の変更を促す外部の風もあったのであろう。ある伝統に対するこの二者のありようから学び得ることは多いと思う(あれ、ボウイはどこに行ったんだ?)。